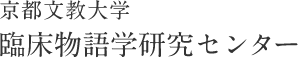2024年11月に行われる公開講演会についてのご案内です。
学外の方もご参加いただけますので、是非ご参加ください。
 ■タイトル:「九相図、時を駆ける」
■タイトル:「九相図、時を駆ける」
本センターでは2022年から継続して九相図(くそうず)の理解を深める試みに取り組んでいる。九相図とは、仏教絵画において僧侶の修行のために描かれたものが古くから残されており、死した肉体が腐敗していくプロセスが綿密に描かれたものである。生命現象の重要な働きは分解であるという指摘があり、もしそうであるならば、九相図こそが生命現象の本質を顕わにさせている絵画表現の最たるものであるとも言える。
現代日本を代表する画家として、触覚的に細部を描く近景と、世界を包むように俯瞰する遠景とを縦横無尽に行き来し、さらには時間軸や表現技法をも超越して自由自在に世界を巡る山口晃先生の手によって描かれた九相図(九相圖)では、現代的テクノロジーと生命との結合体である「何か」が朽ち果てていく。「何か」を新しく生み出しゆくことを重ねるこの現代において、それが朽ち果ててゆく様に触れることは、インフレーションしていく我々の存在を「今-ここ」に呼び戻してくれるようでもある。いにしえの仏教徒が九相図を前に何を感じ得たかを探る試みとして、現代版九相図を目にする私たちはいかに生きることの果てを捉えていくのか、山口晃先生の語りとともに考えていきたい。
■講師: 山口 晃先生(画家)
<プロフィール>
山口晃(やまぐちあきら)
1969年東京生まれ、群馬県桐生市に育つ。96年東京芸術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。2013年『ヘンな日本美術史』(祥伝社)で第12回小林秀雄賞受賞。17年桐生市初の藝術大使に就任。
日本の伝統的絵画の様式を用い、油絵という技法を使って描かれる作風が特徴。都市鳥瞰図・合戦図などの絵画のみならず立体、漫画、インスタレーションなど表現方法は多岐にわたる。
近年の展覧会に、2015年個展「山口晃展 前に下がる 下を仰ぐ」(水戸芸術館現代美術ギャラリー、茨城)、18年個展「Resonating Surfaces」(Daiwa Foundation Japan House Gallery、ロンドン)、23年「ジャム・セッション 石橋財団コレクションX山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン」(アーティゾン美術館、東京)等。2023年ニューヨークのメトロポリタン美術館に作品が収蔵される。
成田国際空港や東京メトロ日本橋駅のパブリックアート、また五木寛之氏による新聞小説「親鸞」の挿画を通算3年間担当するなど幅広い制作活動を展開。19年のNHK大河ドラマ「いだてん 〜東京オリムピック噺〜」のオープニングタイトルバック画を手がけ、東京2020パラリンピック公式アートポスターを制作。
■日時: 2024年11月20日(水)14:40~16:10
■場所: 京都文教大学 弘誓館G101教室)
■司会・対談: 倉西 宏(本学臨床心理学部准教授、京都文教大学グリーフケアトポス「Co*はこ」代表))
■ 入場: 無料
■ 申込: 不要
■ お問い合わせ: 研究支援オフィス(Tel:0774-25-2494、email:kyoumu2@po.kbu.ac.jp)
みなさまのご来場を心からお待ちしております。
 ■タイトル:「九相図、時を駆ける」
■タイトル:「九相図、時を駆ける」