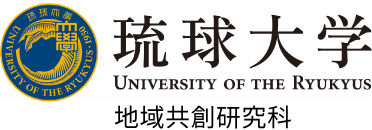Topics 2025 2025年度ニュース・プレスリリース一覧
2025.08.28
【株式会社マザーハウス 堀岡明彦氏・永田健一朗氏 】自分の想いを大切にできていれば、すでにイノベーションは始まっている。
はじめに
「途上国から世界に通用するブランドをつくる」この理念を胸に、マザーハウスは2006年に誕生しました。
創業者・山口絵理子氏が25歳で単身バングラデシュへ渡り、現地の素材と職人の技術を活かしたバッグ作りからスタートした物語は、単なるビジネスではなく「誇りあるものづくりを世界に届ける」という挑戦そのものです。
今回のインタビューでは、京都エリアの店舗統括責任者である堀岡様(京都三条メンズ店)と永田様(京都三条寺町店)にお話を伺いました。お二人は、日々の店舗運営や接客にとどまらず、理念を「自分ごと」にしながら、地域やお客様、生産国をつなぐ役割を担っています。お話の中で浮かび上がったのは、「人に向き合う」という文化と、理想と現実の間を行き来しながら成長していく柔軟な姿勢でした。
本記事では、マザーハウスがどのように理念を体現し、ブランドの価値を生み出しているのか。そして、ソーシャルビジネスに携わるうえで大切にすべき視点について、心理学的な観点からも読み解いていきます。
| 株式会社マザーハウス 設立 :2006年3月 事業内容:発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売 住所 :〒110-0016東京都台東区台東2-27-3 NSKビル1F・2F H P :https://www.motherhouse.co.jp/ |
インタビュー実施日:2025年6月23日(月)

途上国の技術と誇りを世界に届けたい
竹内:まずは、御社の会社概要や事業展開についてお聞かせください。
堀岡:マザーハウスは、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念を掲げて創業しました。代表でありチーフデザイナーの山口絵理子が25歳のときに、単身でバングラデシュへ渡り、現地で起業したことからスタートしました。
山口は学生時代、ワシントンにある途上国支援を行う銀行でインターンを経験しました。そのとき、支援金が本当に現地の人々に届いているのか、誰も気に留めていない現実に違和感を覚えたそうです。お金は実際どう使われているのか、自分の目で確かめたいという想いでバングラデシュに渡りました。
当時は、ネットで「アジア最貧国」と調べると「バングラデシュ」と出てくるような時代。「ひどい」とか「かわいそう」というイメージが先行していました。実際、現地では支援が十分に届いていない現状はありましたが、その一方で、現地の人々は自分たちの素材やものづくりに強い誇りを持っていました。
彼らの姿を見て、山口は強いギャップを覚えたそうです。同時に、「この人たちの誇りである素材を使って何かできないか」と考え、ジュート(黄麻)を使ったバッグ作りから事業をスタートさせました。「途上国の素材や技術の可能性を、日本や先進国にも届けたい」という想いが、マザーハウスの理念の原点となっています。
竹内:お二人がマザーハウスに入社されたきっかけを教えてください。
堀岡:入社を決めたのは、接客業の魅力をマザーハウスが体現していたからです。新卒で入社した会社では営業をやってきましたが、その後、ジュエリーを扱う会社で接客販売の仕事に携わり、そこで接客業にすっかり魅せられました。
日本では、接客業に誇りを持って働いている人が意外と少ない気がします。私は、接客業は素晴らしい仕事だと思うし、ジュエリー会社での経験を経て、今後の人生を接客業に懸けてみたいと考えるようになりました。
マザーハウスは元々顧客として利用していましたが、当時からスタッフの熱量を感じていました。スタッフの誰もが自分の仕事に誇りを持ち、会社やブランドについて自分の言葉で語っていたからです。
実は、途上国支援という理念自体は後から知りました。最初は純粋に、仕事や現場の雰囲気に惹かれて入社しましたね。
永田:私は堀岡とは対照的で、「社会課題を広く伝えていく」という企業の使命に共感したからですね。私自身が社会問題全般への興味が強く、特に環境やジェンダーの課題などに関心を持っていました。
バングラデシュのような途上国でのボランティア経験はありませんでしたが、学生時代はNPO活動にも積極的に関わり、社会課題や環境教育に関する取り組みも経験しました。とても有意義な経験でしたが、ただ、そうした活動に集まる人たちは、「すでに社会課題に目を向けることができている人」なんですよね。
私が問題意識を届けたいのは、むしろ枠の外側にいる人たちです。もっと広く社会課題を伝えていきたいと考えたとき、それを最も楽しく、前向きに実践しているのがマザーハウスだと思いました。自分自身の専門分野とは異なりましたが、ここで学べること、挑戦できることがたくさんあると感じたことが決め手になりましたね。

「人に向き合うこと」が自分自身の働きやすさにもつながる
竹内:現在のお仕事での役割についてもお聞かせください。
堀岡:今は京都三条メンズ店の店舗統括責任者を務めています。いわゆる店長職としてのマネジメントに加え、実際に店頭に立って接客や販売も行っています。
マザーハウスでは、従来の「店長」という呼称をあえて「店舗統括責任者」としています。これは、1つの店舗の裁量権を統括責任者が全て担う、という考え方があるからです。
副社長の山崎からも「店長は中小企業の経営者だ」とよく言われます。店舗の未来をしっかりと描き、そこに向けてどんなアクションを設定していくか、といったビジョンづくりや計画立案も、店舗統括責任者の役割ですね。
永田:私も堀岡と同じく店舗統括責任者、いわゆるプレイングマネージャーとして現場に立っています。日々の業務では、目の前のお客様一人ひとりとしっかり向き合いますが、同時に中長期的な視点で店舗運営を学ばせてもらっています。
店舗統括責任者は店舗ごとに年間計画を立てます。山口や山崎が参加する場で、それを発表する機会もあります。こうした機会を会社が積極的に設けてくれていることは、自分の視野を広げる上でとてもありがたいですね。
竹内:実際に店頭に立ちながら経営的な視点も持つというのは、かなり難しい部分もあるのではないかと思いますが、どのようにマインドの切り替えをされていますか?
堀岡:それはもう試行錯誤の連続ですが(笑)、チームマネジメントは意識するようにしています。具体的には、メンバー個々の目標や「何をしたいか」といった思いをしっかり把握したうえで、自分の苦手な領域や、ときには得意な分野もあえて任せる、ということをやっています。
こうしてコミュニケーションを取ることで、メンバー1人ひとりと向き合うことができるようになりましたし、プレイヤーとマネージャーの役割を切り替える際にも、一呼吸おいて冷静な判断ができるようになりました。
マザーハウスは「人に向き合う」文化をとても大切にしています。メンバーのコンディションや強みを日々把握することが、結果的に自分自身の働きやすさにもつながっていると感じています。
永田:私は状況に応じて「主語」を切り替えることを心がけています。
マザーハウスは、ある意味でとても欲張りな会社です。ビジネスとして成長を目指す一方で、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」ことを目標としています。そして、日々の店舗運営では、目の前のお客様との接客が中心になります。
つまり「ビジネス」「生産国」「お客様」という3つの重要な視点があって、状況に応じて主語を切り替えることが求められます。
お客様に向き合うときはお客様を主語に考え、生産国の職人と関わるときは彼らの生活安定や技術を守ることを大切にし、経営的な判断が必要なときは店舗全体の視点で考える。主語を瞬時に切り替えるスキルは、マザーハウスで働くうえではとても重要だと思います。

"想い"のバトンをつないでいく「ファクトリービジット」
竹内:たしかに、店舗では途上国支援を前面に出さず、あくまで商品の魅力を入口にしている、という印象を受けます。店舗での販売方針には、どのようなメッセージが込められているのでしょうか。
堀岡:スタッフは商品のストーリーを語るスキルを持っていますが、それ以外に全員が共通言語として持っている「接客指針」があります。
この指針には業界知識や接客マナー、所作に至るまで、さまざまな要素が盛り込まれています。大切なのは、「かしこまることだけが接客ではない」ということです。トップレベルのマナーから温かみのあるカジュアルなコミュニケーションまで、現場の状況に応じて自在に行き来できる接客システムを目指しています。
初めて来店されるお客様も多い中で、まずは期待に応えること、そのために対等なコミュニケーションを取ること、そして自分たちのことを好きになってもらうためのマナーの育成に力を入れています。このアプローチには私自身、非常に共感しています。
伝えたいことが多いブランドだからこそ、入口であらゆる人に届くような柔軟な対応が求められます。「接客指針」はまさにそれを実現するシステムだと思います。
竹内:良い商品を作っていても、生産現場の環境が悪ければ販売員は自信を持って販売できません。御社はこの点においても一線を画していると感じます。
堀岡:マザーハウスの取り組みは、ファッション業界では本当に珍しいと思います。今でこそ「製販一体」や「顔が見えるものづくり」が注目され始めていますが、まだまだ大量生産・大量消費が主流です。特に途上国で作られた製品には「安かろう悪かろう」というイメージが根強く残っています。
でも、マザーハウスの商品は背景やストーリーがしっかりしているから、私たちも自信を持っておすすめできます。最終的に選ぶのはお客様ですが、その選択を全力で気持ちよくサポートできるのは、やはりこのバックグラウンドがあるからでしょうね。
永田:お客様の中には、途上国で生産しているブランドだと知らずに購入される方も多いです。私たちも最初からお伝えすることはありません。お客様が知りたいと思っていただけるのであれば、もちろんお伝えします。
マザーハウスには、スタッフが生産国の工場を実際に訪れる「ファクトリービジット」という制度があります。私も2年前に、バングラデシュの工場を訪れました。現地の職人たちと交流し、日本のお客様がどれだけ商品を楽しんで使ってくださっているかをプレゼンさせてもらいました。
こうした経験は、スタッフにとっては大きな学びですし、現地の職人にとってもモチベーションになる。私たちが店頭に立って商品を販売することは、まるで現地の職人から受け取ったバトンをお客様に渡していくような、そんな感覚になりますね。
私もバングラデシュから帰国した後、「もっと現地とのつながりを感じられる機会を作りたい!」と思って、社内で「Tsunagaruタイム」という活動を始めました。これは、新作発表の際などに、職人がこだわったポイントにスポットを当てることで、商品をよりインタラクティブに知ることができるというものです。
「Tsunagaruタイム」だけでなく、誰かが「やってみたい」と声を上げれば、みんなで「じゃあやろう」と自然に広がっていく。ボトムアップ型の取り組みが多いのも弊社の特徴です。

多様性を受け容れ京都に新しい価値を生み出したい
竹内:御社は、京都市から「これからの1000年を紡ぐ企業」の認定も受けておられますね。
永田:8年ほど前に認定をいただきました。この認定は、経済性だけでなく、社会性や環境への配慮など、これからの1000年を担う企業としての姿勢が評価されたものです。
認定を受けたからといって、義務やノルマがあるわけではありません。どちらかといえばコミュニティ的な側面が強くて、認定企業同士の横のつながりが生まれたことが大きいですね。若手の交流会を開いたり、情報交換をしたり...こうした企業はまだまだ母数が少ないので、つながる機会を得られていることはありがたいですね。
京都市との連携というところでいうと、最近は教育分野にも力を入れています。京都市、同志社大学と連携し、探求型学習のプログラムを実施しています。
京都は大学が多く学生の街でもありますが、卒業後に他の地域へ出て行ってしまうという課題もあります。そこで、京都の企業の魅力を知ってもらうため、弊社を含む10社程度が選定されて、学生が企業訪問をしたりインタビューをしたりということをやっております。これも「これからの1000年を紡ぐ企業」の認定がきっかけで生まれた取り組みと言えますね。
竹内:京都は古都として長い歴史を持ち、100年以上続く企業も多い土地柄です。京都という場所で店舗運営をされる中で、御社の理念をどう地域に伝えていこうと考えていらっしゃいますか。
堀岡:店舗としてできるアクションの一つは、学生さんの採用です。大学生のアルバイトだと、長くても3年ほどの在籍になりますよね。その3年間で、京都の魅力や多様なお客様との交流を学んだ学生さんたちを排出していきたい。そして、彼らがさまざまな現場で活躍し、いずれまた京都に戻りたいと思ってもらえるような活動を目指していきたいですね。
京都は多くの人の憧れの地でありながら、近づき方がわからないとか、距離感の難しさを感じるという人もまた多い。でも、実際に住んでみると、京都の人々は決して壁を作ろうとは思っていなくて。でも一方でちゃんと誇りを持って、楽しく働く大人が多いという印象があります。
私自身は大阪出身ですが、京都にご縁をいただいている身として、地域と外部の人材がうまくマッチングできるような取り組みを続けていきたいと考えています。
永田:国籍も年代も性別も問わず、いろいろな人が気軽につながって楽しめる店でありたいですね。例えば、年に数回開催されるサンクスイベントでは、生産国の職人も来日してお客様と一緒にDIYを行うなど、文化を超えた交流が生まれています。
京都は海外からのお客様も多いですが、観光で消費されて終わってしまう側面も強いと、個人的に感じています。せっかく多様なお客様が訪れるのに、地元の方々とインバウンドの方々、国内旅行のお客様同士が交わる機会がまだまだ少ない。
私たちのような企業が、そうした多様性を受け容れ、つなげる場や機会を提供できれば、京都という街に新しい価値を生み出せるかもしれない。そんな想いで日々店頭に立っています。

ソーシャルビジネスには"抽象的な概念"と"具体的な行動"を行き来できるスキルが必要
竹内:本学にも「京都が好きだからこの大学に来た」という学生や、ソーシャルビジネスに興味を持つ感度の高い学生が多く在籍しています。ソーシャルビジネスに携わる上で意識していることや、学生たちに期待していることがあれば教えてください。
堀岡:前提として、全ての企業が、社会課題を解決していると思っています。その上で、重要なのは、抽象的な理念と具体的な行動を行き来することだと思います。社会課題やソーシャルグッドといった言葉は、学生さんにとっても私たちにとっても、やや抽象的な概念です。具体的に「自分が何をできるのか」まで考えなければ、社会課題は解決できないと考えています。
店舗のアルバイトさんの日々の業務は、接客や検品などが中心ですが、そうした業務はともすれば、単なる作業になってしまいがちです。しかし、彼らにも、もともと持っている「社会のために何かしたい」「将来こうなりたい」という想いがあるはずです。
それを私たちが問いかけたり、本人が振り返ることで、単なる作業にも意味を見出せるようになるし、それがおのずと自分が実現したいソーシャルグッドにつながっていくのではないでしょうか。
竹内:どれだけ素晴らしい理想を掲げていても、現場では泥臭い仕事もたくさんありますよね。理想と現実の両方を意識できる必要があるということですね。
永田:私は、自分の想いを持ち、それを言葉にして語れる人と一緒に働きたいですね。
マザーハウスは、もともと山口という一人の人間の想いから始まったブランドです。その思いに共感し、協力してくれる人がいたからこそ、ここまで大きくなってきました。私たちも会社から「何がしたいか?」を常に問われていますし、アルバイトの方にも思いを聞くことは多いですね。
例えば「家族や友人にしてあげたいこと」や「自分の住んでいる地域でやってみたいこと」とか、どんなに小さいことでもいいんです。想いを語ることで、協力してくれる人が現れ、一人ではできないことも実現できるようになる。これがチームで働くことの心強さであり、楽しさです。
もちろん、チームで働く以上、ある程度のルールや決まりごとも必要です。すべてが自由なわけではありませんが、マザーハウスも想いが重なり合った結果、大きくなったブランド。はじめは、自分の思いを口にする恥ずかしさや不安もあるかもしれませんが、みなさんの思いを聞いてみたいと私たちも思いますし、一緒に育てていけるような組織や会社でありたいと思っています。
竹内:想いは人それぞれでも、御社のスタッフはみなさんが会社の理念に共感し、活躍されています。会社の理念やビジョンをどう「自分ごと」として落とし込むかは、社会人として大切なマインドセットですよね。
堀岡:私は、「なぜこれをやるのか」という"why"を大事にしています。ともすれば、日々の業務は流れ作業になってしまいがちです。そういったとき、「これは何のためにやっているのか」と自分に問いかける。
日本はとても恵まれた環境で、何も考えなくてもそれなりに暮らしていけてしまう。だからこそ、「これって何のため?」「自分はなぜここにいる?」と立ち止まって考える時間が必要。ひょっとしたら「マザーハウスで働くことが自分のやりたいことじゃなかった」という答えにたどり着く人もいるかもしれない。でも、それも含めて、自分なりの"why"を持つことで、仕事を自分ごとにできていくのだと思います。
永田:大切なのは、まず「やってみる」ことだと思います。自分が新卒で入社した頃を振り返ると、漠然とやりたいことはあっても、ビジネスとしてそれをどう実現していいかは全然わかっていませんでした。多くの学生さんも同じように、想いはあってもスキルがない、あるいは自分の得意・不得意や好き嫌いがわからない状態でスタートすることが多いのではないでしょうか。
そういうときは、まずは行動を起こすことです。行動してみることで、自分にどんな強みがあるのかが少しずつ見えてくる。自分の輪郭が具体的になってきたとき、いつの間にかできることは増えていると思います。
バングラデシュの工場長がよく言うのが「トライファースト」という言葉です。できる・できないではなく、「どうしたらできるか」を考えることを、私自身も大切にしています。まずは小さな一歩でも踏み出してみること、それが自分ごと化の第一歩になるのではないかと思います。

自分の想いを大切にできていればすでにイノベーションは始まっている
竹内:ソーシャルイノベーションを目指して学んでいる学生たちに、京都の地でソーシャルグッドな取り組みをされているお二人から、メッセージをお願いします。
堀岡:まず、ソーシャルイノベーションを起こしたいという気持ちや、臨床心理学を通じて社会に貢献したいというビジョンを持っている時点で、すでに素晴らしいこと。そこに参画しようと一歩を踏み出しているだけで、もう大丈夫だと思います。
その大きな目標を、日常の小さな行動や具体的な実践にいかに落とし込んでいくかが、これからは大切になっていくでしょうね。例えば、日々の気づきを書き出したり、人に話してみたり、どんな形でもいいからアウトプットしてみることで、自分を客観的に見つめる時間を持ってみてください。
自分自身の想いを大切にし、少しずつでも前進していけば、すでにイノベーションは始まっていると思います。ぜひ、自分を褒めながら前に進んでいってください。
永田:すでにがんばっている自分をまず認めてあげる。そして、今をもっと楽しんでほしいですね。
社会課題に向き合うことは、ときにとてもタフなことですし、ときには考えたくない、向き合えない瞬間もあるかもしれません。でも、私たちの会社で大切にしているのは、「正しさ」よりも「楽しさ」や「美しさ」といった言葉だったりします。
人間は「正しい」だけでは動けない。これは山崎もよく言っていることです。目的を持ちながらも、目の前の取り組みをいかに楽しめるか。日々の中で「かわいい」「かっこいい」といったシンプルな感情を大切にして、肩の力を抜いて続けていってほしいです。それが、活動やビジネスを持続させる秘訣だと思います。

おわりに
マザーハウスの取り組みを通じて、改めて「理念を現場に落とし込む力」の重要性を感じました。どれだけ美しいビジョンを掲げても、日々の小さな行動に結びつけなければ、ソーシャルビジネスは持続しません。その一方で、同社の文化には「正しさ」だけでなく「楽しさ」や「美しさ」を大切にする余白があり、これが人を動かすエネルギーになっているのだと強く実感しました。
また、「ファクトリービジット」に象徴されるように、現地の職人とお客様をつなぎ、理念をストーリーとして伝える仕組みは、臨床心理学が重視する「関係性のデザイン」とも親和性が高いと感じます。ソーシャルイノベーションを目指す学生や若手人材にとっても、マザーハウスの実践は、自分の"想い"を起点に、どう現場で具体化していくかを学ぶ絶好の事例といえるでしょう。
「大学連携型ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」は、臨床心理学や地域共創の知見をもとに、社会課題の解決に挑む人材を育成します。今回の学びを糧に、私たちも引き続き「人」と「社会」をつなぐ実践を広げていきたいと思います。
京都文教大学 地域企業連携コーディネーター
竹内良地
| インタビュアー | 竹内良地 京都文教大学 地域企業連携コーディネーター / Actors合同会社COO 2017年に京都文教大学臨床心理学部を卒業後、新卒でネスレ日本株式会社に入社。セールスや企画業務を担当。2022年には人材育成・組織開発プロジェクトをオーナーとして成功に導き、社内コンテスト「イノベーションアワード」を受賞。その後、スタートアップ企業を経て、Actors合同会社の立ち上げに参画しCOO(最高執行責任者)に就任。心理学の知見を活用した企業におけるビジネス課題の解決やオープンイノベーション創出を行う「ラポトーク」事業を立ち上げ、責任者を務める。加えて、京都文教大学にて文部科学省採択事業「大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」における地域企業連携コーディネーターを務め、大学・企業・地域団体間の連携に尽力。 |
「大学連携型ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」のご紹介
龍谷大学大学院政策学研究科、琉球大学大学院地域共創研究科、そして京都文教大学大学院の3大学院が連携し、次世代のソーシャルイノベーション人材を育成するためのプログラムです。このプログラムでは、社会課題を多面的な視点から分析する力や、異なる領域の知見を統合し新たな価値を創出する力を養います。持続可能な社会の発展に貢献できる人材を育成することを目指し、臨床心理学の知見を活かしながら、社会課題解決に向けたイノベーションのプロセスやデザインを描けるイノベーション人材、そしてそのイノベーション人材を支援する心理専門家を育てていきます。