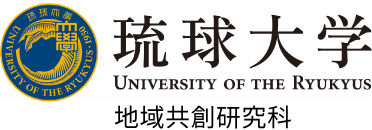Topics 2025 2025年度ニュース・プレスリリース一覧
2025.07.22
【日本新薬株式会社 高谷尚志氏・山西絢菜氏】ビジネスは結局「対人」。人を知ることがあらゆるビジネスに応用できる強みになる。
はじめに
「日本人ののむくすりは日本人の手で」という強い理念のもと、100年を超える歴史を歩んできた日本新薬株式会社。創薬という困難な領域において、難病や希少疾病に挑み、国内外で高品質な医薬品を届け続ける姿勢には、単なるビジネスを超えた使命感が感じられます。
今回のインタビューでは、人事・総務・リスク・コンプライアンス・DXを統括される取締役・高谷様と、DX統括部に所属される山西様にお話を伺いました。創薬やDX推進、ウェルビーイングの取り組み、そして「学び続ける文化」の醸成に至るまで、多岐にわたるテーマの中に一貫して流れていたのは、「人」を大切にする企業文化です。
特に印象的だったのは、「面白いから良い薬が生まれる」「ウェルビーイングな組織こそが生産性を高める」という言葉です。企業の持続的成長を支えるのは、制度や技術だけではなく、社員一人ひとりの主体性や幸福感なのだというメッセージは、臨床心理学を学ぶ私たちにとっても大きな示唆となるものでした。
本記事では、100年企業・日本新薬がこれからの時代にどのような変革を起こそうとしているのか、そしてその中で「人」が果たす役割について、心理学的な視点からも読み解いていきます。
| 日本新薬株式会社 創立 :1919年10月1日(創業1911年11月20日) 事業内容:医薬品・機能食品の製造及び販売 住所 :〒601-8550 京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14 H P :https://www.nippon-shinyaku.co.jp/ |
インタビュー実施日:2025年5月21日(水)

「日本人の薬は日本人の手で」という思いのもとに
竹内:まずは、お二方のご経歴や現在のお仕事についてお聞かせいただけますか。
高谷:私は1984年に入社しまして、気づけばもう42年目になります。もともとMR職で入社し、営業を7年ほど経験した後は、営業企画、調査企画、経営企画といった部門を担当してきました。7年前からは人事総務DXの担当取締役を務めています。
山西:私は2018年に入社し、今年で8年目です。最初は人事部人事課に配属され、6年間にわたり人事業務に携わってきました。その後、昨年度からDX統括部DX推進部DX企画推進課に異動し、現在2年目になります。
竹内:事業の概要や現在注力されている取り組みについてもお聞かせください。
高谷:私たちはもともと医薬品の製造業として創業しました。日本の医薬品企業の多くは薬種商、つまり薬の貿易からスタートしていますが、当社は最初からメーカーとして、「日本人ののむくすりは日本人の手で」という創業者の思いのもと、1919年に設立されました。今年で107年目という歴史を持っています。
1960年代には食品事業(機能食品)にも進出し、現在は医薬品と食品の2つの事業を柱として展開しています。医薬品分野では、当初は生活習慣病向けの薬が中心でしたが、現在は大手企業と競合しない難病や希少疾病の治療薬に注力しています。特に肺動脈性肺高血圧症治療剤「ウプトラビ®」と、筋ジストロフィー治療剤「ビルテプソ®」という2品目については、国内のみならずアメリカでも展開しています。
竹内:海外売上比率も全体の半分ぐらいになってきていますね。
高谷:「ウプトラビ®」は自社販売ではなく、提携パートナー経由でアメリカ市場に進出しました。ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)グループのヤンセンファーマからの評価を得て売り出しています。この成功をきっかけに、アメリカからの事業収益が大きく伸びています。
筋ジストロフィー治療剤「ビルテプソ®」については、当社がアメリカの現地法人で開発をして、自社で販売しています。現在はアメリカでの地盤固めを進めており、現地法人は約130名体制、日本からの出向者が30名強、現地採用が100名ほどとなっております。
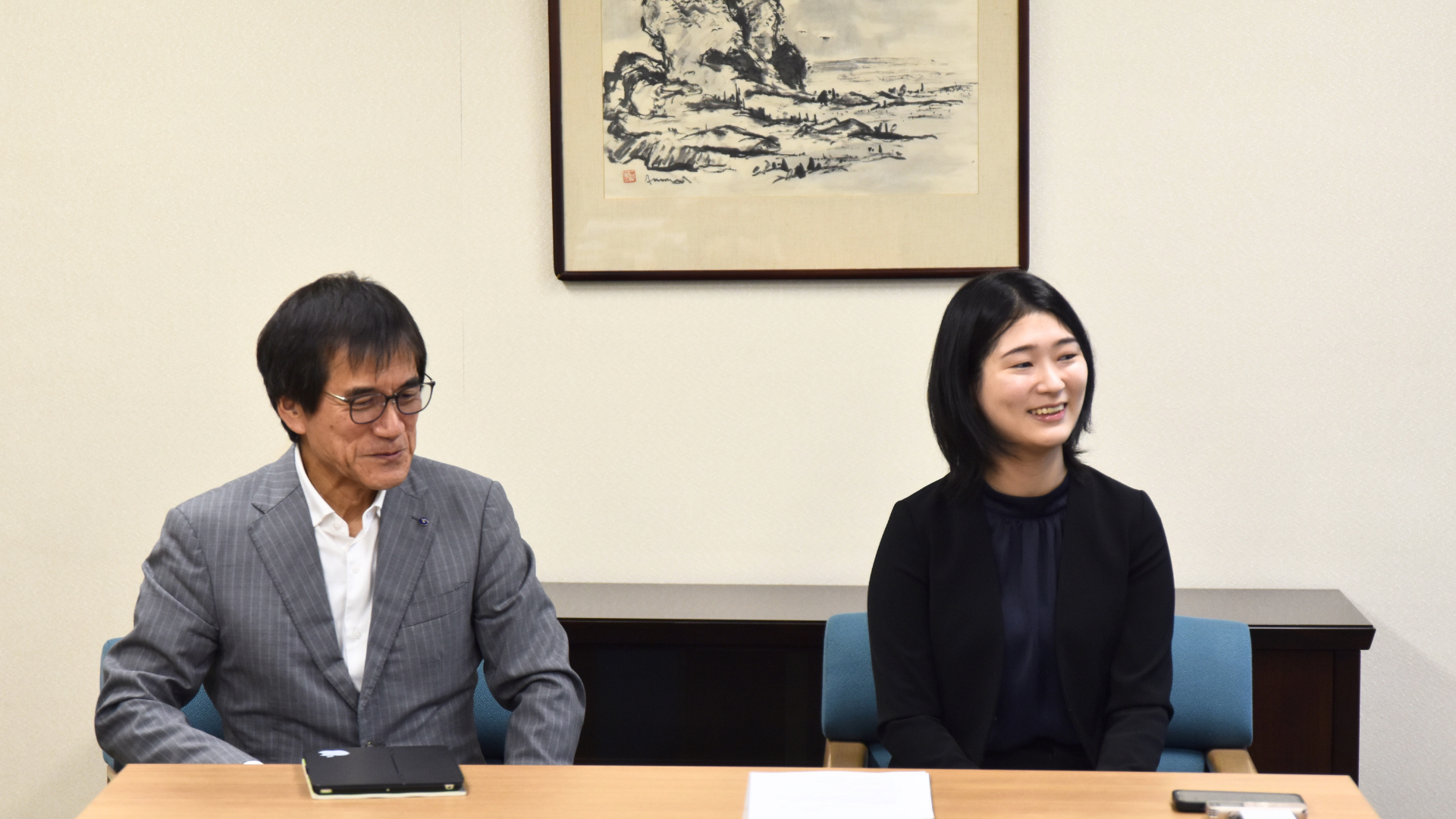
他社製品の積極投入が世界市場への足掛かりに
竹内:日本新薬という会社名には、日本発で海外に進出し、発展していきたいという思いも込められているのかなと想像します。まさに今、そういった活動をされているということですね。
高谷:107年でようやくというか(笑)そういうステージへ入らせていただいて。
竹内:海外からはどのような点が評価されていると感じますか?
高谷:他の産業でもそうですが、日本の品質は特殊なレベルにあると思います。実務家たちの間において、高いクオリティでなければ次の工程に進ませないという文化が根付いているからです。
医薬品でも日本の基準で承認されたものは、外観検査ひとつとっても「オーバースペック」と言われるほど高品質です。一方で、アメリカなど海外市場では、医薬品本来の効能・効果、つまり物質としての品質が重視されます。
逆に、私どもが海外から原材料や製品を輸入する際は、日本の品質基準でチェックするので、かなりの割合で基準に満たずにはじかれることが多い。「もう少し基準を上げて」というようなフィードバックをするケースもしばしばあります。
今後、日本の高品質をどのようにアピールしていくのか、あるいはアピールする機会を得ていくのかは、これからの課題です。
竹内:現在、売上収益が約1,600億円。10年前から倍近くに伸びていますが、どのような要因があったのでしょうか。非常に高い成長率だと感じています。
高谷:現在の会長である前川が社長に就任して以降、他社製品の国内投入をアグレッシブに推し進めてきました。自社で研究開発した薬は、自社で販売していきたいという思いもありましたが、創薬の成功確率は非常に低いのが現実です。そこで、他社が開発した優れた薬を積極的に国内に導入し、展開してまいりました。
その取り組みを続けているうちに、運良く自社開発品も発売できるようになり、そこから売上が一気に拡大し始めました。

「ウェルビーイング」という言葉に出会い完全に腹落ちした
竹内:高谷様、そして山西様もご所属されていた人事総務やDX部門について、現在メインで取り組まれている代表的な施策や業務について教えてください。
高谷:私は総務や人事、コンプライアンス、CX 、DXなどを幅広く管轄しています。特にDXに関しては、2022年に「DX統括部」を新設し、デジタル化推進に本格的に取り組み始めました。それ以前は「情報システム部」という名称でしたが、時代の流れに合わせて組織自体を再編成した形です。
最初の2年ほどは、社内のデジタル化推進やDXの啓発活動に取り組みました。今後の社会でデジタルを使いこなせないと、仕事も立ち行かなくなるという危機感があり、全社的なデジタルリテラシー向上を目指したつもりです。
また、ここ1~2年は人事制度の抜本的な改革にも着手しています。日本企業に長く根付いてきた新卒一括採用、年功序列、終身雇用といった制度。その名残を当社も色濃く残していました。ここを変えていきたかったんです。
ただし、何かを大きく変えていくときには社員も不安になる。できるだけ「明るく楽しい雰囲気」を大切にしながら意識改革を進める、ということを心がけています。
竹内:「明るく楽しくなければ」という人事の考え方について、どのような思いが込められているのでしょうか。
高谷:これは、私自身が「ウェルビーイング」という言葉に出会ったことが大きなきっかけです。
コロナ禍では、当社もでしたが「できるだけ出社しないように」という風潮が生まれました。会議がすべてオンラインになり、世の中の仕組みも大きく変わりました。それにより、それまでは東京でしか参加できなかった講演会なども、すべてオンラインになり、京都の会社でも勉強しようと思えばいくらでもできる環境になりました。
その中にはウェルビーイングに関する講演もあり、実際に学びはじめると、「これはもうすごいな」と。「人が幸せでなければ生産性は上がらない」と完全に腹落ちしまして。社員にとってウェルビーイングな環境を作ることこそが、生産性を上げることにつながると考えるようになりました。
生産性を考えるときに、「いくらお金を使った」とか「時間をどのくらいかけた」という考え方は全然つまらないというか、むしろしんどくなるんですね。大切なことは「楽しいかどうか?」であって、「楽しくないなら楽しくしようか?」っていう感じで、ざっくりやらせてもらっています(笑)。

「幸せの健康診断」でパフォーマンスが向上
竹内:心身ともに健康的な状態、いわゆるウェルビーイングの実現に向けて、御社ではどのような取り組みをされていますか。
吉田(人事部ウェルビーイング推進課長):ウェルビーイングの推進は、私が山西と一緒にプロジェクトとして始めました。体の健康診断は定期的に行いますが、「幸せの健康診断」ってやらないですよね。当社では月に1回、「自分の幸せ」を測る機会を設けています。
また、取締役にインタビューをして人となりを社員に知ってもらったり、武蔵野大学ウェルビーイング学部ウェルビーイング学科の前野隆司教授が監修した「ダイアログカード」を使って、仕事以外の話題でお互いを知り合う対話の場も設けたりして、ウェルビーイングを社内に広めていこうとしています。
竹内:「幸せの健康診断」は、継続して実施されているのですか。
吉田:武蔵野大学の前野先生とはまた別の先生にアドバイスをいただきながら、毎月1回実施しています。高谷からは「毎日でもチェックしてほしい」と言われているんですが(笑)。
今やりたいことは、毎日会社を出るときに「今日楽しかった」「がんばれた」「ぐっすり眠れそう」というボタンを押してもらう仕組みを作ることです。それを押さないとPCを閉じられへん、みたいな(笑)。でも、そこまではできていません。
「毎日歯磨きをする」くらいのレベルまで「幸せの健康診断」を習慣化できたらいいですね。自分だけじゃなく、周囲の人の幸せまで感じてもらえるような会社になれば、自然とパフォーマンスが上がっていくと思います。
竹内:実際にはどのような指標を使い、どのように変化や推移を見ていらっしゃるのでしょうか。
吉田:月に1回の「幸せの健康診断」に加えて、エンゲージメントサーベイやストレスチェックの中にウェルビーイングに関する項目を設けています。
ただ、ストレスチェックやマネージメントサーベイは定期的にはなかなかできないのが悩ましいところです。今は年1回の実施で組織ごとの状態を測り、「この部署のウェルビーイングはどうかな」という判定をしています。マネージャーが変われば、組織の状態も変化することがありますし、プライベートでの出来事が影響することもあるので、総合的に見ていく必要があります。
高谷:プロジェクトには京都大学の内田由紀子先生にアドバイザーとして関わっていただいて、今年で5年目になります。コロナ禍では人とのつながりが希薄になりがちだったので、オンラインで社員同士をシャッフルして、普段話さない人と会話する機会を作るなど、思いつくことをいろいろ試してきました。

(写真左から、日本新薬株式会社 人事部ウェルビーイング推進課長 吉田直美様、日本新薬株式会社 DX統括部DX推進部長 重野大介様)
「面白い」から良い薬が生まれる
竹内:山西さんは新入社員として最初に人事部へ配属され、その後ウェルビーイングプロジェクトにも参加されたとのことですが、若手社員の視点から会社のこうした活動をどのように受け止めていましたか。
山西:「社員を大切にする風土」は、持続的に生産性を上げていくために欠かせない要素だと考えています。当社のウェルビーイングプロジェクトの特徴は、「自分のウェルビーイング」だけでなく「周囲のウェルビーイング」にも目を向けましょう、というメッセージを発信している点です。
こうした取り組みを通じて、一人ひとりを大切にしながら組織全体の雰囲気や環境を良くしていこうとしているところが、日本新薬らしいカラーだと感じています。
竹内:「心身の健康」というと自分自身に目が向きがちですが、本来は組織として取り組むべきことだと思います。高谷さんもその点を意識されてきたのでしょうか。
高谷:そうですね。一人ひとりの健康の総和と、チームや組織全体の健康というのは少し違うものだと感じています。プロジェクトのメンバーが「周囲の人のウェルビーイング」というキーワードを掲げてくれたことは、非常に大きかったと思います。
竹内:ウェルビーイングへの取り組みを経て、会社や組織としてどのような変化を感じていらっしゃいますか?
高谷:実際にどれほど変化しているのかは、正直よくわからない部分もあります。ただ、優秀な人材が「面白い」と感じて研究に没頭できる環境があれば、必ず良い薬が生まれると信じています。
私たちの会社には何百人もの研究者がいて、ゼロからイチを生み出す仕事をしています。大切なのは、上司の指示で動くのではなく、「面白いからやってみたい」と思える雰囲気を作ることです。
「面白い」というのは、単に楽しいという意味ではなく、研究者として夢中になれるテーマに取り組める環境です。その土台づくりは全力を尽くしてやっていますよ。

人間ならではの「ひらめき」でデジタルと共存していく
竹内:DXの推進について、研究開発でのAI導入や働き方改革など、さまざまな側面があると思いますが、DX化についてどのように捉え、現在どのような取り組みをされていますか?
山西:「デジタルと人間の共存」の重要性を強く感じています。DX推進部では、デジタル活用の啓発や実際のサポートを行っていますが、現場ではまだうまく進まない部分もあります。「自分の仕事がAIやデジタル技術に置き換わるのでは」という不安感もあるようです。"人間ならでは"の部分に目を向けて、人間の強みを生かしながら、デジタルと共存していくための取り組みを進めていきたいです。
竹内:現時点で御社の中で「これは本当に人でないとできない」と感じる仕事や領域、今後も人が担い続けそうな業務とは何だと思いますか?
山西:AIに関して専門的な知見を持ち合わせているわけではなのですが、個人的に今のところ人にしかできないと考えていることの一つに、「概念を生み出す」ことがあるのではと考えます。市場やアカデミアにおいて、概念が提唱されたことによって、全く新しいサービスや製品が生まれたり、学問が発展したりすることがあるかと思います。概念を生み出すことは、視点と意志(独自の価値観と目的意識)をもって世界の現象や状態を切り取ることと言えると思いますので、そういった意味でも、一人ひとりが意志を築いていくことが重要なのではないかと考えます。
高谷:究極的には、人が「何がやりたいのか」だと思うんですね。AIがどれだけ進化しても、「意思」や「価値観」に基づく選択や決断は、今後も人の役割として残り続けるんじゃないでしょうか。何がやりたいか、何を目指すのかが決まれば、その後のプロセスはかなりの部分がAIで自動化できる。
従来のデジタル技術の使い方は、人間がやっていた仕事のプロセスはそのままにして、そのプロセスのいろんな部分をデジタルに置き換えていくという思考法でした。ところが、人間の発想で生まれたプロセスは、機械にとってはむしろまどろっこしい、非効率なプロセスだったりするわけです。 だったらAIが働きやすいプロセスに変革して、人間はチェックポイントで「決定」だけを担う形に変えてしまえばいい。これが、最近主流のいわゆる「ヒューマン‧イン‧ザ‧ループ」という考え方です。 この「決める」という行為は、合理的な正解を出すだけなら、これもやはりAIで事足りてしまいます。でも、「どっちが好きか」「何をやりたいか」といった好みや価値観による意思決定は人間にしかできないと思います。
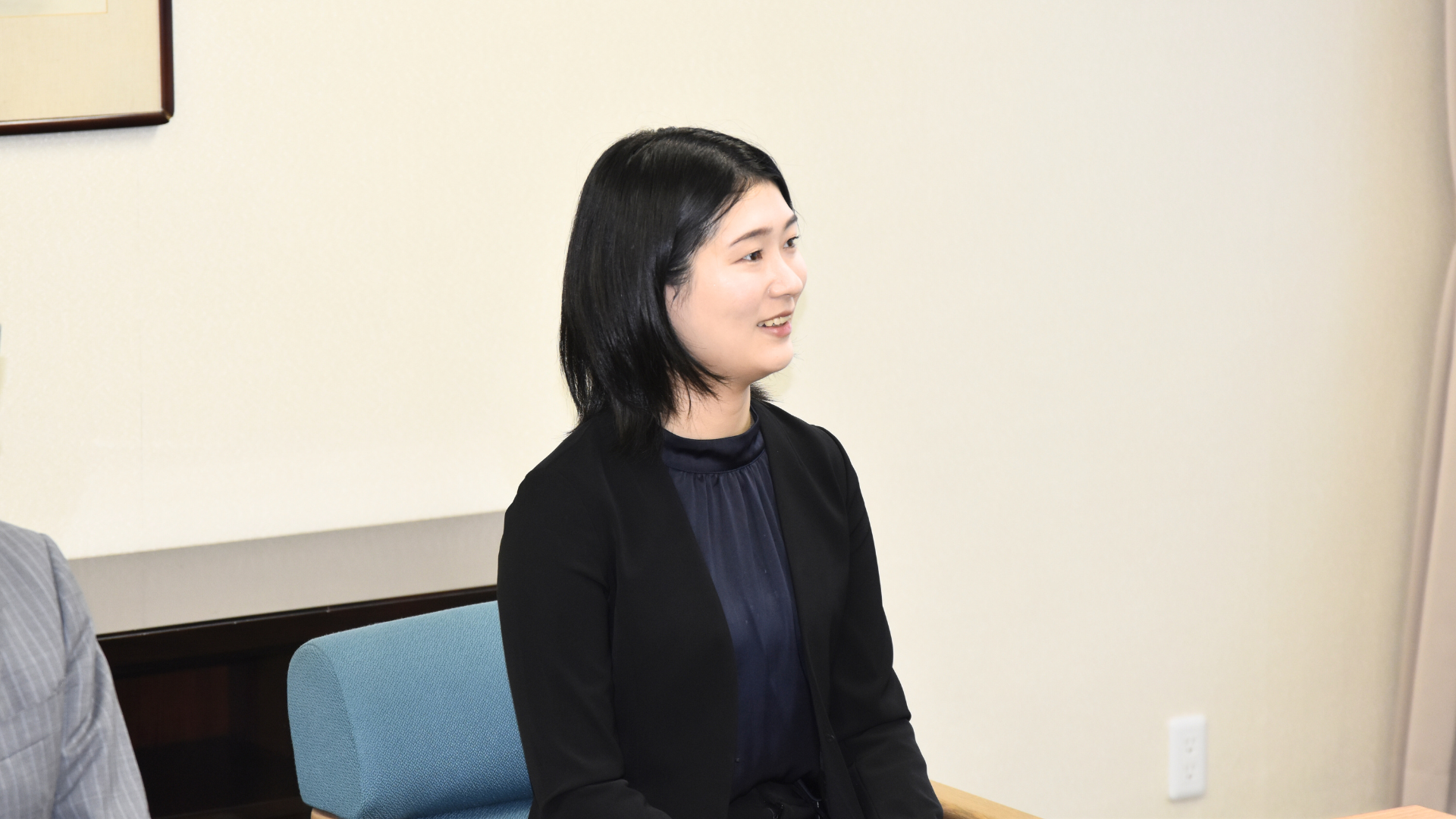
組織の問題を解決するとき心理学の知見が活かされている
竹内:山西さんは大学で心理学を学ばれ、日本新薬に入社後も心理学の学び直しを視野に入れていると伺いました。それも一つの「意思」だと思いますが、どのような課題感から学び直しを考えられたのでしょうか。
山西:入社後にぶつかってきた課題に、心理学の知見が活かされるのではないか、心理学について学びを深めることで、さらに業務に還元できるのではないかと考え始めたからです。「働く人に関することに携わりたい」と人事を希望して入社しましたが、大学時代は社会心理学や組織心理学、産業心理学といった応用心理学には深く触れてこなかったんです。
心理学に興味を持ったきっかけは中学時代で、不登校についての話を見聞きする中で「メンタル不調」というものに素朴な疑問を持ったのが始まりです。自分自身は比較的メンタルが安定しているタイプなので、「なぜそうなるのか」がとても気になり、高校生の頃には心理学を学びたいと思うようになりました。ただ、大学では神経心理学や認知心理学に近い分野のミクロ領域の心理学を専攻していたので、社会心理学等は概論を学んだ程度でした。
気づきを得たのは入社後、人事に配属されてからです。現場ではマクロな心理学の知識が必要な場面が多く、「大学時代に学んだ概論と今の実務がつながっている」と実感しました。それで「もっと社会心理学や産業・組織心理学、集団力学も学んでおけばよかった」と感じるようになり、最近はその分野を中心に学び直しを始めています。
竹内:今回のプログラムは「心理学を学び、それを社会やビジネスに生かす」ことが目的です。山西さんご自身は、心理学を学んだことが仕事でどのように役立っていると感じていますか。
山西:人の感情を理解したり、組織内での問題を発見したりするときに、心理学の視点は生かされています。たとえば人事評価制度は、人間の心理やモチベーション、動機づけとの関係を抜きには考えられません。どうフィードバックすれば納得感が得られるか? どのような制度が人のやる気を引き出すか? こうした点は心理学の知識と直結しています。
また、DX推進やウェルビーイング推進などのプロジェクトでも、アンケートの設計や分析など、心理学で学んだ手法が活きる場面は多いと感じています。
組織上の課題は、物理的な要因だけでなく人の感情やコミュニケーション上の要因も多く、 課題解決に向けてその場で生じている感情やコミュニケーションの状態をひも解いていくことがあります。その過程には心理学の知見が生かされています。
竹内:人の感情など、言語化できない部分から課題発見につなげていくというのは、まさにAIでは難しい領域ですね。

学び続ける文化を根付かせる「NSアカデミー」
竹内:人材育成についてお伺いします。御社のユニークな取り組みとして「NSアカデミー」というものがあると聞きました。これは内製化された自社研修とのことですが、どのような内容なのか教えていただけますか。
高谷:NSアカデミーは、社員一人ひとりが自身でキャリアパスを思い描き、その目標に向かって必要な学びを自由に選択できる仕組みです。社員は自分の進みたい方向に合わせて、多様なカリキュラムから段階的に学びを積み重ねていくことができます。
従来の日本企業は、新卒一括採用や年功序列、終身雇用が前提でした。だから1年目研修、3年目研修、係長研修、課長研修など、入社年次や役職ごとに一律の研修が行われてきた。しかし、当社の研究所には、たとえば大卒で入社する22歳の社員と、博士号取得後に入社する30歳前後の社員が混在しています。
年齢やキャリアの背景が大きく異なる人たちに、画一的な年次別研修は意味がないと考え、従来の層別研修をすべてやめたんです。その上で、社員が自分のキャリアに必要な学びを自ら選択できる「NSアカデミー」を導入しました。
ところが完全に自由にした結果、部長になってから一度も研修を受けたことがない、というケースも出てきました。そういった問題が起こるたびに軌道修正を迫られたり、悩みながらやっています。
竹内:山西さんもそういった研修を受けてこられたんですか?
山西:私が入社した当時は、まだNSアカデミーはありませんでした。最初は従来型の階層別研修を受けていた世代です。ただ、途中から「手挙げ型」の研修がどんどん充実してきて、「自分で選んで学べる」という風潮やメッセージが、次第に強くなっていったと感じています。
高谷:日本新薬では「学び続ける文化」を根付かせたいと考えています。私自身は営業にいたころから「勉強しよう」と呼びかけてきましたが、今と比べると勉強好きな社員は多くなかった。今の若い世代はみなさん勉強熱心ですよね。
学びを奨励するように、「オープンバッジ」という仕組みもあります。これは、研修や学びを積み重ねるとバッジがもらえる、というものです。自分の学びの履歴が可視化されることで、さらに学ぶ意欲が高まっていますよ。

「優秀な人財 」の定義は大きく変わっている
竹内:御社が求めている人材についてお伺いしたいです。どのような人に入社してほしいと考えていらっしゃいますか。
高谷:実は、昨日も取締役会で「優秀人財とは何か」について議論したばかりです。明らかに言えることは、「優秀人財の定義」は大きく変わってきていて、再定義が必要だということです。
今までは計算ができる、作文が上手いといった"頭のいい人"が優秀な人財でしたが、そういった能力は今やAIで代替できてしまう。だからスキルだけを持つ人を採用しても意味がなくなってきています。
それよりも好奇心と情熱を持った人に入ってきていただきたい。自ら課題を見つけて深掘りできる人、そして本質を見抜く力を持った人を採用したいと考えています。ただ、そういった部分はエントリーシートをいくら読んでもわからない。ではどうやって人財を見極めるのか? それをまさに模索しているところです。
竹内:課題発見力を養うのも難しいですし、それを見極めるのもやはり難しいですよね。
高谷:おっしゃる通りです。少なくとも「リアクティブ」、指示があれば的確に動けるというタイプの人は、これからの時代にはなかなか活躍しづらくなると考えています。むしろ、自分で課題を見つけて自発的にアクションを起こせる人。私はそういう人と一緒に働きたいと思っています。
竹内:山西さんご自身も「日本新薬が求める人材」としてご入社されたわけですが、時代や技術の変化も踏まえ、今後どんな方と一緒に働きたい、あるいは入社して欲しいですか。
山西:先ほどの「AIで置き換えられない部分」や「何をやりたいか」という話ともつながりますが、やはり「意志」と「アイデンティティ」を持っている方が大切だと思います。深い考えがあっても、自分が何をやりたいのか?という意志がなければ、行動に移すことはできません。
私自身が就職活動をしていたとき、グループ面接などで他の応募者の方が学生時代の経験を話す中で、「なぜそれをやっていたのか」を聞かれた際に答えに詰まるという場面をよく見かけました。
自分なりのバックグラウンドがあって、確立されたアイデンティティがあれば、それに基づく意志があると思います。その意志を周囲に上手く伝えて巻き込んでいける方と働いていきたいですね。
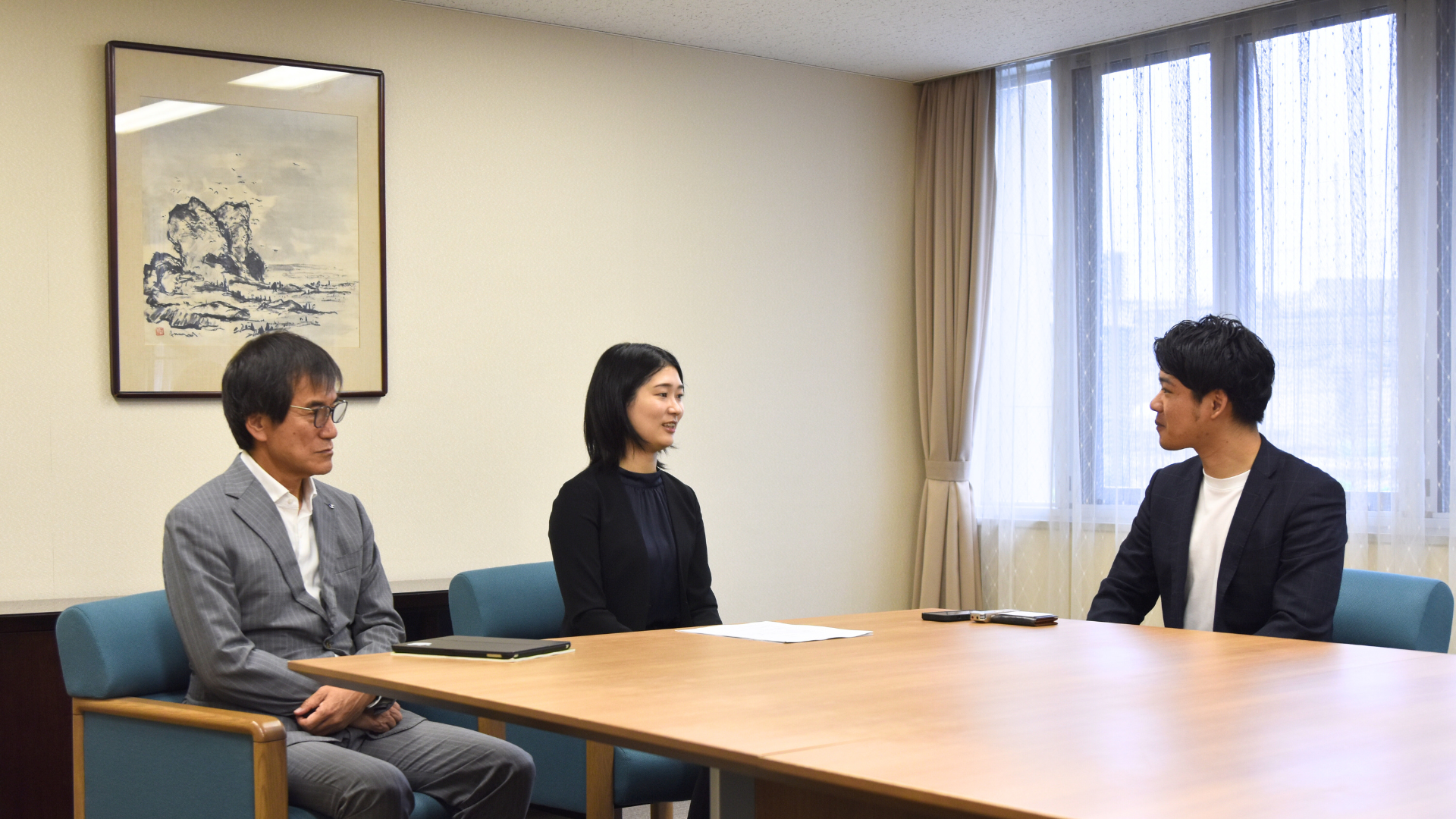
学び続けることで視野を広げ続けてほしい
竹内:最後に一言ずつ、本学で学びを深め、ソーシャルイノベーションを起こし、企業で活躍しようとする方々へメッセージをお願いします。
山西:私自身は心理学の知見がベースにあることで、仕事において気づける範囲や視野が大きく広がったと思っています。
ビジネスは結局「対人」で、人について知ることはあらゆるビジネスに応用できる強みになると考えています。そのための学びを続けていきたいですね。一つの学びが新しい視点をもたらすことで、活躍の幅が広がると思います。
高谷:AIが実装されてきた今だからこそ、主体性や好奇心がますます重要になると思います。日本では社会人が学び直しのために大学に戻ることは少ないですが、海外では当たり前のことです。
当社としては、そうした学び直しを希望する社員を応援しています。また、大学だけでなく、NSアカデミーを通じて「働きながら学びたい」という方も積極的に支援していきたいですね。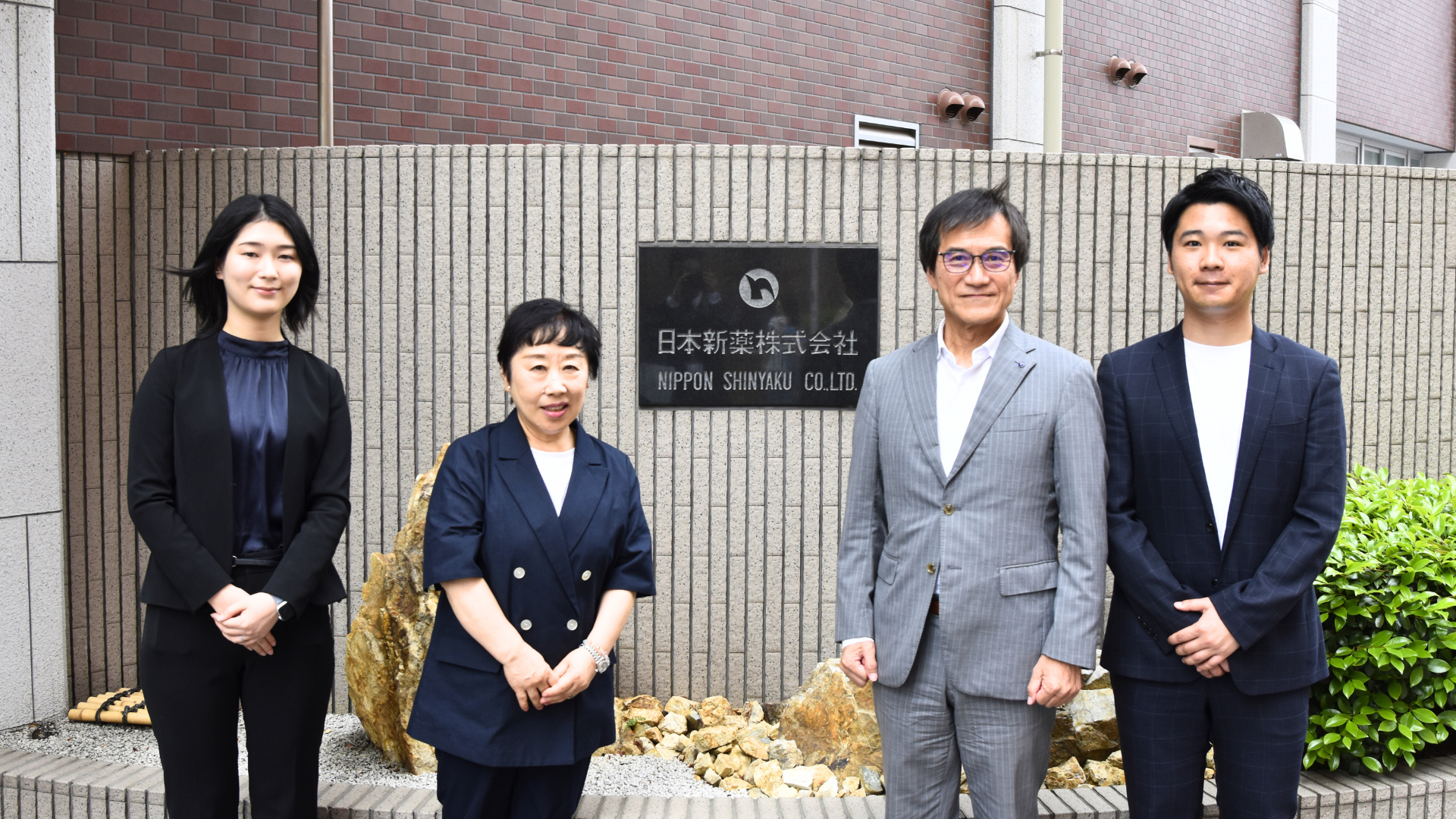
(左から、日本新薬株式会社 DX統括部 山西絢菜様、京都文教大学 産業メンタルヘルス研究所 研究所⻑ 中島恵子、
日本新薬株式会社 取締役 高谷尚志様、京都文教大学 地域企業連携コーディネーター 竹内良地)
おわりに
日本新薬の取り組みを通じて、改めて「人を中心に据えた組織づくり」の重要性を実感しました。技術革新やグローバル展開といったビジネスの成長戦略の裏には、必ず「人の成長」が存在しており、それを支える風土や制度こそが企業の本質を形作っているのだと思います。
特に、「幸せの健康診断」や「NSアカデミー」のようなユニークな取り組みは、臨床心理学の知見と親和性が高く、私たちが目指す「心理学を社会に活かす」実践例として非常に示唆に富んでいました。さらに、AI時代における「人間らしさ」の価値や、意思と好奇心を持った人材の重要性といった話題は、これからの人材育成に対して新たな視点を与えてくれました。
「大学連携型ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」は、臨床心理学・政策学・地域共創学といった多様な領域を融合しながら、社会課題の解決に挑む人材を育てていきます。今回のインタビューで得た学びを土台に、今後も「人」の可能性を信じ、社会に変化をもたらす実践を続けていきたいと考えています。
京都文教大学 地域企業連携コーディネーター
竹内良地
| インタビュアー | 竹内良地 京都文教大学 地域企業連携コーディネーター / Actors合同会社COO 2017年に京都文教大学臨床心理学部を卒業後、新卒でネスレ日本株式会社に入社。セールスや企画業務を担当。2022年には人材育成・組織開発プロジェクトをオーナーとして成功に導き、社内コンテスト「イノベーションアワード」を受賞。その後、スタートアップ企業を経て、Actors合同会社の立ち上げに参画しCOO(最高執行責任者)に就任。心理学の知見を活用した企業におけるビジネス課題の解決やオープンイノベーション創出を行う「ラポトーク」事業を立ち上げ、責任者を務める。加えて、京都文教大学にて文部科学省採択事業「大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」における地域企業連携コーディネーターを務め、大学・企業・地域団体間の連携に尽力。 |
「大学連携型ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」のご紹介
龍谷大学大学院政策学研究科、琉球大学大学院地域共創研究科、そして京都文教大学大学院の3大学院が連携し、次世代のソーシャルイノベーション人材を育成するためのプログラムです。このプログラムでは、社会課題を多面的な視点から分析する力や、異なる領域の知見を統合し新たな価値を創出する力を養います。持続可能な社会の発展に貢献できる人材を育成することを目指し、臨床心理学の知見を活かしながら、社会課題解決に向けたイノベーションのプロセスやデザインを描けるイノベーション人材、そしてそのイノベーション人材を支援する心理専門家を育てていきます。