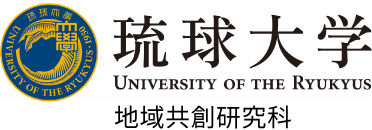Topics 2025 2025年度ニュース・プレスリリース一覧
2025.04.22
【香川県庁 小出明日香氏】産業現場で働く心理専門職のホントのトコロ「人と人がつながることで変えられることがきっとある」
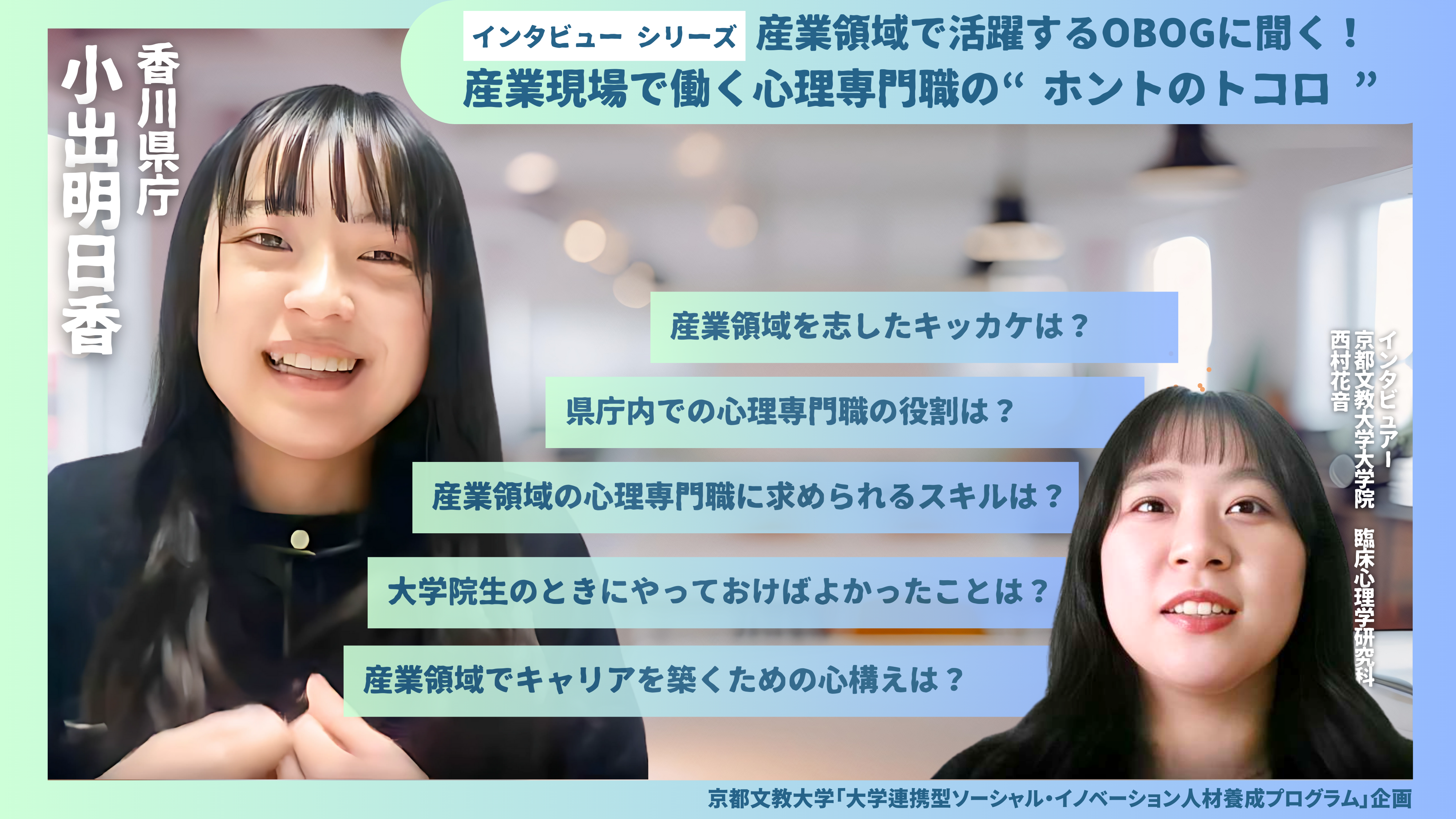
はじめに
心理学を学びながら「この学びをどのように社会で活かせるのか」と考えたことはありませんか? 臨床心理学の知識は、医療や福祉の分野だけでなく、企業や行政、社会課題の解決に向けた場面でも必要とされています。特に、働く人のメンタルヘルスや職場環境の改善、組織の成長を支える「産業領域の心理専門職」は、これからの時代においてますます重要な役割を果たすでしょう。
本記事では、京都文教大学大学院臨床心理学研究科を卒業し、現在、香川県庁で県職員のメンタルヘルス対策を担当する産業心理専門職として活躍する小出さんに、現役大学院生の西村さんがインタビューを行いました。小出さんが産業領域に進むまでの歩み、心理専門職としての役割、そして日々の仕事の中で感じるやりがいや課題について伺いながら、産業領域で働く心理専門職のリアルを探ります。
「心理学を活かして社会に貢献したい」「産業領域に興味があるけれど、どのようなキャリアパスがあるのか知りたい」そんな方にとって、きっと新たな視点や気づきが得られる内容になっています。心理学の学びが、どのようにソーシャルイノベーションにつながるのか、一緒に考えてみましょう。
|
香川県庁 住所:〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号 |
オンラインインタビュー実施日:2025年2月19日(水)

人と人がつながることで変えられることがきっとある
西村:これまでのご経歴や心理専門職を目指したきっかけについてお聞かせいただけますか?
小出:大学では心理学を専攻していたのですが、在学中から産業領域に強い関心を持っていました。そこで、ゼミの先生から産業領域の勉強ができる大学院を紹介していただいて、京都文教大学大学院に進学しました。
修士論文のテーマも「いきいきと働くにはどうしたらよいか」でした。将来、産業領域で働く場合に備えて、ストレスチェックのアルバイトや学外のリワークプログラムの参加など、実践的な経験も積んでいました。
幸運なことに、香川県庁の求人があり、今は県庁内の産業心理専門職として就職するに至っています。
西村:なぜ産業領域を選ばれたのでしょうか。
小出:きっかけは高校時代の経験です。私は陸上部だったのですが、練習中に疲労骨折をして走れなくなってしまったんです。周りは強い選手ばかり。自分だけが取り残されていくような孤独感を味わいながら、できる練習をしていました。
そんなとき、他の部活にも同じように怪我をしている友人がいることを知りました。トレーニングジムには怪我をしている人たちが集まっていたので、自分の話を聞いてもらったり、友人の話を聞いてあげたり。同じ境遇の人がいるだけで「自分だけじゃないんだ」と安心できました。
打ち明け話ができたのは信頼関係があったからこそだし、人との関係性ってこんなに大切なんだと実感しました。この出来事があって、人の話を聞いてサポートすることに興味を持ちはじめました。
西村:私も同じです! 心理に興味を持ったきっかけは、高校の部活でした。バトミントン部だったんですけど、試合で負けて落ちているときに先生や友人に励ましてもらったことや、エースだった友人が足を怪我したときに自分を頼ってくれて、トレーニングルームで話を聞いてあげたりもしました。そういった経験から、メンタルの重要性を知りました。
小出:話を聞いてもらうだけで「もう少し頑張れそう」と思えたり、変わらない現実を捉え直すことで、違う見方ができるようになったり...人と人がつながることで変えられることってきっとありますよね。
誰もがいきいきと仕事時間を過ごしてほしい
西村:実際に、産業領域を志すようになったのはいつごろからですか。
小出:それは大学時代ですね。ピザ屋でアルバイトをしていたんですけど、そこは店長が1年で3回も変わるような店でした。店長が変わると、店の方針や雰囲気がよくも悪くも変わってしまう。そのたびに働きにくさを感じましたし、どんな職場環境なら働きやすいのかを考えるようになりました。
もう一つは、大学時代に所属していたサークルでの経験です。アイスブレイクとして、グループ発表をする機会がありました。そこで、一つのグループが盛り上がると他のチームにも雰囲気が伝染したり、自然とリーダーが決まっていったりする過程を見て、集団や組織というものに興味を持つようになりました。院生時代には働く人のメンタルヘルスについて研究しました。人生の3分の1を費やす労働時間を、元気にいきいきと過ごしてほしい。そのためにはメンタルヘルス不調の予防が必要だと考えたことが、産業領域を目指すきっかけとなりました。
県庁内での産業心理専門職の役割
西村:現在の仕事での役割や日々の業務内容について教えていただけますか?
小出:一般財団法人香川県職員互助会に所属する団体職員です。県の委託を受けて、県庁内で産業心理専門職として働いています。県職員の方たちを対象に、メンタルヘルス対策を実施するのが仕事です。職場には、産業医と保健師、看護師、事務職の方がいて、心理専門職は私のほかに3人の先輩がいます。
仕事の内容は、主にメンタルヘルス不調の予防や、職場復帰に向けた支援です。予防には3つの段階があります。1次予防としてストレスチェックの実施があります。実施によって、職員のセルフケアへの意識を高める取り組みをしています。あとは、職階ごとにセルフケアの研修を行います。
2次予防では、ストレスチェックで高ストレス判定になった人に向けて、産業医の面接を実施します。面接に抵抗がある方には、心理専門職への相談をご案内します。セルフケアを確保していただくための相談を行っています。また、被災地に派遣した職員さんに対して、健康管理のための面談を行っています。
3次予防として、メンタルヘルス不調で長期療養となった方の職場復帰支援も行っています。
現場におけるアセスメントの難しさ
西村:産業領域で心理専門職として3年ぐらい働かれているとのことですが、仕事を通じて印象に残っているエピソードや、直面した課題について教えてください。
小出:一番印象に残っているのはアセスメントですね。1回のアセスメントで適切に評価を行うことが難しく、課題を感じていました。
院生時代は、面談は3回ほどあって、スーパービジョンを受けながら見立てを固めていくプロセスがありました。しかし、産業領域では、相談に来られた方の話をその場で聞き、すぐに対応策を提案することが求められます。そのため、素早いアセスメント力が必要になるのですが、上手くできていないと感じる場面が多々ありました。
面談では、まず相手の話を聞くことが重要です。それなのに、先走って解決方法を考えてしまい、目の前にいる相手の話を聞くことがおろそかになってしまったこともありました。
相談者が求めているのは解決策ではなく、話を聞いてもらうことだったかもしれません。それなのに、つい「こうした方がいいのでは?」とアドバイスをしてしまった。その結果、相談者の反応に違和感を感じたり、次回の面談につながらなかったりしたこともありました。
西村:私もケースを持ち始めてから、クライアントのニーズについて悩むようになりました。自分の見立てが本当にクライアントの求めているものと合っているのか、面接のたびに迷うので、よく先生や先輩に相談しています。
小出:常に考えさせられますよね。私自身も、先輩に相談しながら、ケースごとのアプローチを学んでいます。さまざまな事例を聞くことで、アセスメント力を磨いていく必要があると日々実感していますね。
産業領域ならではの集団へのアプローチ
西村:産業領域の心理専門職には、アセスメント力の他にどんな能力が必要だと思われますか?
小出:さまざまな立場の人の話を中立的な立場で聞く、ということですね。大学院では、基本的にクライアントの話だけを聞いていればいいのですが、産業領域ではそれだけでは不十分です。なぜなら、上司の意見を聞いたり、職場の状況も把握したりする必要があるからです。
クライアントが思っていることと上司の方が言っていることが違う、ということもよくあります。心理専門職としてはクライアントの立場に寄りがちですが、その人が職場復帰するには上司の支援も必要です。だから、上司もクライアントだと思って話を聞きます。
例えば、クライアントが「こうしてほしい」と訴えていても、それをそのまま上司に伝えるのがいいとは限りません。上司からクライアントに対する考えを聞くと、クライアント本人の問題が浮き上がってくることもあります。
問題を解決するには、クライアント自身が職場への適応力を高めていけるように支援をしていく必要があります。そのためには、双方が納得できる落としどころを見つけないといけないんです。
西村:大学院でのケースや産業以外の領域だと、第三者に焦点を当てることはあまりないと思います。それは産業領域ならではですね。
小出:産業領域では、個人だけでなく集団へのアプローチも大切です。相手の話を聞くだけではなく、自分の言葉で伝える力も求められます。
また、クライアントの反応を見て、話し方や話の内容を変える必要もあります。クライアントがこちらの話をイメージできているかを観察しながら、必要に応じて具体的なエピソードを加えるなど、臨機応変に対応します。
産業領域を目指すためにやったこと
西村:心理専門職としての就職先はどのように探されたのでしょうか?
小出:求人サイトなどの情報をこまめにチェックしていました。ただ、産業領域の求人には「社会人経験3年以上」などの条件があることも多いんです。ふつうに探しているだけでは難しいと思って、大学院経由の求人や、卒業生向けの限定情報を活用していました。
あとは、「メンタルヘルスの仕事をしたい」と周囲によく話していたことも大きかったですね。相談をしていたことで、友人が香川県庁の求人を見つけて教えてくれたんです。それがきっかけとなって、今の仕事につながりました。
西村:大学院卒業後、医療機関を経由せずに産業領域に直接進まれたということですけど、周りの方は医療機関が多かったですか。
小出:病院で働く友人も多かったし、あとは療育施設とか子どもの発達支援の領域に進む人の割合が高かったように思います。
西村:今の仕事を探す際にもっとも困難だったのは、「働き口が少ない」という点でしょうか。
小出:そうですね。3年ぐらいは社会人として働いて、そこからやっと進める領域なのかなって。だから、最初は医療領域で経験を積んで、それから産業領域に進もうかとも考えていました。
西村:他にも産業領域に進むために取り組まれていたことはありますか?
小出:産業領域で働く方々とのつながりを積極的に探していましたね。直接進路に結びついたわけではありませんが、「産業メンタルヘルス研究所」で行われていた産業心理臨床家養成プログラムの運営にも関わっていました。
そこでは、全国で産業領域に携わる人がこんなにいるんだと知ることができました。現場で活躍されている方々の経験談を聞きながら、自分がやりたいことを整理できたし、それを言語化できるようになったと思っています。
また、リワークプログラムで職場復帰を目指す方々に関わったこともあります。対人緊張の高い人が少しずつ心を開いて話してくれるようになるのを見て、「自分が安心して話せる場所」を作ることの重要性を実感しました。
自分の言葉として伝えなければ届かない
西村:逆に、大学院生のときに「もっとこうしておけばよかった」と思うことはありますか?
小出:一つは、研修での伝え方ですね。初めてセルフケアの研修をやったとき、受講者に伝わっていないと気付いたんです。
例えば、ストレス対処法は複数持ったほうがいいとか、気分転換と問題解決をバランスよく使うのが大切だとか、セルフケアの一般的な知識がありますよね。それはみんな知っていると思うんです。
だけど、普段から自分自身がセルフケアを意識してやっていないと、自分の実感として語れない。伝わらなかったのは、私が表面的な知識だけを話していたからだと思うんです。大学院生のうちに、研修で扱うテーマを自分で試したり、学びを深めたりする機会をもっと作ればよかったと感じました。
もう一つは、社会の動きにもっと敏感になっておけばよかったということです。例えば、働き方の変化や、コロナ禍が人々に与える影響など、時代の変化を追うことで、環境や組織を見る視点が鍛えられる。それが結果的に個人を理解する助けになるんですよね。
今になって思うのは、ニュースや新聞を「社会の変化が人にどう影響を与えるのか」という視点で見ておくとよかったなと。私は働き始めてからその重要性に気づいたので、もっと早くから意識しておけばよかったと思いますね。
西村:もし今大学院2年生に戻ったとして、もう一度就職活動をすることになったら、産業領域に進みたいと思われますか? それとも、医療など他の分野に進んでみたいですか?
小出:今の職場は大変なことも多いけど、一緒にケースを検討してくれる方たちがいる環境であれば、また産業領域で働きたいと思います。
ただ、アセスメントのスキルを高めるには、医療領域での経験があるとよりよいかもしれませんね。重度の症状を持つ方々の診察や治療を間近で見ておけば、産業領域で健康度の高い方々を見たときに、「医療と連携すべきか」「見守りでよいか」の判断がしやすいと思います。
クライアントの強みが解決の手立てになる
西村:大学院で学んだ臨床心理学の知識は、現在のお仕事にどのように活かされていますか?
小出:クライアントを理解するためには、ポジティブとネガティブの両面に目を向ける必要があるということです。
大学院でアセスメントを学んでいるときに心理検査を実施したんですけど、そこでは相手の困りごとを中心に話を聞くので、「なぜそうなってしまうのだろう」と、課題に目を向けがちでした。
ただ実際には、その人の得意なことが解決の手立てに繋がることが多くあります。強みと課題、2つの側面からその人の全体像を捉えて理解する姿勢を持たなければいけないことを、そのときに学びました。
産業領域の前提として、働いている方が相談に来られるので、健康度は比較的高い人が多いんです。もちろん悩みを抱えているから相談に来られるのですが、これまでうまく対処してきた経験を持っている方も多い。そういった成功体験には必ず意識を向けます。
ストレスチェックによる集団分析をするときも、単にネガティブな部分をなくすことで不調者を減らす、というようなことはしません。健康度や生産性を向上させるためには、職場の強みや資源を活用していくことに主眼が置かれます。
西村:クライアントの強みを、よりプラスにしていくためのアプローチというのは簡単じゃないですよね。一方で、マイナスなことを傷つけずに伝えることもすごく難しくて、所見を書いたり心理検査を実施したりするとき、どう伝えるべきか悩むことが多いです。
小出:伝え方次第で、せっかくのアセスメントが役立つどころか、かえって傷つけてしまうこともありますよね。信頼関係ができていない状態で、クライアントにとって負荷の大きい話を伝えるのは、本当に難しいです。
私も伝え方には常に気を付けていて、まずは関係を築いてから、クライアントがその話に向き合えるタイミングを見計らって伝えるようにしています。
臨床心理学でクライアントの過去と未来を支える
西村:産業領域において、臨床心理学がどのように応用されていると感じますか? 具体的なエピソードや経験があれば教えてください。
小出:例えば、職場復帰支援の場面では、単に「職場復帰したら終わり」ではなく、その後も継続的に働き続けられているかを確認していきます。職場復帰後しばらく経ってから、当時の状況を振り返ってもらうと、「あのときは本当にしんどかったけど、今思うとこういうことだったんだな」と、見方が変わっていることがよくあります。
環境そのものが変わらなくても、本人の捉え方や意味づけが変わることで、状況が違って見えるようになる。その変化を一緒にたどりながら、その人の過去と未来の生き方を聞けるのは、産業領域ならではの面白さだと思います。
今は辛くても、その辛さがずっと続くわけではなく、元気になって振り返ってみれば、意味づけが変わっていることもある。その変化を支える場面で、臨床心理学の視点は生かされていると思います。
その希望が本当にクライアントのためになるのか?を考える
西村:心理職はクライアントの立場に立って話を聞くことが求められる一方で、組織の立場も考慮する必要があると思います。そのバランスについて、小出さんはどのように判断し、対応されていますか?
小出:現実的な視点を持つことが大切です。職場復帰にあたってクライアントから「異動させてほしい」などの希望が出ることがありますが、すべてが実現できるわけではありません。
働くためには現実を受け入れてもらうことも必要です。職場にはできることとできないことがあること、本人が頑張ってもらわないといけないこともあるということを、中立的な立場から伝えます。
クライアントに対して、適応力を高めてもらうための働きかけも必要です。職場のルールに沿った形で復帰できるように、公務員であれば「週5日勤務」「就業時間は8時半から5時15分まで」といった基本的な働き方を目標として伝えていきます。
西村:これまでのご経験の中で、クライアントの希望と組織など周囲の意向にギャップがあるケースはありましたか?
小出:ありますね。クライアントの希望が組織のルールや文化、規範などに合わないということはあります。
西村:そういった場合、どのような方向性で面談を進めていくのでしょうか?
小出:その希望が本当にクライアントのためになるのかを一緒に考えます。例えば、「それを職場に伝えたらどうなると思う?」とか、「そうなったとき、周囲との関係はどうなると思う?」と、自分の考えを客観的に見てもらうようにします。
直接的には伝えませんが、「自分も勉強しないといけないな」「もっとスキルアップしよう」といった気づきを促せるようにします。環境を変えてほしいと訴えるだけではなく、自分自身がどのように適応し、成長できるかを考えてもらうことが大切です。
問題が解決されないまま職場復帰すると、同じことを繰り返して、また長期療養となってしてしまうこともあります。そうならないようにサポートすることが私たちの役目です。
つながりができたことで自分の立ち位置が明確になった
西村:臨床心理学や産業領域について、今でも学びを続けられていることや取り組まれている活動はありますか?
小出:学会に参加したり、香川県臨床心理士会の産業領域の委員会に関わったりしています。そこでは、働く人のメンタルヘルスについて、同じ業界の方々と意見交換をしています。
また、新人研修会にも参加しています。そこではキャリア5年目までの人たちが集まって話し合い、今後のキャリアを考えるということをしています。
先ほど話した「産業心理臨床家養成プログラム」にも参加しています。ここは業界のさまざまな人とつながりを持てる貴重な場です。また、産業領域で必要な知識を体系的に学べたことで、自分の立ち位置も明確になった気がします。まだ経験したことのない業務に関する講義もあるので、今後はそういった部分をしっかり学んでいきたいですね。
積極的に人と関わってほしい
西村:現在の大学院生に向けて、産業領域で心理専門職としてキャリアを築くための心構えやアドバイスをお願いします!
小出:ビジョンを明確にしましょう、ということを伝えたいです。私は産業領域で予防に関わる仕事をしたいと思い、それに向けてできることに取り組んできました。まずは、自分が何をしたいのかをはっきりさせること。そして、そこに向かって自分が今できることをやっていくことが大事だと思います。
あとは、やりたいことを実現したいとき、人とのご縁を大切にしてほしいと思います。私がプログラムや学会、研修などで出会った人たちの中には、経験豊富な先輩や同じ志を持つ大学院生、臨床心理専門職になって数年の方々がいました。
そうした方とつながり、近況を共有し、自分がやりたいことを話していくうちに、「こういう情報があるよ」とか「こんな仕事があるよ」とか、新しいご縁が生まれることもあります。積極的に人と関わるということをぜひやってみてください。
誰にでも誰かに頼れる環境が必要
西村:私は新卒社員のメンタルヘルスに関心があって、修士論文でそのテーマを扱おうと考えています。新卒1年目の方々を対象に、メンタルヘルスの推移を調査していく予定なのですが、新卒研修のご経験がある小出さんにアドバイスをいただきたいです!
小出:新卒社員にとって、大きな課題のひとつは「リアリティショック」への適応だと思います。学生時代と社会人生活では環境が大きく変わるため、思っていた仕事とのギャップに戸惑うことが多いです。
新卒社員が感じるストレスについては、マイナビなどのサイトで調査結果が公開されています。私の研修でも、そういった資料を活用しながら、何がストレスになりやすいのかをあらかじめ伝えます。
会社に入ってから、何が待ち受けているのかを知ることができれば、心構えもできますし、「自分だけじゃなくて、みんなも同じように感じているんだ」と思ってもらえるようになる。その結果、新卒社員が環境の変化に適応しやすくなると思っています。
まずは、ストレスのサインに気づくこと。適切に対処ができれば、メンタルヘルス不調は防げます。また、職場での悩みは職場で解決していくのが一番です。職場でのソーシャルサポートを考えることも重要だと思いますよ。
西村:ありがとうございます! 先行研究を読んでも医療関係の研究ばかりだったので、参考になります。
小出:どうして新卒のメンタルヘルスに興味を持ったんですか?
西村:もともと、働く人のメンタルヘルスに興味があったんです。アルバイトの店長がメンタル不調で辞めてしまったとき、「人の上に立つ人のメンタル支援って誰がしているんだろう?」「上の人って下には頼りにくいよな」という疑問が浮かんだのがきっかけです。
小出:たしかに、上司はラインケアで部下のメンタルヘルスを守る立場ですよね。でも、上司は上司で、悩みを抱えていることもあるから、誰かに頼れる環境は必要です。ただ、たしかに部下に相談するのは立場上難しいですよね。そういう方たちのためにも、私たちのような心理専門職の存在が必要です。
実際、部下の方が療養に入ってしまったことで悩んでいる管理職の方の話を聞くこともあります。産業領域であれば、産業保健スタッフとして管理職の支援にも関わりやすいと思いますよ。
西村:ありがとうございます! 私も産業領域で働きたいと、より思うようになりました。
おわりに
小出さんの朗らかな話し方に加えて、ご自身をしっかり確立していらっしゃると感じ、そこに凄く感銘を受け、私も小出さんのような人になりたいと思いました。 私が質問するだけでなく、小出さんが私に興味を持って下さり質問してくださったので、とてもリラックスしてお話出来たのではないかと感じています。
小出さんとお話している中で、私の過去や、心理学に興味を持った経緯など様々な部分に共通点を感じ、私の目指している道を歩まれている先輩として、聞きたいことがどんどん出てきてしまって絞るのが大変でした。
産業領域に進むために、どのように行動すれば良いのか、今の自分に何が足りないのか、何をするべきなのか考えることが出来、勇気づけられた時間でした。自分自身ビジョンの明確化も、周りにそれを公言することもあまり得意では無いので、残りの1年間でそれらが出来るようになりたいと思い、周りの人との関わりをより大切にしようと思えました。
院生にとって身近な先輩のお話を聞く機会を与えていただけたこと、そしてお忙しい中協力してくださった小出さんに感謝します。 貴重なお話本当にありがとうございました。
京都文教大学大学院 臨床心理学研究科
西村花音
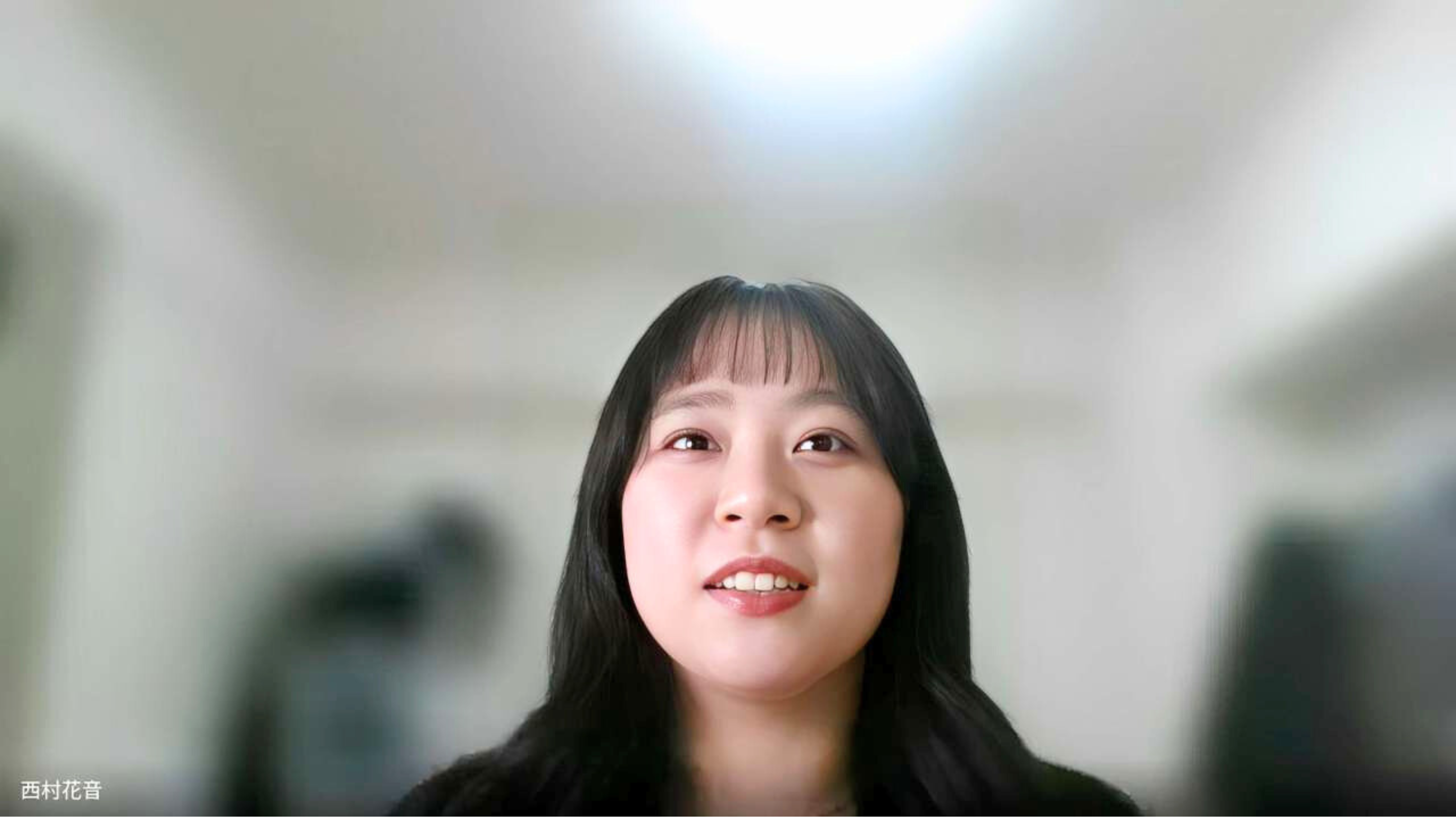
「大学連携型ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」のご紹介
龍谷大学大学院政策学研究科、琉球大学大学院地域共創研究科、そして京都文教大学大学院の3大学院が連携し、次世代のソーシャルイノベーション人材を育成するためのプログラムです。このプログラムでは、社会課題を多面的な視点から分析する力や、異なる領域の知見を統合し新たな価値を創出する力を養います。持続可能な社会の発展に貢献できる人材を育成することを目指し、臨床心理学の知見を活かしながら、社会課題解決に向けたイノベーションのプロセスやデザインを描けるイノベーション人材、そしてそのイノベーション人材を支援する心理専門家を育てていきます。
公式ホームページ:https://www.kbu.ac.jp/kbu/siprg/index.html