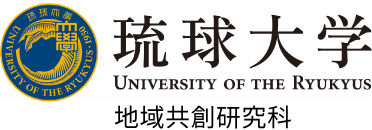Topics 2025 2025年度ニュース・プレスリリース一覧
2025.04.09
【京セラ株式会社 能原隆氏】京セラ創業者・稲盛和夫から受け継ぐリーダーの心得「リーダーは"心理学者"でなければいけない」

はじめに
京セラ株式会社は、創業以来、技術革新と多角経営を推進し、世界的な企業へと成長してきました。その根底には、創業者・稲盛和夫氏が掲げた「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること」という経営理念があります。この理念は、単なる経営哲学にとどまらず、事業戦略や人材育成の根幹を成し、現代においても強い影響を与え続けています。
今回のインタビューでは、京セラ株式会社 執行役員 経営推進本部長の能原様に、新規事業開発のあり方、リーダーシップの本質、そしてソーシャルイノベーションに求められる視点について伺いました。特に印象的だったのは「リーダーは心理学者でなければならない」という稲盛氏の言葉です。企業経営において、技術や戦略はもちろん重要ですが、最も大切なのは「人」であり、リーダーはメンバーの心の状態を把握し、最適な環境を整える存在でなければならないという考え方です。
本記事では、能原様のキャリアを振り返りながら、京セラがどのようにして新たな価値を創出し続けているのか、そしてソーシャルイノベーションを実現するために必要な人材とは何かを掘り下げていきます。臨床心理学を学ぶ私たちにとっても企業のリーダーがどのように「人」を見てマネジメントを行っているのか、その視点は非常に示唆に富んだものでした。
| 京セラ株式会社 設立 :1959年4月 事業内容:ファインセラミック部品、電子部品、半導体部品、情報機器、通信機器、 太陽電池、セラミック、宝飾、医療用製品などの製造・販売 住所 :〒612-8501 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 H P :https://www.kyocera.co.jp/ |
インタビュー実施日:2025年2月5日(水)

技術ではなく市場ありきで自分たちを定義していく
竹内:まずはご経歴について、現在のお立場に至るまでの道のりを教えていただけますか?
能原:今は社長直轄の経営推進本部で、新規事業の担当をしております。以前は、携帯電話やスマートフォンを扱う通信機器事業の部門に30数年おりまして、そこで営業やマーケティングをさせていただいておりました。
現在の新規事業開発は、経営推進本部の主軸となるミッションの一つです。その中で、私が通信機器事業の出身ということもあり、IoTのビジネス開発を5年間担当してきました。そして、昨年の4月から現職に就いています。
竹内:経営推進本部というのは、どのような役割を担っているのでしょうか?
能原:役割は大きく2つあります。1つがコーポレートスタッフとして、経営層を補佐する役割。もう1つは、サステナビリティに関する取り組みと、新規事業開発への注力です。
当社は多角経営企業です。部品事業や機器事業、さらにはサービス事業も展開していますが、一つの部門だけで新しい提供価値を創出するのは難しいことが多いです。そこで、社長直轄の経営推進本部が新規事業を担当することになりました。
竹内:新規事業は複数の部門をまたぐ、いわゆる横ぐしで進められるのでしょうか?
能原:新規事業の進め方は、実際にはさまざまなアプローチがあります。横断的に一気通貫で進める場合もありますし、全く新しい取り組み方で進める場合もあります。一定の判断基準はありますが、定型的なプロセスというのはあまりないですね。
竹内:能原さんのネット記事も拝見しましたが、ハイドロ*関連の展開について触れられていましたね。そのようなご経験が、現在の役割に繋がっているのでしょうか?(*ハイドロ:北米でヒットした京セラのスマートフォンシリーズ)
能原:マーケティング時代に商品企画やプロモーション戦略、製品デザインなどを担当していたので、「市場との関わり合いの中で自分たちをどう定義していくか」ということは常に考え、経験してきました。
そのおかげで、技術ありきではなく、市場ありきで物事を考えていくことが身に付きました。だからこそ新規事業を任せてもらえているのだと思います。 
一つの分野に留まっていては退歩が待っているだけ
竹内:能原さんが京セラに入社された経緯についてもお伺いさせてください。
能原:大学卒業後、新卒で京セラに入社しました。当時、私は新しいことに挑戦したいという思いがありました。そんな中、京セラがDDI(現KDDI)という会社で新しく通信事業に参入する計画を立てていることを知りました。
一つの分野に留まっていては、退歩が待っているだけ。しかし京セラは、リスクを恐れず新しいことにチャレンジしていく姿勢がありました。そこが、私自身がやりたいことと一致していたんです。
竹内:御社はセラミック事業からスタートして、今ではさまざまな領域でソリューションを提供されています。新しいことに挑戦していくという風土には、どのような考え方が根本にあるのでしょうか。
能原:根本にあるのは、創業者の稲盛和夫が掲げた経営理念です。「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類社会の進歩発展に貢献すること」というものです。
「全従業員の物心両面の幸福」とは、会社が絶えず利益を出して従業員に給料を支払い続ける物質的な幸福を求めていくとともに、精神的な幸福、つまり、仕事の場での自己実現を通じて、生きがいや働きがいを追求するということ。この理念を実現するための手段として、多角化戦略が選ばれました。
一つの製品だけに依存していては、その需要が落ち込んだときに従業員の生活を守れなくなる。だから、世の中の動きに関わらず、従業員に給料を渡し続けられる仕組みづくりが必要です。
実際、創業当初から稲盛は先を見据えた行動をしていました。最初の製品であるU字ケルシマを開発したときから、その需要がなくなった場合を想定して、次の用途開発に向けたアクションを起こしていました。
多角化戦略は、ステークホルダーへの還元はもちろんですが、何より従業員とその家族の生活を守ることを重視したアプローチだと思います。
竹内:新規事業の選定はどのように行われているのでしょうか?
能原:基本的には、我々の技術基盤を活用できるかどうか、ですね。例えば、セラミックの焼成技術のような、当社が持っている技術を基に、応用分野を広げていけそうな事業であれば着手します。ここで言う技術基盤とはエンジニアリングだけでなく、ものづくりのノウハウや生産技術、製造技術なども含まれます。
完全に異なる分野への「飛び石」的な多角化は、実際には1、2回程度しか行っていません。そういったケースは、顧客が困っている課題に対して、我々の技術で解決策を提供できないかという発想から生まれることが多いです。
竹内:企業や個人の悩みに対してソリューションを提供するというのは、まさにソーシャルイノベーションの精神ですね。
能原:リスクを取ってチャレンジすることは社内でも奨励されています。それが会社人としてのやりがい、働きがいにもつながっていると考えています。 
現代にも通じる稲盛和夫氏のフィロソフィ
竹内:京セラを語る上で稲盛和夫氏は絶対に外せないポイントだと思います。稲盛氏のフィロソフィと呼ばれるものが、DNAとして今でも受け継がれていると感じます。
能原:京セラには、先ほども申し上げた「人類、社会の進歩発展に貢献する」という理念が60年以上前から掲げられています。これは今で言う社会課題の解決そのものです。
自分たちだけが儲かるようなビジネスを選ぶのではなく、事業を通じて人類社会の進歩発展に貢献していく。以前は社会貢献活動と言えばメセナなどがありましたが、そうではなく、世の中のためになる事業を生み出すことで、「従業員の物心両面の幸福」を追求していく。これが京セラという会社の根本にあるものです。

リーダーシップを育成するアメーバ経営
竹内:社会課題の解決に向けた事業展開について、大企業はスピード感の面で難しい部分もあると思います。京セラが課題に対応できているのは、アメーバ経営が根付いているからだと想像しています。
能原:アメーバ経営は当社の組織運営に大きな影響を与えています。アメーバ経営とは合目的集団みたいなもので、特定の目的のために組織化され、その目的を達成するために活動します。目的が達成されれば、そのアメーバは解散し、新たな目的のために別のメンバーで再編成されます。この手法を取り入れていることによって、新しいものにトライすることに対してハードルが低くなっている側面はあると思います。
竹内:基本的にはプロジェクト単位で動かれるのですか?
能原:そうですね。特に、研究開発や、私どもみたいな事業開発はプロジェクト単位で動いています。アメーバ経営の場合、プロジェクトの役職と人事的な資格は厳密に紐づかないことが多いですね。
竹内:アメーバ経営のリーダーは、経営報告に近いような報告をされるとお聞きしました。そのようなタスクを通じて、リーダーシップが育つということでしょうか。
能原:リーダーシップの本質は責任と権限だと思います。リーダーに任命されれば、そのプロジェクトの中で相応の権限が与えられます。同時に、プロジェクトを遂行する責任も負うことになります。責任と権限が一体となることで、リーダーとしての経験が上がっていく。プロジェクトの大小に関わらず、リーダーにはものすごいプレッシャーがかかりますが、そこを乗り越えることでリーダーシップは育成されていきます。
竹内:リーダーはどのようにして選ばれるのでしょうか?
能原:それはさまざまですね。「このプロジェクトは私の人生をかけてでもやりたい」と言って手を挙げる人もいますし、「プロジェクトの規模を考えれば彼が適切じゃないか」みたいな形で任命する場合もあります。
竹内:多くの製造業では物づくりに注力するあまり、人材育成がうまくいかないケースも見られます。しかし、御社は代表的な製品を持ちながらも、人材育成にも力を入れていると感じます。なぜこのようなバランスを取ることができているのでしょうか?
能原:小さな組織でリーダーシップの経験を積めるからでしょうね。アメーバ経営は、若いうちから小規模組織のリーダーとして、人、物、金をすべてハンドリングしてプロジェクトを運営します。この経験が、人材育成の土台になっています。
特別なエリート教育ではなく、現場で自然にリーダーシップを学びながら徐々に責任が重くなっていく。制度としてそう決まっているわけではないのですが、企業文化として根付いているので、将来のリーダーを創出しやすい環境にはあるんじゃないかと思います。

リーダーは心理学者でなければならない
竹内:御社には「心をベースに経営する」という思想がありますね。能原さんは、稲盛和夫氏のこの考え方をどのように解釈されていますか?
能原:人間が一番生きがいや働きがいを感じるのは、自分がやりたいことを苦労しながらでも達成できるか、と私は考えています。欧米企業では、ジョブディスクリプションを明確にして、「あなたの仕事はここからここまでの範囲です。こういう仕事をやってください。権限はここまでです」というやり方をしますよね。これはトップダウン型で、従業員は仕事を割り振られるという感覚になります。
しかし、稲盛のように「心をベースに経営」をすればそうはなりません。やっていることに熱中することで、「言われたからやっている」以上の力を発揮していく。そうすればやりがいや働きがいを感じるようになる。理想的なのは、「自分がやりたいと思っていることをやれている状態」です。周りから見ると苦労しているように見えても、本人は苦にしていない。これこそが最高のパフォーマンスを発揮できる状態です。
極論を言えば、リーダーやマネージャーというのは、従業員の心を最適な状態に保つためにいるんです。実務ができるからリーダーになっているわけじゃない。常にベストパフォーマンスが出せる状態でいられるように、メンバーの心のありようを維持し続けられるのがリーダーであり、マネージャーの役割です。
稲盛はよく「リーダーは心理学者でなければならない」という言い方をしていました。個々の顔を見ながら、この人は今どういう状態なのか、どういう懸念があるのかを把握し、一人ひとりに対して手を打っていく。これをやるのがリーダーの仕事だということです。
竹内:本学ではまさに臨床心理学を学んでいますが、人のモチベーションを理解し、高めることは非常に難しいと感じています。御社の「個々のメンバーの心を見る」マネジメントは、どのように養われているのでしょうか。
能原:稲盛は「まず事業の目的、意義を明確にしなさい」と言っています。プロジェクトが社会にどのように貢献するのか、世の中に変化をもたらすことでどれほど多くの人が救われるのかを部下に伝えます。
駆け出しのリーダーはとかく「この仕事を、このやり方で、いつまでに終わらせてください」というふうに、淡々と業務内容を伝えがちです。あたりまえですけど、それではパフォーマンスは出ません。出ないから、リーダーは悩むんです。
悩んで考えるうちに、プロジェクトの大義名分を明確にしたり、個々のメンバーの悩みをケアしたりする必要性に気付きます。小規模なプロジェクトでも、リーダーとしての経験を積むことで、人の心を理解し、モチベーションを高める手法の習得につながっていきます。
竹内:能原さんがリーダーとしてメンバーと向き合うとき、「心理学者にならなければいけない」という稲盛氏の言葉をどのように解釈し、実践されていますか?
能原:まず、熱量を伝えることです。会議の冒頭で、会社の状況や最新の技術トレンドについて話します。今でいえばAIの話題などですよね。こうあるべきとか、こうすればもっと売れる、といった自分の思いを、ときには笑いもまじえながら、とにかく熱量を持って伝える。話しながら汗だくになることもあります。すごいカロリーを消費しますよ。単に私が話好きなだけかもしれませんが(笑)。でも、思いが伝わらなければ人は動きませんから、そこにはじっくり時間をかけます。
あとは、普段からメンバーに声をかけること。真面目な話ばかりしていると堅苦しくなるので、コミュニケーションは肩ひじを張らずにやった方がいい。リーダーが気軽に「元気?」と声をかけることで、メンバーがほっとする瞬間もあると感じています。
また、メンバーが相談に来たときは手を止めて、相談者の悩みの解決を優先することが大切です。
竹内:リーダーはメンバーのことを常に気遣いつつ、リーダー自身も人格者でなければいけないんですね。
能原:「人格を磨け」ということは、メンバーにもよく言います。リーダーは実務能力ではなく人格を磨くべき、ということは稲盛もよく言っていましたし、今のトップマネジメントもよく使う言葉です。
竹内:御社の製品の強みは世界的に有名ですが、それ以上にメンバーや会社、そこにいる人々が御社の強みになっているように感じます。
能原:そうですね。ただ、一つ懸念点があります。コロナ禍やさまざまな変化を経験する中で、物理的なコミュニケーションの時間が短くなっています。同じ熱量でも、リモートは対面にくらべ伝わり方に違いがある。対面の方が、人の発しているカロリーのようなものが届くのかもしれません。オンラインコミュニケーションが増えていくことが時代の流れなのだとしたら、それに合わせて新しいコミュニケーションの方法を模索する必要があるでしょうね。

新規事業は成長のための先行開発
竹内:現職として取り組まれている新規事業の中でも、特にサステナビリティの分野は各企業が最重要課題として取り組まれていると思います。御社は、その中でもどの領域に重点を置き、どのような取り組みをされているのでしょうか?
能原:食糧問題、生物多様性、食料安全保障など、社会課題の解決を第一に、当社が貢献できることへの取り組みを進めています。
明らかにわかっている問題としては、地球温暖化と人口増加に伴う食糧問題です。今80億人いる人口が100億人になる時代を迎えると、単純に20億人分の食料がさらに必要となる。とはいえ、農地はもうない。これ以上森林を伐採すればCO2をキャプチャーできなくなるので、今度は温暖化への影響が大きくなる。
そこで、当社の光波長制御技術を使って、稲の栽培をしたり、養殖場で魚の成長を促進させたりするなど、食料を恒常的に工業生産する方法が考えられています。
他に例を挙げれば、AIを活用したロボティクスサービスがあります。これは、日本が抱えているような労働力減少という課題を解消するための取り組みです。
また、環境への取り組みとして、インクジェット捺染プリンター「FOREARTH」が挙げられます。この技術は、水をほとんど使わずに生地を染められるため、従来の捺染と比べて水の使用量を大幅に削減し、水質汚染の問題を解決するための一歩となっています。
これらは既存事業の延長線上にあるビジネスではなく、将来の成長のための先行開発です。京セラは、技術シーズではなく、市場ニーズに基づいて必要とされるサービスを提供していきたいと考えています。 
ゼロベースの思考で「あたりまえ」を疑う
竹内:本プロジェクトは、「社会課題の解決ができる人材を育てていく」がテーマになっています。ソーシャルイノベーションを起こし社会課題を解決するような人材には何が必要だと思いますか。
能原:好奇心と疑問を持つことです。世の中の動きをそのまま受け入れてしまうと、そこから新しい発想は生まれません。「なぜそうなっているのか?」を知ろうとする姿勢が、新規事業開発やソーシャルイノベーションには不可欠です。
先ほどのインクジェット捺染プリンターにしても、「なぜ水を使って生地を染めているのか?」「服の生地って染物でなければいけないの?」という疑問から生まれました。京セラは複写機のビジネスをやっているので、あるとき「印刷で代替できるのでは?」とひらめいた。この着想が重要なんです。
今後AIの活用が進み、事業計画などで活用されていくでしょう。例えば、AIに「今の社会問題を30個列挙してください」と指示すれば、すぐに回答を得られます。しかし、その中からどの問題が本当に興味深くて、取り組む価値があるかを判断するのは、まだまだ人間の役割です。
竹内:ソーシャルイノベーションには、課題"解決"能力よりも課題"発見"能力が必要だということですね。
能原:そうですね。課題を設定する上で重要なのは、「何が問題なのか」をきちんと把握することです。問題が定義できれば、あとは解決策を考えるだけ。その手段はさまざまあります。ゼロベースの思考を持って、「あたりまえ」を疑いながら取り組んでいける、胆力のある人材がこれからは求められていくと思います。
ただし、民間企業が取り組む場合、「事業として成立するか」という視点も必要です。世の中の役に立ついいアイディアだとしても、コンスタントに利益が出るテーマでなければ、事業は継続できない。ここで多くのプロジェクトが頓挫します。ボランティアでやるのであればいいですが、「誰がそのコストを負担するのか」という点は、曖昧になりがちです。
竹内:サステナビリティというと社会貢献活動のように思われがちですが、そうではなくて、解決していくことでビジネスとして成立させていくことが重要だということですね。
能原:そうしなければ、長続きしないと思います。企業が継続的に活動するためには、適正な利潤が不可欠です。それは潤滑油のようなもので、利潤がなければガタが来て動かなくなってしまいます。サステナビリティに取り組むのであれば、ビジネスモデルや収益構造がしっかり設計された状態で始めるべきでしょうね。

スペシャリストであるよりもこれから重要なこと
竹内:御社が求めている人材像についてお聞かせください。これまでのお話にもヒントがあったように思いますが、あらためて京セラが現在求めている人材とはどのような方でしょうか。
能原:先ほども申し上げた、好奇心と疑問を持つ姿勢ですね。そこに尽きます。
私が現在所属している部門では、新規事業開発とサステナビリティに取り組んでいます。どちらも自分で仕事を作り出す部門です。以前は、新入社員に対して数年間の教育トレーニング期間を設け、その後部門に配属されて先輩の仕事を見習う、いわゆるOJTが一般的でした。しかし、私たちの部門に来る新入社員は、最初から自分で仕事を作り出さなければなりません。
そのためには、自分からアクティブに動く必要があります。待っているだけでは何も始まらない。そういった環境で、無理なく自発的に行動できる人材が理想です。
竹内:大企業にいながら、新入社員から新規事業の開発に携われる可能性があるんですね。うらやましい環境です。
能原:個人的には、従来の教育方法では、現代の急速な技術進化に追いつけなくなっていると感じています。OJTで5年かけて教育しても、技術の進化の方が早ければ、5年後には学んだことを活かせなくなってしまいます。だとしたら、最初からフレキシブルにしたほうがいい。特定のスキルを習得するよりも新しいことを学び続け、外部の環境変化に対して柔軟に適応できる能力を磨くべきだと思います。
竹内:本プログラムは3大学共同で実施し、臨床心理学、地域共創学、政策学という多角的な学びを提供します。このような多様な知識を持つ人材は、これからの社会や御社のような企業で求められると思いますか?
能原:ポリバレント、つまり多様な環境に適応する能力は非常に重要だと思います。若いうちから多角的に学んで、経験を積んでおくことは、これから先の時代においては有効でしょう。これまではじっくり一つの分野に集中して、スペシャリストになることに価値があるとされてきましたが、これからはきっとそうはなりません。
現代は、さまざまな事象がカオス的に混在し、古いものがまた流行ったり、全く新しいものが登場したりする多様性の時代です。予測困難な環境でも、柔軟に対応できる能力を若いうちから身につけておくことは非常にいいことだと思いますよ。

特色ある地域発展を目指すために
竹内:最後に一点お伺いしたく思います。本学と龍谷大学は京都、琉球大学は沖縄という土地柄の異なる大学が連携しています。企業から見て、それぞれの地域の特性を生かしたコラボレーションは生まれると思いますか?
能原:地域間の交流で、新しいものを生み出す可能性はたしかにあるかもしれません。当社も、グループ会社を含めて日本全国に拠点があり、転勤者も多くいます。日本がここまで便利になって同質化が進んでいる中で、京都と沖縄でどれほどの差があるのかという点は考慮する必要があるでしょうね。
竹内:日本人の標準化が進んでいること自体が、社会課題と言えるかもしれません。だとすると、地域に根ざした人材育成が一つの解決策になる可能性があるのではないでしょうか。
能原:おっしゃる通りですね。これからは高齢化が進み、定年退職後に地方に戻る人が増えていくでしょう。そういった方々は時間に余裕があります。会社人生で、プライベートでの人脈が限られている人も多いでしょう。
例えば、私みたいにマーケティングの経験がある人が、地域の商店街でイベントを企画したり、エンジニアの経験がある人が3Dプリンターを使ってモノづくりをしたり、それぞれの専門性を活かした活動をする人が、今後は増えていくかもしれませんね。
これからの高齢者の生き方として、そういった時間の使い方があちこちで出てくるように思います。人件費もほとんどかからないので、うまく活用できれば地方の特色ある発展につながるのではないでしょうか。

おわりに
今回のインタビューを通じて、京セラが持つ「人を中心に据えた経営」の奥深さを改めて実感しました。技術革新や市場ニーズの変化に対応することはもちろん重要ですが、最終的に企業を支えるのは「人」であり、その人の成長や幸福を追求することが、結果的に企業の持続的な発展につながるのだと強く感じました。
特に、稲盛氏が残した「リーダーは心理学者でなければならない」という言葉は、臨床心理学を学ぶ私たちにとっても示唆に富むものでした。リーダーがメンバーの心理状態を理解し、モチベーションを高めることができれば、組織全体の生産性は大きく向上します。これは、京セラのアメーバ経営にも通じる考え方であり、小さな組織単位でリーダーシップを経験しながら、人材が育っていく仕組みの重要性を再認識しました。
また、新規事業開発において「ゼロベースの思考であたりまえを疑う」ことの大切さについても学ぶことができました。ソーシャルイノベーションに必要なのは、単に課題を解決するスキルではなく、「何が本当の課題なのか」を発見する力であるという言葉は、まさに本プログラムが目指す人材像と一致しています。
「大学連携型ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」では、臨床心理学、地域共創学、政策学といった異なる視点を組み合わせながら、社会課題に取り組むためのスキルとマインドを養っていきます。能原様のお話は、この学びをさらに深める貴重な機会となりました。
今後も、臨床心理学を軸にしながら、社会にインパクトを与えるイノベーションのあり方を探究し続けたいと思います。
京都文教大学 地域企業連携コーディネーター
竹内良地
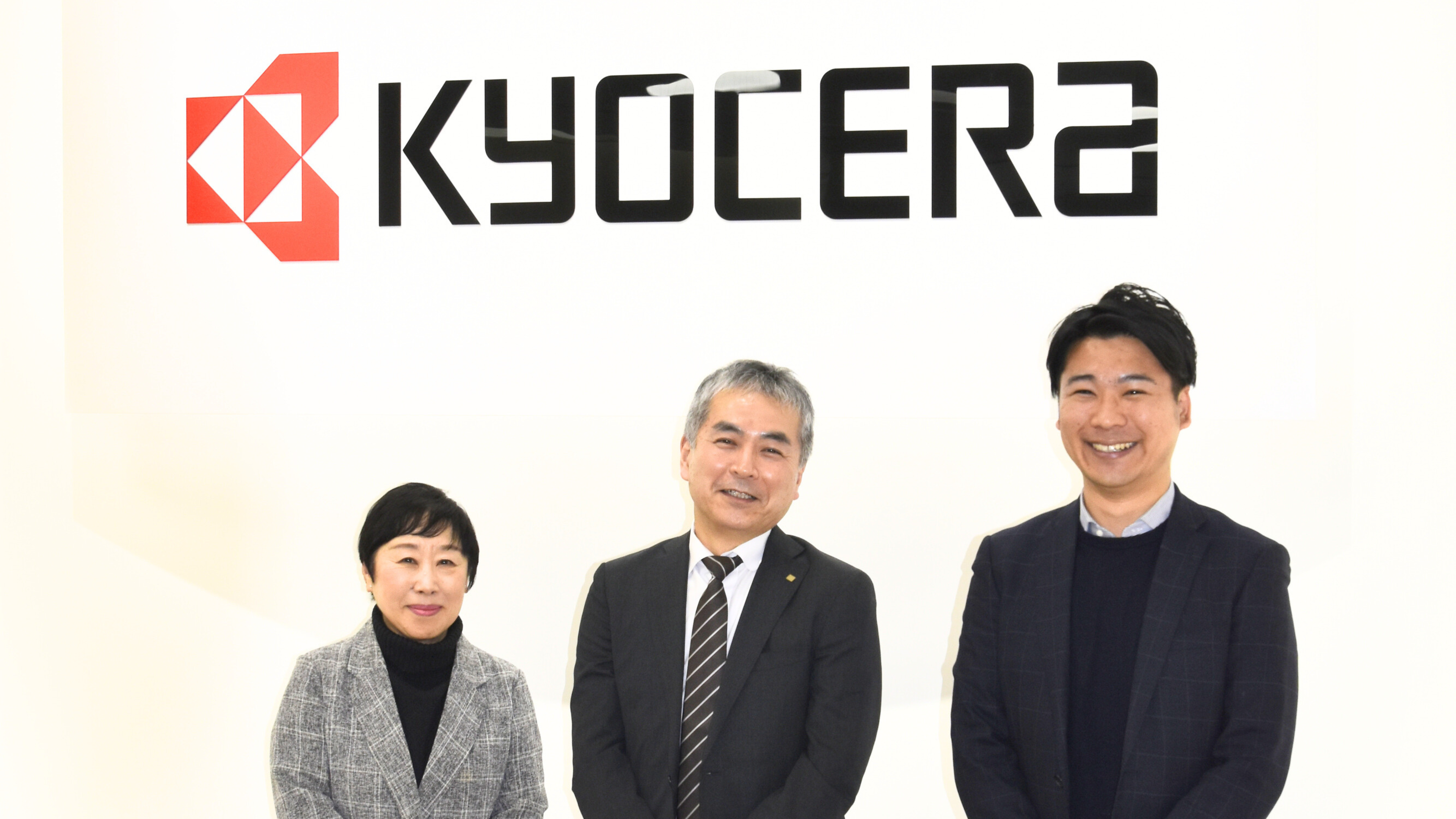
写真(左から、京都文教大学 産業メンタルヘルス研究所 研究所⻑ 中島恵子、京セラ株式会社 執行役員 経営推進本部長 能原隆様、京都文教大学 地域企業連携コーディベーター 竹内良地)
「大学連携型ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」のご紹介
龍谷大学大学院政策学研究科、琉球大学大学院地域共創研究科、そして京都文教大学大学院の3大学院が連携し、次世代のソーシャルイノベーション人材を育成するためのプログラムです。このプログラムでは、社会課題を多面的な視点から分析する力や、異なる領域の知見を統合し新たな価値を創出する力を養います。持続可能な社会の発展に貢献できる人材を育成することを目指し、臨床心理学の知見を活かしながら、社会課題解決に向けたイノベーションのプロセスやデザインを描けるイノベーション人材、そしてそのイノベーション人材を支援する心理専門家を育てていきます。
公式ホームページ:https://www.kbu.ac.jp/kbu/siprg/index.html