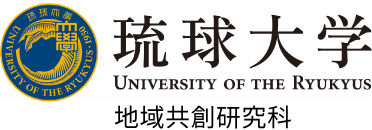Topics 2024 2024年度ニュース・プレスリリース一覧
2025.03.31
【株式会社LITALICO・八木氏】心理専門職としてではなく「人として何ができるか」が大事
はじめに
社会にはさまざまな課題が存在しますが、それらを解決するためには、単なる支援ではなく、新しい仕組みや視点を生み出す「ソーシャルイノベーション」が求められます。その代表的な企業の一つが、株式会社LITALICOです。
株式会社LITALICOは、「障害のない社会をつくる」というビジョンのもと、就労支援、発達支援、教育、キャリア支援など多岐にわたる事業を展開しています。単なる福祉支援ではなく、社会全体の構造を変え、すべての人が生きやすい環境をつくることを目指しているのが特徴です。ビジネスという枠組みを活用し、スピード感をもって社会課題を解決しようとする姿勢は、多くの企業や団体にも示唆を与えるものではないでしょうか。
今回のインタビューでは、株式会社LITALICOの人材戦略や事業展開の背景にある考え方に迫りながら、「ソーシャルイノベーションを生み出す企業とは何か」について探っていきます。お話を伺ったのは、LITALICOジュニアの人材採用に関わる八木様です。社会課題を解決しながら成長を続ける株式会社LITALICOのビジョンと、その実践について詳しくお聞きしました。
| 株式会社LITALICO 創業 :2005年12月 事業内容:LITALICOワークス(就労支援サービス) LITALICOジュニア(ソーシャルスキル&学習教室) LITALICOワンダー(IT×ものづくり教室) LITALICO発達ナビ(発達障害ポータルサイト) LITALICO仕事ナビ(障害のある方の就職情報サイト) LITALICOキャリア(障害福祉で働く人の転職サービス) LITALICOライフ (ライフプランサポート) LITALICO教育ソフト(特別支援教育に携わる教員向け支援サービス) 住所 :〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー15F/16F/20F H P :https://litalico.co.jp/ |
インタビュー実施日:2025年1月29日(水)

「障害のない社会」のためにさまざまな事業を展開
竹内:まず御社の事業概要について教えてください。
八木:LITALICOは、「障害のない社会を作る」というビジョンのもと、さまざまな障害福祉サービスを展開している会社です。日本語の「利他」という言葉と、「利己」という言葉が由来になっていて、社名がそのまま理念にもなっています。
竹内:御社は、LITALICOジュニアやLITALICOワークス、LITALICOキャリアなど、さまざまな事業展開をされておられます。各事業についても教えてください。
八木:最初に立ち上げた事業は、LITALICOワークスです。これは障害のある大人への就労支援サービスで、立ち上げた当初は、利用者の約7割が精神障害をお持ちでした。彼らの話を聞いていくと、多くの方が幼少期からの失敗体験の積み重ねによって、うつ病やパニック障害を発症していたことがわかりました。
この経験から、「もっと早い段階から個々に合った支援が提供できていれば」という思いで立ち上げられたのがLITALICOジュニアです。これは障害のあるお子様に対して発達支援を行うサービスです。
そこからさらに派生して、「学校教育以外にも、子どもたちの可能性を広げる場所があったほうがいい」という思いから、LITALICOワンダーが誕生しました。LITALICOワンダーは年長から高校生までを対象に、プログラミングやロボット開発、電子工作などを学べる教室です。
竹内:最近立ち上げられたLITALICO発達ナビも、同様に派生した事業ですか?
八木:そうですね。LITALICO発達ナビは、発達障害に特化したポータルサイトです。LITALICOジュニアに通っていないお子さまや保護者の方のために「困ったことがあればすぐに情報を得られるツール」の必要性を感じたことから、誕生しました。
お子様に発達障害という診断が出たとき、どこを頼って何をすればいいのか、調べるだけでも大変だと思うんです。そういうときに、あちこちに情報が散らばっているよりも、「ここを見れば必要な情報がまとまっている」という場所があれば便利ですよね。そうした思いから始まったのが発達ナビです。
情報を探す過程で疲弊される方も多いと思うので、その負担を少しでも軽減するために、情報をまとめたプラットフォームが発達ナビですね。
竹内:ほかにもここで紹介しきれないくらい、さまざまな事業を展開されていますね。
八木:はい。LITALICO仕事ナビという、発達ナビのLITALICOワークス版のようなサービスもあります。これは、就職を希望する大人が就労支援を行う事業所を探せるサイトです。
さらに、LITALICOキャリアという福祉サービスに特化した就職支援サービスや、障害のある方のご家族向けにファイナンスサポートを提供するLITALICOライフというサービスもあります。
竹内:ホームページを拝見しましたが、「ゆりかごから墓場まで」のような、子どもから介護まで包括的にサービスを提供されているという印象を受けました。
八木:事業を展開していく中で新たな社会課題が見つかると、すぐに事業化しようというのがLITALICOの強みです。
例えば、福祉に関する事業をやっていれば、「福祉施設で働く人材が不足している」という課題が見つかります。そこに対して事業化を計画する。新しい事業が派生すれば、また次の課題が見つかる。その結果、包括的な事業展開になっているのだと考えています。
子どもを取り巻く環境にまで広くアプローチ
竹内:数ある事業の中でも主力事業であるLITALICOジュニアは、どのように社会課題を解決してこられたのでしょうか。
八木:LITALICOジュニアは、お困りのあるお子様に対して発達支援を行うサービスです。最大の特徴は、お子様への直接支援だけでなく、お子様を取り巻く環境に対してもアプローチをしている、という点です。
中でも力を入れているのは、お子様への影響が特に大きい、親御様に向けてのアプローチ支援です。ペアレントトレーニングという形で、お子様へのかかわり方や褒め方をご家庭で実践していただいています。プラスアルファな褒め方をするなど、親御様の伝え方が少し変わるだけで、お子様のできることが一気に増えることもあるんです。
また、園や学校との連携にも力を入れていて、保育所などの訪問支援も実施しています。これは通常の学級に通っているけど集団だとお困りがある、いわゆるグレーゾーンにいるお子様を対象にしています。
例えば、学校の中で落ち着きがなくてよく動き回る、感情のコントロールが苦手でこだわりが強い、言葉の遅れがあって伝えたいことが伝えられない、といったお子様が通っている園や学校に行って、普段の様子を見せていただく。そして、園や学校の先生のお話を伺いながら、一緒に手当を検討していく、というものです。
具体的には声掛けのタイミングや、補助ツールの活用の仕方を伝えていくことで、お子様が園や学校でできることが増えたり、過ごしやすくなったり、という報告があります。
言葉の遅れがあるお子様に対しては、言葉の練習だけでなく、ジェスチャーで相手に伝える練習もします。感情のコントロールが苦手なお子様には、落ち着くための手段を一緒に考えます。
一人のお子様に対して包括的にアプローチをすることで、お子様にとって障害のない社会を作っていくことが、LITALICOジュニアの仕事です。
竹内:NPOや社会福祉法人の場合、当事者であるお子様への支援が主になると思います。周囲の環境までケアされているというのは、ビジネスならではですね。
早く大きく動かせることがビジネスの強み
竹内:福祉事業はNPOや社会福祉法人といった非営利団体が担うケースが多い印象ですが、御社はビジネスとして課題解決に取り組んでいらっしゃいます。非営利ではなく、ビジネスとして解決しようとされてきたのは、どのようなお考えからでしょうか。
八木:ビジネスとしてやる方が、早く大きく動かせるからです。もちろん非営利でもできることはあると思いますが、社会にインパクトを与えていくという意味では、なるべく大きく、そしてスピード感を持って動かしていく必要があると考えています。
竹内:創業から20年で、これだけの事業を立ち上げられたのはすごいですね。課題があれば、すぐに事業化をしていくというのは、御社の風土なのでしょうか。
八木:風土としてビジネス志向が強いかというと、そうでもないと思います。それよりは「障害のない社会を作る」というビジョンに対して、強いこだわりを持っている人が多いと感じています。さまざまな事業が立ち上げられているのも、「社会をよりよくしたい」という思いがあるからこそですね。
働くことを通じて自分の成長や喜びを実現してほしい
竹内:八木さんがLITALICOさんを選ばれたのはどういった理由からですか。
八木:私は教育や福祉、障害といった分野には、もともと関心がありませんでした。メーカーや商社の営業職で内定をいただいていたんですが、内定先で仕事見学をさせていただくうちに、「営業で利益を生み出すこと」より「人と関わる仕事」がしたいと気づいたんです。
自分の行動によって誰かが成長したり、変化したりする瞬間に立ち会いたい。その「相手」として思い浮かんだのが、障害のある方々でした。
実は、私の母が高次機能障害を抱えていて、昔から一人で生活することが難しく、就職活動も苦労したようでした。その姿を見て、「母のように障害のある方々をサポートできる仕事がしたい!」と思うようになりました。
それからは障害に関する仕事を検索して、大学4年の6月という就活も佳境の時期に、LITALICOのホームページにたどり着きました。カラフルで明るいデザインにまず惹かれましたし、「障害のない社会をつくる」というビジョンが「自分の思いとぴったり!」と、心を掴まれました。
すぐに説明会に参加して、「私はここで働くんだ!」って。もうLITALICOに入社すること以外、考えていませんでしたね。
竹内:御社に入社される方は、やはり「利他」「利己」という精神に共感をされる方が多いんでしょうか。
八木:そう思いますね。特に大事にしているのは、「利己的に働く」という部分ですね。誰かのために、という利他的な気持ちも大事ですけど、それだけではなく、働くことを通じて自分の成長や喜びを実現してほしい。LITALICOに入社してくる人は、そこに共感してくれるんじゃないかなと思っています。
多様な専門職の採用を推進
竹内:LITALICOジュニアには、臨床心理士や公認心理師の資格を持っている専門職の方は、どのくらい在籍されているのでしょうか?
八木:LITALICOジュニアの場合、専門職は教室に1~2人、多くて3人程度です。本当はもっと専門職の割合を増やしていきたいんですけど...自治体による要件、例えば「勤続年数が5年以上の方を優遇する」といった規定があるため、難しい部分もあるんです。
LITALICOジュニアは、新卒採用にも力を入れています。専門職の方も積極的に採用していて、大学院を卒業された公認心理師や臨床心理士、臨床発達心理士、さらに作業療法士や理学療法士、言語聴覚士といったセラピスト系の資格をお持ちの方が多く在籍しています。
新卒だけでなく、中途採用でも専門職の採用を進めていますよ。
心理専門職としてではなく「人として何ができるか」が大事
竹内:専門職として資格を持って、最初は現場で働いていて、後からビジネスサイドの仕事に移られる、というケースもありますか?
八木:それは職種問わずあります。最初は現場で経験を積んで、その後コーポレート部門や、発達ナビなどのポータルサイト運営、BtoB事業など、ビジネスサイドの仕事に移る方もいらっしゃいます。
竹内:今までの心理専門職の働き方にはない展開ですね。これまでは専門職として入ったら、ずっと専門職として働くことが多かったと思うのですが、会社としてはどういったメリットがあるのでしょうか。
八木:採用としては、すごくメリットを感じています。心理専門職を積極的に採用したい場合、就職活動をしている心理専門職に訴求するポイントは、やっぱり心理専門職自身がいちばん理解しています。実際に昨年、心理専門職の方が採用部門に来てくれたことで、その効果を実感しました。
採用以外でもメリットはあって、例えばLITALICO発達ナビでは、心理専門職の知見を基に論文を書くこともあります。大学院で培った専門知識やスキルが、さまざまな業務に活かされていると感じることは多いですね。
竹内:現場で専門の仕事をされてきた方がビジネスサイドに移られるというのは、職種がガラッと変わると思うんですけれども、うまく適応される方の共通点はありますか?
八木:自分で考えて行動する力がある方は、どこに行っても適応しやすいという印象があります。
LITALICOジュニアの指導員は、専門職として入社しますが、実際の仕事内容は専門職とそれ以外の職種でそんなには変わりません。その中で「自分が学んできたことをどう活かすか?」を考えながら行動されている方は、成果を上げています。
心理専門職として何ができるか?を考えることはもちろんですが、心理専門職としてだけでなく、「人として、その人に何ができるか?」を意識して行動されている方は、他の部署や違う役割に移っても活躍されています。
やりたいことがあれば応援してくれる環境がある
竹内:新卒の専門職の場合、初配属は必ず現場になりますか? それともビジネス職やコーポレート職での専門職の採用もあるのでしょうか。
八木:基本的に最初は現場への配属になります。採用は事業部ごとに行っていて、新卒採用はLITALICOの主軸になっているLITALICOワークス、LITALICOジュニア 、LITALICOワンダーの3事業部です。
竹内:人事の目線として、どういった方、どういった資格を持っている方が望ましいですか?
八木:「まずは自分で考えてやってみる」ということができる方に入社していただきたいです。
その人がやってみたいことを応援してくれる環境があるところが、LITALICOのいいところ。自分が疑問に思ったり、改善したいと思ったら、すぐに行動に移せる素直な人のほうが、LITALICOの社風にフィットすると思います。
専門職としての採用枠はありますが、例えば心理専門職として「検査をたくさん取る」といった業務ではないので、そういうイメージで来られると、物足りなく感じる方もいるかもしれません。
それよりは「自分で考えてやってみよう」というマインドでいる人の方が楽しそうに働いています。 働き方の自由度が高いところも魅力だと思います。自分の意志を持ち、やりたいことを形にしたい方にとって、LITALICOはとても魅力的な職場だと思います。
竹内:専門職というと一つのことを突き詰めるというイメージがありますが、さまざまなことに幅広く興味を持ってチャレンジできる方を求められているということですね。
縦にも横にもキャリアは広げていける
竹内:新卒として現場で入った後に、ビジネス側に転向するキャリアパスもある一方で、専門職としてキャリアを伸ばしていく道もありますよね。
八木:もちろんです。現場で専門性を深め、教室長やマネージャーなど、縦にキャリアを伸ばしていきたい方も歓迎しています。
LITALICOジュニアでは入社して半年後から教室長やチュー
心理学を活かせる仕事はたくさんある
竹内:一般職についてもお伺いさせてください。八木さんが入社後にLITALICOジュニアの指導員として配属された際、心理学の知識や経験はどのように役立ちましたか?
八木:大学で学んでいたカウンセリングのスキルが役立ちました。親御様へのヒアリング、園や学校とのやり取りにおいて、どうすれば相手の本音を引き出せるか、どういった質問の流れで進めていくべきかなどは、心理学を学んでいたからこそスムーズに入ることができたと思います。
LITALICOの支援の考え方は、応用行動分析という心理学の手法を基盤としています。私自身は応用行動分析を学んでいたわけではないんですが、統計や分析の授業は受けていたので、「根拠に基づいて支援を行う」という考え方に自然と馴染むことができました。
竹内:心理学って人の心を扱うものですけど、ビジネスも人と人が行うものである以上、あらゆる場面で心理学は活きてきますよね。
八木:そうですよね。少し話が変わるかもしれませんが、今は採用の仕事をしていて、セルフコントロールがすごく大事だと感じています。ストレスを認識して自身をケアしていく方法を大学時代に学びましたが、これは社会人になれば誰しもが役立てられるスキルだと思います。
ストレスチェックの内容や実施する意味についても、社会人になってから「なるほどな」と思える発見がたくさんありました。
竹内:心理学部を卒業されているスタッフさんは結構いらっしゃるのですか。
八木:学部卒の方もたくさんいますよ。私自身も学部卒ですけど、以前は大学院に行って心理専門職の資格を取らないと、心理学を活かせる仕事はないと思っていました。
でも、LITALICOジュニアの児童指導員は、心理学部を卒業していれば認定される資格なので、学部卒の方が多く応募されていますよ。
LITALICOの活動が社会の意識づけにつながってほしい
竹内:大学の心理学部と産学提携も積極的にされています。狙いについてお伺いしてもいいですか。
八木:一言で言えば、「LITALICOをより多くの人に知っていただきたい」というのが目的です。
採用的な意味もありますが、LITALICOを知ることで、障害を持つ人に対しての意識が多くの人に芽生えたらいいと考えています。
例えば、障害のある方にとっての生きづらさは社会の側にも原因がある、という意識を持ったり、自分が困っている理由や身近な人が困っている原因について考えたり...LITALICOの事業を知ることで、そういう意識につながってくれればいいですね。
また、LITALICOジュニアやLITALICOワークスなどの事業所を増やして、困っている方たちに必要な支援をもっと届けるためにも、LITALICOを知っていただきたいという思いもあります。
学生は学生として学び抜いてほしい
竹内:最後に、八木さんから学生たちに、大学時代に学んでおくべきことについてアドバイスをお願いします。
八木:語弊があるかもしれませんが、「何もしなくていい」と思っています。学生の期間は、学生として全うしてもらうのが一番いいです。
今学んでいることが経済学なら経済学をちゃんと学んでほしいし、心理学なら心理学をちゃんと学んでほしい。学んでいることを、学び抜いてほしいですね。
でも、「4年間をムダにしないようにしなくちゃ!」と変に気負う必要はないと思います。せっかく大学生なんだから、旅行に行ったりサークル活動を楽しんだり...その期間にしかできないこともたくさんしてほしいです。
社会人になってからのことは、社会人になってからいっぱい学べますから、今しかできないことをやっておいた方がいいと思います!
おわりに
株式会社LITALICOの取り組みから感じたのは、「社会課題の解決には、視点の転換が必要である」ということです。障害のある人への支援を、単なる福祉活動ではなく「社会の構造を変えるビジネス」として捉え、スピード感をもって事業を展開している姿勢は、まさにソーシャルイノベーションの体現と言えるでしょう。
特に印象的だったのは、「障害のある人の支援」と言いつつも、実際にはその家族、学校、企業、社会全体にアプローチをしている点です。個人を支えるだけでなく、その周囲の環境を変えることで、より大きなインパクトを生み出す。この視点こそが、株式会社LITALICOが持続的に成長し、社会的価値を生み出し続ける理由だと感じました。「新たな課題が見つかれば、それをすぐに事業化する」という柔軟でスピーディーな経営スタイルも、株式会社LITALICOの大きな強みです。
今回のインタビューでは、「障害のある人を助ける」だけではなく、「障害という概念そのものをなくしていく」ための取り組みを知ることができました。この視点は、福祉に限らず、多くの業界・企業にとっても重要なヒントになるはずです。
社会課題に向き合い、解決しようとするすべての人にとって、株式会社LITALICOの挑戦は大きな示唆を与えてくれるものです。
私たちも、こうした実践例を参考にしながら、社会課題の解決に貢献する人材の育成に尽力していきたいと思います。
京都文教大学 地域企業連携コーディネーター
竹内良地
「大学連携型ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」のご紹介
龍谷大学大学院政策学研究科、琉球大学大学院地域共創研究科、そして京都文教大学大学院の3大学院が連携し、次世代のソーシャルイノベーション人材を育成するためのプログラムです。このプログラムでは、社会課題を多面的な視点から分析する力や、異なる領域の知見を統合し新たな価値を創出する力を養います。持続可能な社会の発展に貢献できる人材を育成することを目指し、臨床心理学の知見を活かしながら、社会課題解決に向けたイノベーションのプロセスやデザインを描けるイノベーション人材、そしてそのイノベーション人材を支援する心理専門家を育てていきます。
公式ホームページ:https://www.kbu.ac.jp/kbu/siprg/index.html