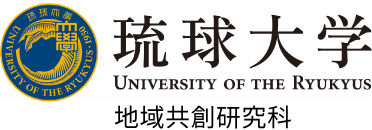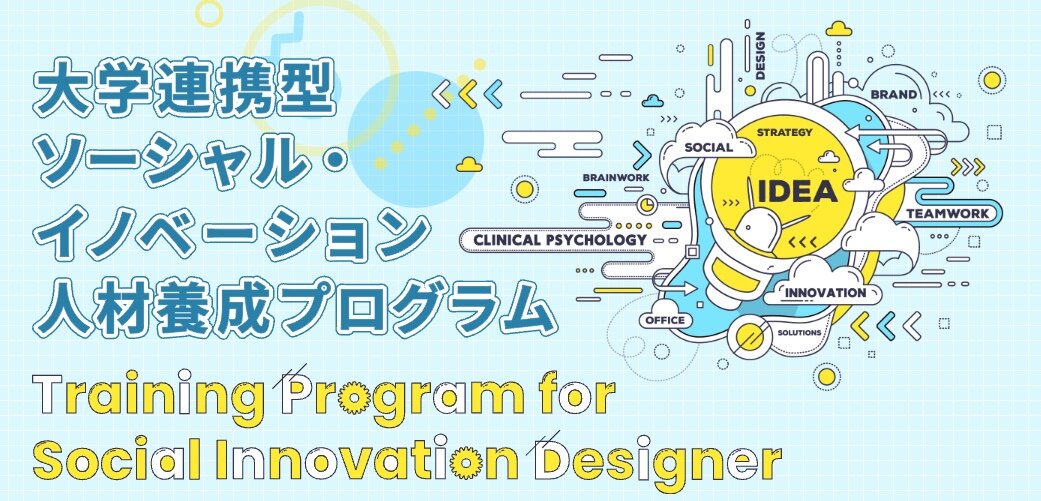Topics 2024 2024年度ニュース・プレスリリース一覧
2025.02.26
【神田東クリニック・森啓祐氏】産業現場で働く心理専門職のホントのトコロ「自分が誰のために何を提供したいのか?を明確にすること」が大切。
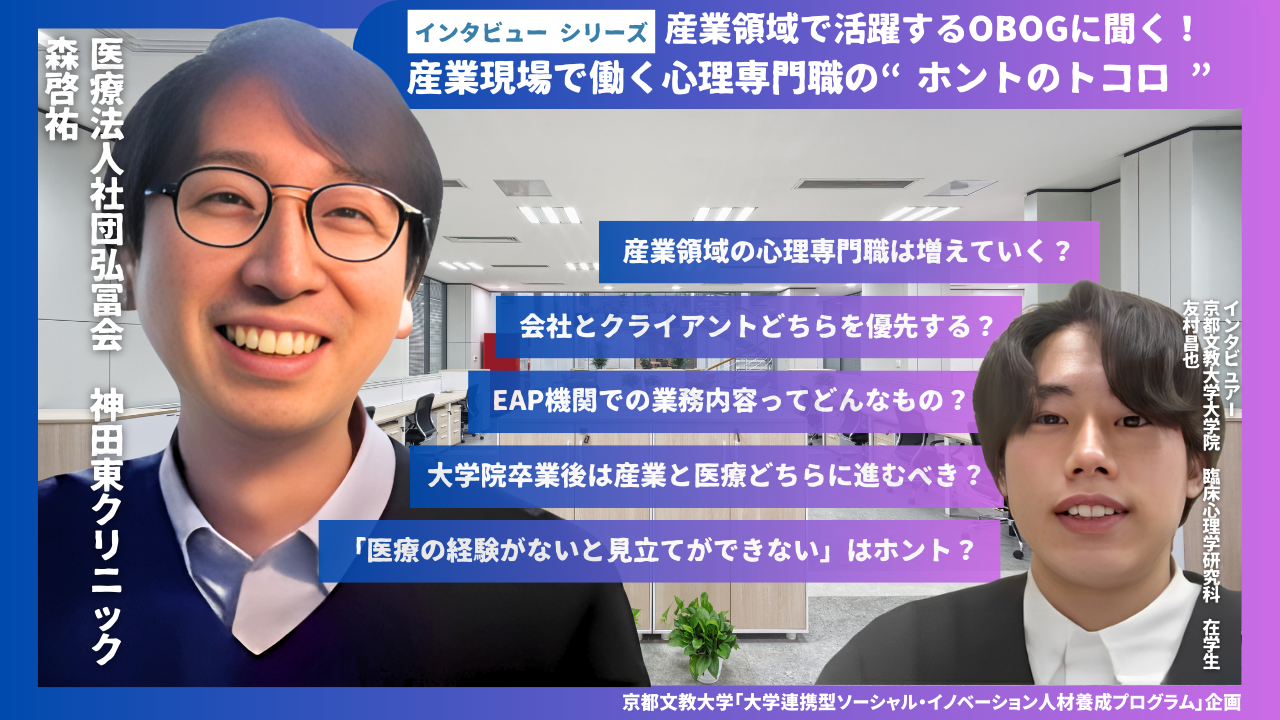
はじめに
心理専門職といえば、医療や教育の現場をイメージされる方も多いかもしれません。しかし、近年では企業や組織の中で活躍する「産業領域の心理専門職」にも注目が集まっています。ストレスチェックやEAP(従業員支援プログラム)の導入が進む中、職場のメンタルヘルスをサポートする専門家として、心理専門職の需要は確実に高まりつつあります。
今回の記事では、京都文教大学大学院臨床心理学研究科のOBである森さんに同大学院在籍の大学院生・友村さんがインタビューを行い、産業現場で働く心理専門職の実情に迫ります。
森さんは、京都文教大学大学院の修士課程を修了後、企業内の心理士として7年ほど勤務し、現在は心療内科・精神科クリニック併設の外部EAP機関の医療法人社団 弘冨会 神田東クリニックに勤務されています。
今回は、浪人時代の原体験から心理専門職を目指すことになったきっかけ、企業内EAPで味わった理論と現場のギャップ、さらには産業領域ならではの苦悩ややりがいなど、具体的なエピソードを交えてお話しいただきました。
これから大学院受験を考えている方、あるいは将来の進路で産業領域に興味を持っている大学院生に向けて、産業心理の現場がどのような可能性や課題をはらんでいるのか、一歩踏み込んだ視点を提供できればと思います。心理学が組織や従業員の支援にどう活かされるのか、"ホントのトコロ"をぜひご覧ください。
医療法人社団 弘冨会 神田東クリニック
事業内容:心療内科・精神科クリニック併設の外部EAP機関
住所 :〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田東山ビル 3階
H P :https://www.iomhj.com/clinic/
オンラインインタビュー実施日:2024年12月20日(金)
話すだけで救われた予備校時代の原初体験
友村:心理専門職を志したきっかけについてお聞かせください。
森:きっかけは、あるカウンセラーとの出会いです。
実は私、大学で心理学を専攻する前に一浪しているんですよ。浪人時代に予備校に通っていたのですが、その当時は勉強に全然身が入っていませんでした。志望学部も定まっていなかったし、やらなければいけないことはわかっていても、なかなか手がつかない。
そこで、予備校にカウンセラーがいたので、試しにカウンセリングを受けてみたんです。そうしたら、心がすごくすっきりしたんですよね。「話すことってこんなに効果があるんだ!」という気づきがありました。
そんなことがあって立命館大学の心理学部に入りました。修了後、一度は住宅営業の会社に就職したのですが、働く人のメンタルヘルスについて考えるきっかけもあって、やはり「心理専門職になりたい」という思いが芽生え、京都文教大学の大学院に入ったことが、心理専門職を目指したきっかけですね。
友村:僕も浪人したんですが、僕の予備校にはカウンセラーがいなかったので、吐き出せる場所がなかったですね。
森:心理専門職がいない予備校の方が多いでしょうね。私の場合は、そこで今後の進路を左右する経験をさせてもらったので、今思うとご縁だったなと思います。
EAP機関での業務内容ってどんなもの?
友村:現在、森さんは心療内科・精神科クリニックに併設されたEAP機関で働かれているとのことですが、そこでの役割や日々の業務内容について教えてください。
森:今は、精神科・心療内科の医療機関と、外部EAP機関が併設された、神田東クリニック/MPSセンターで働いています。医療機関(神田東クリニック)での主な仕事としては3つあります。
1つ目はインテークと呼ばれる、初診の患者さんに対する予診です。患者さんが安心して診察に臨めるように関わりながら、状況の全体像を把握し、主治医に共有して診察につなげていくという仕事です。2つ目は、医療機関内でのカウンセリング。3つ目が心理検査です。検査の実施やフィードバックを通して、今後の治療に活かしていく、というものですね。
外部EAP機関(MPSセンター)での業務についてですが、企業の抱えているメンタルヘルス上の課題に対する見立てや改善に向けたコンサルテーションを通して、企業側の担当者と連携しながら施策を実行に移していきます。例えば、顧客企業の事業所に伺ってカウンセリングを実施することもあれば、課題やニーズに応じて研修を企画・提案し講師を務めることもあります。また、ストレスチェックの実施サポートや集団分析の結果報告・改善策の提案なども担当しているので、まぁ幅広くやらせてもらっています。
友村:求職者支援や緊急対応にも関わるそうですね。どの場面にも関わっていく、大変な仕事だと感じました。
森:業務内容は多岐にわたりますね。今おっしゃってくださったようにポストベンションといって、緊急事態が起きたときにメンタル的なサポートをしていくこともあります。
今思えば痛いカウンセラーでした
友村:産業領域で心理専門職として働かれてきた中で、特に印象に残っているエピソードや直面した課題について教えていただけますか。
森:印象に残っているのは、やはりイニシャルケースですね。大学院を出た直後に企業内EAPのカウンセラーとして働き始めたときのことです。カウンセリングで学んだ理論が、実践だとまあうまくいかない。
沈黙の重要性というのは学んでいたけど、実際に3分間沈黙が続くと、ただただお互いに気まずくなってしまって(苦笑)。他にも、体調が悪い中カウンセリングに来てくださったクライアントに対して、「体調が悪いなら来なくても大丈夫だったのに」と言ってしまったこともあります。当時の私としては体調を心配して良かれと思って言っていたんですけどね。今思えば、クライアントの思いをまったく汲んでいない、理解できていない、「痛い」カウンセラーだったと思います。最初はこんなことの繰り返しでした。
クライアントが来なくなってしまってから「全然話を聞いてあげていなかった」 「全然寄り添えていなかったな」とようやく気づき、反省しました。それからは「どうすれば寄り添えるか?」を日々の現場で学んでいきました。理論を学ぶことはもちろん大切ですが、実践で体験して学ぶことも同じくらい大切だと思います。自分の「痛さ」や失敗への反省は程々にしつつも、それをクライエント支援のためにどう活かして還元していくかが、大事なのかなと思います。
現場での実践で学んだ"重要な質問"
友村:ほかにも印象的だったことはありますか?
森:そうですね...
産業領域に限ったことではないのですが、クライアントに睡眠のことを聞く、ということの重要性は、現場での実践を通して痛感しましたね。大学院では成育歴を中心に聞いていましたが、産業領域でのカウンセリングでは「眠れていますか?」という質問がその方のメンタルヘルスの状態を見立てる上で非常に重要なんです。カウンセラー1年目の時、睡眠の状況を聞かずにいたら、先輩カウンセラーに「なんで睡眠のこと聞いてないの!?」ってビックリされて(笑)。それ以降は必ず聞くようになりましたね。
友村:やっぱり睡眠不足による影響って大きいんですね。
森:睡眠はとても重要です。働く上で、十分な睡眠をとらないと心身に疲れが溜まります。その状態が解消されずに続いてしまうと、仕事のパフォーマンスが落ちたり、夜遅くまで残業をして睡眠時間が減ってしまったり、朝起きられず出勤ができなくなったりして、結果として抑うつや不安といったメンタルヘルス不調の状態につながってしまうこともあります。実際、産業領域で出会う不調を感じている方は、睡眠に何らかの問題を抱えていることが多い印象があります。
もちろん、睡眠の状況以外にも大切な質問は他にもありますが、産業領域でのカウンセリングの実践の中で学んだこととして、今でも印象に残っています。
企業の心理職として抱える葛藤
友村:EAPについて、企業の内部で関わる場合と外部から関わる場合の違いについて教えてください。
森:そうですね。メリット、デメリットでお話ししましょうか。
内部にいるメリットは、内部の仕組みやルール作りに携われる点です。例えば、部署の特定の課題に対して、どのようなケアが必要かという点に関与しながら観察できるので、理解は増しますよね。
デメリットは、組織の一員として深く関わることで、身内の論理や先入観に陥りやすいことです。「あの人/部署はこうだよね」とか「これはこういうものだから」とレッテル貼りや思考停止が自分に起きていて、問題の本質やその背景要因が見えなくなったことがありました。
あとは、一社員としてさまざまな業務を求められる点ですね。専門職としての仕事だけでなく、総合職として専門性を用いない事務作業や調整業務をすることもありました。
今ではとても役にたつ経験ができたと思えていますが、当時は葛藤を抱えていましたね。自分が本当にやりたいと思う仕事じゃないことも役割としてはやらないといけない。「企業内部」に限ったことではないかもしれませんが、自分が何を大切にしたいか?という軸はしっかり持っておくこと、時折立ち止まって考えることはとても大事だと思います。これは、組織の方針や求められる役割に身を委ねきっていた自分への自戒を込めて、でもありますが。
友村:うーん、難しいですね。
森:そうですね。でも、悪いことばかりじゃないですよ。産業保健の実態や産業領域ならでは専門性は、身をもって理解・体験できますからね。心理職の中ではまだニッチな領域だからこそ、スペシャリストとしての価値も高まるのではないでしょうか。
ただ、「人の心への理解をもっと深めたい」という個人的な課題意識もあって、これまでの経験を活かせる外部EAPや医療機関での心理臨床を経験してみたい、と思うようになったことがきっかけで、その両方が併設されている神田東クリニック/MPSセンターに転職をしました。
外部EAPでは常に成果が求められる
友村:外部からEAPに携わるメリット、デメリットも教えてください。
森:メリットは、さまざまな企業への支援に携われること。企業風土は本当に多種多様だなと実感しますし、その経験の蓄積があるからこそ、それぞれの企業の特徴の見立てやコンサルテーションに役立っています。また、自身の専門性に集中しやすい感覚もありますね。
一方、デメリットは関われる範囲に限界があることです。内部ほどの近い距離感で深く関わることはできません。そしてなにより、成果を出さないと契約が終了となってしまうという点で、シビアな世界かもしれませんね。
友村:成果というのは、どのような指標があるのでしょうか?
森:1つは費用対効果でしょうね。 例えば、ストレスを感じている人が減ったとか、コンサルテーションで有益なアドバイスができたとか。具体的な成果指標は企業によると思いますが、企業の予算には限りがあるから、一般的なことしか言えないようだと、他に予算を回した方がいいよねっていう判断になることもあります。
友村:心理専門職の成果って、明確に数値化できるものじゃないですよね。
森:そのとおりです。だから成果以上に大事なことがあります。それは、信頼関係を築くことです。もちろん信頼関係だけでは、どうにもならないこともあります。企業はあくまで営利組織ですから、メンタルヘルスのことだけを考えているわけではありません。経営の方針が変わることに伴い契約が終了となる、なんてことも実際にありました。
外部EAPの立場としてできることとして、顧客企業との信頼関係を築き上げること、やっぱりそこは重要かなと思います。やっぱり最終的には、人と人、なんですよね。
友村:成果だけでなく、人との温かい信頼関係が大切ということですね。
会社とクライアントどちらを優先する?
友村:内部の話に戻りますが、企業で心理職として働くとき、クライアントの立場に立って考えることと、会社の立場を考えること、2つの軸があると思います。両者の狭間で、森さんはどのように判断し、対応されてきたのでしょうか?
森:すごくいい質問ですね! まずは、クライアント重視が基本です。面談に来られた方、お話しくださる方を最優先で大切にします。ただし、会社のルールや法律の枠内で、というのが前提になります。
例えば、「会社に行きたくないです」と言われた時。その「行きたくない」という気持ちはもちろん一旦受け止めますが、カウンセリングの中だけで「じゃあ行かなくていいですよ」という結論にはならないでしょうね。会社と労働者の間には雇用契約や安全配慮義務という明確なルールがありますから、その範囲の中で考えていくことになります。「行きたくない」背景には何があるのか?という視点が重要で、健康上の問題があれば医療機関で治療してもらう方向になるでしょうし、キャリアの問題を抱えているのであれば仕事への価値観の整理が役立つかもしれない。クライアントには内面を自由に話していただきますが、こちらはあくまでルールを想定しながら話をしないといけません。
面談は、クライアントが自ら来る場合もあるし、職場から「この人を見てほしい」と紹介される場合もあります。後者の場合、企業側のメッセージが強く出ますが、まずはその人との信頼関係を築いて、本音で話してもらうことが大切です。そうでないと、職場にフィードバックできる内容もなくなってしまいますし、結果的に誰のためにもならなくなってしまうからです。
だから、まずは目の前のクライアントに全力を尽くします。そして、クライアントの同意が得られた範囲内で職場にフィードバックをして、お互いの着地点を見つけていきます。ただし、会社のルールや法律の枠内で。それをクライアントにも最初に説明します。
また、治療はできないということも伝えます。産業保健スタッフや産業医、保健師との情報共有についても事前に説明します。職場には同意なしには情報を伝えないことも明確にします。その前提の中で最大限のことをするのが、私たちの仕事です。
内部と外部、心理検査の機会が多いのはどっち?
友村:内部と外部では、どちらのほうが心理検査をする機会が多いのでしょうか。
森:
内部でも外部でも、産業保健の範囲内では心理検査はあまり実施されないと思います。
質問紙形式であれば、抑うつ尺度や不眠尺度など健康状態の把握を目的としたスクリーニングとして用いられることはあると思いますが、自己理解を深めること目的とした心理検査が実施されるのは稀ではないかと。
というのも、産業保健では、健康状態を悪化させるリスクをいかに低減し、安心して仕事ができる職場環境をいかに作るか、という視点が主眼となるためです。勤務時間中に検査を受けている間は離席して仕事がストップすることになりますし、心理検査の結果を誰が、何のために、どのように扱うのか?という問題も出てきます。
将来、産業領域の心理専門職は増えていく?
友村:産業領域で心理専門職として働くための就職先は、どうやって見つけたんでしょうか?
森:私の場合は、本当にご縁です。「こういう話あるけどやってみない?」って言われて、「やってみます!」という感じでたどり着いたルートなので。ご縁がなかったら、産業領域の世界には入れてなかったんじゃないかと思います。
それぐらい産業領域への入口は狭いというか、まだまだニッチなんですよね。これからの課題だと思っていますよ。だから、この「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」にも、めちゃくちゃ価値があると思っています。
友村:5年先、10年先には、産業領域の雇用は増えていると思いますか?
森:増えると思っていますよ。ストレスチェックの導入など、企業が産業保健に対して力を入れつつあるし、それに付随して外部EAPサービスの拡充も進んでいます。企業がメンタルヘルスの重要性を理解すれば、心理職の雇用も増えてくる。産業領域で働く専門家たちの努力が、今後の発展に大きく寄与するでしょうね。
多様性の時代と言われますけど、多様性ってまさに心理専門職が得意とする分野だと思います。私たち心理専門職が、さまざまな背景を持つ人々の相談相手として役割を果たせるように、がんばっていかないといけないですね。
「医療経験がないと見立てができない」はホント?
友村:大学院修了後、産業分野に進まれたと伺いました。学校では、産業分野に入る前に医療経験を積むべきだとよく言われます。医療経験がないと見立てができない、というのが理由にあるようです。産業分野で働き始めたとき、医療経験がないことで困難はありませんでしたか?
森:これはもう即答で、ありました(笑)
おっしゃる通り、見立てなんですよね。見立てる力は、自分は確かに弱かったです。だから専門家としての意見も一般論になりがちでした。「なんかアテにされてないな...」と思うことも多々ありました。悔しかったですよ。でもそこは、腐らずに勉強するしかないので、やりましたけどね。
友村:見立てというのは、具体的にはどのようにするのでしょうか。
森:もちろん病態水準や症状に対する見立ても大事なんですけど、産業領域で特に重要な見立ては、「事例性」と「疾病性」の視点です。
「事例性」というのは、職場で実際に起きている問題のことです。例えば遅刻が多いとか、欠勤が多いとか、同僚と対立してしまうとか、職場で支障をきたす出来事を指します。
一方、「疾病性」は、医療的な視点で、どのような病気か、どのような症状が出ているか、といった側面を見ます。
事例性と疾病性の見立ては、産業や組織領域ならではのところがあるのではないかと思っています。どちらの問題なのかによって、連携する相手が医療機関なのか、職場上司や人事労務なのかが変わってきます。これが産業分野ならではの難しいところでもあり、面白いところでもあります。
いちばん難しいのが、疾病性と事例性の両方が複雑に絡み合っているようなケースです。こういうときは、職場(上司)、人事担当者、産業保健スタッフ(産業医、保健師、心理職など)、外部医療機関(主治医)がそれぞれの役割を果たせるよう、社内でできる範囲でのサポートを一緒に考えながら交通整理をしていく、というのが私たちの役割になると思います。
友村:なるほど。例えばうつ病だったらどうですか? まずは休養を勧めた上で、疾病性の改善を医療機関へリファーしていくのでしょうか。
森:そうですね。ストレスチェックで高得点が出て、医療機関での診察が必要だと判断される場合は、まず休養を勧めます。ただし、我々から「休んでください」と言うことはできないので、外部の医療機関の主治医に診断書を書いてもらうことで、リファーしていきます。
大学院修了後は産業と医療どちらに進むべき?
友村:今ご自身が大学院生の立場だとしたら、産業分野と医療分野、どちらを選ばれますか? 産業分野に直接飛び込むのもあるし、医療分野でしっかりと経験を積んでから進むという選択もあると思うんですけど。
森:すごい難しい質問ですね(笑)でも結論を言うと、どちらからでもやれると思います。
私自身は当時、医療からも声がけはあったんですよ。アルバイト先のクリニックなんですけどね。でも、最終的には産業分野を選びました。理由は、そのときの判断で「こっちの方が面白いかな」と思ったという、それだけです。
今、これまでの経験を踏まえて振り返ってみても、やはり迷いはあります。ただ、必ずしも医療分野から始めなければならないとは思っていません。産業分野から入れば、産業的な視点は医療分野にいる人より、確実に培われます。だから、どちらからでもなんとかなりますよ(笑)
ただ、そう言えるようになるには、ご縁を大切にして、その場でその場で全力を尽くしていくことです。その結果、見えてくる可能性もあると思います。「こうでなければいけない」というものはないんじゃないかな。少なくとも、自分はそう心がけてやってきました。
私の経験を振り返ると、クランボルツ教授の「計画された偶発性理論」(Planned Happenstance Theory)に通じるものがあるかな。目の前にあることを一生懸命やっていたら、いつの間にかそれが道になっていた、みたいな。偶然もたらされた機会を主体的に活かしていこうという理論ですね。
私も医療分野から入っていたら、また別の展開があったでしょうけど、産業分野から入ったことに後悔はないです。なんとかやってこられましたしね(笑)
ただ、学び続けることはもちろん必要だと思いますよ。そして、学んだことを、目の前の現場でどう生かすか。私自身もその気持ちを大切にして、一生懸命やってきました。
友村:わかりました。ありがとうございます!
森:悩みますよね。でも悩み尽くして自分で出した結論であれば、きっと後悔はしないはずですので、大いに悩んでください(笑)
大学院修了は「入口」でしかない
友村:京都文教大学大学院を修了されたとのことですが、学内での臨床心理学の学びや知識は、現在の産業分野のお仕事にどのように活かされていますか?
森:臨床心理学を学んでわかったのが、「人の心はわからない」ということです。そのスタンスを今でも大事にしています。
わかった気になるのが、一番危ないんです。レッテルを貼ったり、簡単に理解したつもりになることが、一番わかっていないんです。「なぜだろう?」「どうしてこうなるのだろう?」という謎を、クライアントと解きほぐし、一緒にわかっていこうとする姿勢が大事だと思います。
あと、大学院ですべてを学ぶことはできない、という前提は持っておいた方がいいですね。修了することよりも、修了後も学び続け、いかに自分をアップデートしていくかの方が重要です。
私自身、心理専門職になってからもSV(スーパービジョンの略。カウンセラーやカウンセラーを志す研修生が受ける訓練の一つ)を受け続けてきました。大学院時代には意味がわからなかったことも、現場に出ることでわかるようになることもあります。大学院は本当に入口でしかないと思いますよ。
「誰のために何ができるのか」を忘れないこと
友村:大学院生や、これから産業領域で臨床心理士や公認心理師としてキャリアを築きたい人へのアドバイスや心構えをお聞かせいただけますか?
森:まずは、「自分が誰のために何を提供したいのか?」を明確にすることですね。産業領域ではさまざまな利害関係が絡むので、それに流されないこと。困っているのは誰なのか、どのような支援が必要なのか、ブレないスタンスを持つことはすごく大事ですね。
あとはさっきも言った、ご縁を大切にすることですね。自分が思い描いている通りのキャリアにはならないかもしれませんが、目の前の機会に全力を尽くすことで、それが自分の道になっていくと思います。ぜひ腐らずに頑張ってみてください!
友村:今何をすべきかという軸を自分で持つことが大切、ということですね。今日お話しいただいたことは、産業領域に進もうか迷っている大学院生全員に、広く共有したいです!
森:ありがとうございます。私のような人間でも産業分野に入って10年生き残っていますので、皆さん大丈夫ですよ! やりたい方はぜひチャレンジしてください。
おわりに
インタビュー当日は、森さんの朗らかな話しぶりのおかげで、早々に緊張がほぐれたのを強く感じました。産業領域ならではの視点や考え方を、直接お話として拝聴できたことは、大変貴重な経験です。また、これは産業領域に限ったことではありませんが、「今を大切にすること」や「ご縁を大切にすること」が、現時点の私にできることなのだと改めて実感しました。将来、何をしたいのか、どのように成長していきたいのかを考えつつ、それを実現するためにひたむきに行動することの重要性に、今回改めて気づかされました。
特に印象的だったのは、「計画された偶発性理論」のお話です。一生懸命に取り組むうちに、失敗も成功もすべてが糧となり、そこに刻まれる轍がその人のキャリア形成につながっていくという内容でした。今後、どこかの段階で振り返り、あるいは先を見据えることで、さらにブラッシュアップにつながるとも考えています。その地点に至るまでに味わう苦労や広がる視野は、まさに自分自身のものであり、それらをすべて含めて良い思い出にしていけるのではないかと思います。貴重なお話をありがとうございました。
京都文教大学大学院 臨床心理学研究科
友村昌也
「大学連携型ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」のご紹介
龍谷大学大学院政策学研究科、琉球大学大学院地域共創研究科、そして京都文教大学大学院の3大学院が連携し、次世代のソーシャルイノベーション人材を育成するためのプログラムです。このプログラムでは、社会課題を多面的な視点から分析する力や、異なる領域の知見を統合し新たな価値を創出する力を養います。持続可能な社会の発展に貢献できる人材を育成することを目指し、臨床心理学の知見を活かしながら、社会課題解決に向けたイノベーションのプロセスやデザインを描けるイノベーション人材、そしてそのイノベーション人材を支援する心理専門家を育てていきます。
公式ホームページ:https://www.kbu.ac.jp/kbu/siprg/index.html