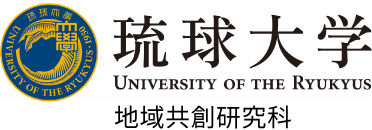Topics 2024 2024年度ニュース・プレスリリース一覧
2024.09.18
【ダイジェスト記事版】京都文教大学OBの起業家2人が語る「産業臨床心理学を活用したソーシャルイノベーションの起こし方」
はじめに
今回は、京都文教大学のOBであり、Neurodiversity at Work株式会社の代表取締役を務める村中直人氏と、Actors合同会社のCOO(最高執行責任者)を務める竹内良地氏の対談の様子をお届けします。
テーマは「産業臨床心理学を活用したソーシャルイノベーションの起こし方」です。
村中氏と竹内氏は、それぞれ京都文教大学で臨床心理学を学び、現在は会社を起業をして臨床心理学の知見を活かしたソーシャルイノベーションを事業としています。本インタビューでは、両氏が産業臨床心理学の知見をどのように事業に応用し、社会に貢献しているか、また今後の展望について深掘りしていきます。

-出演者紹介-
村中直人氏|Neurodiversity at Work株式会社代表取締役
1977年生まれ。2005年に京都文教大学大学院臨床心理学研究科を卒業。臨床心理士・公認心理師。一般社団法人子ども・青少年育成支援協会代表理事、Neurodiversity at Work株式会社代表取締役。多様なニーズのある子どもたちが学び方を学ぶための学習支援事業「あすはな先生」や「発達障害サポーター'sスクール」の運営に携わり、著書に『ニューロダイバーシティの教科書――多様性尊重社会へのキーワード』(金子書房)がある。 2024年7月17日発売の最新著書『「叱れば人は育つ」は幻想 』(PHP新書)は、発売即重版となりAmazonベストセラー1位(精神医学ノンフィクションカテゴリー)を獲得。https://amzn.asia/d/04wTdCpE
竹内良地氏|Actors合同会社COO(最高執行責任者)
2017年京都文教大学臨床心理学部を卒業後、ネスレ日本株式会社へ新卒入社。セールス及び企画業務を担当。2022年には人材・組織開発プロジェクトをオーナーとして率いて社内コンテスト「イノベーションアワード」を受賞。その後、ユニファ株式会社での勤務を経て、2023年よりActors合同会社の立ち上げに参画し最高執行責任者(COO)を務める。2024年にはラポトーク事業を立ち上げ、事業責任者に就任。その他、京都文教大学での「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」コーディネーターや、NPO法人カタリバでの不登校支援事業スタッフを務める。 ラポトーク公式HP:https://rapotalk.studio.site/
インタビュー全編は、ぜひYouTube動画をご覧ください。
https://youtu.be/EGu4_tt7HyE
- 自己紹介と現在の事業内容 -
竹内:
まず、簡単に私から自己紹介させていただきます。私は京都文教大学を卒業して、新卒でネスレ日本株式会社に入りました。その後にスタートアップ企業を経て、「Actors合同会社」という会社を立ち上げています。主に事業としては、ラボトークという、臨床心理士や公認心理師といった心理専門職の方々と産業領域をマッチングするビジネスをしております。
村中:
村中直人です。臨床心理士・公認心理師として、発達障害支援者の養成スクールや、学習支援事業を展開しています。最近は、「ニューロダイバーシティ」をキーワードに企業との仕事が増えており、特に発達障害の方々をはじめとする「ニューロマイノリティ」だけでなく、あらゆる人材を対象に「日本型ニューロダイバーシティ」を企業に推進しています。
竹内:
実は、村中さんとは7~8年前、私が大学卒業前後に初めてお会いし、飲みに行かせていただいたことを覚えています。
村中:
当時、まだネスレに入られる前ですね。あの出会いをつないでいただいたのは、濱野先生ですよね。
勢いのある学生だなという印象がありましたね。
竹内:
そうです、濱野先生のゼミ生だったので、そのご縁で村中さんをご紹介いただきました。
勢いで飛び込んで、村中さんから一対一で色々なアドバイスをいただきました。当時、僕は臨床心理学を学んでいて、それをビジネスにどう活かせばいいのか悩んでいたんです。先輩の事例もあまり見つからなかったので。
そんな中で、大学の先輩方が働いている様々な職場を訪問させていただき、その中で村中さんにお会いしたのですが、当時、とても印象的だったのが、村中さんが本当に自分の言葉で話しておられる姿でした。それがとても強く心に残っています。
村中:
そうだったのですね。
竹内:
他の方々からもいろいろお話を伺っていたのですが、多くの場合は会社の話や、いわゆる教科書通りの話が多かったんです。でも、村中さんは違って、全て自分の言葉で話されていて、それがすごく格好良いなと思いました。
なぜそう感じたのかを考えてみたのですが、それはきっと村中さんが自分でビジネスをやっているからだと気付きました。それが僕自身が起業を決意する一つのきっかけにもなり、村中さんは憧れの先輩です。
村中:
そうですね、あれは7年前くらいのことですね。今では「村中直人」として本を書かせてもらったり、メディアにも出るようになり、業界内でも「村中ね」と思ってもらえるようになってきましたが、当時はまだ本も書いていませんし、事業をしていると言っても、メディアにも全く出ていませんでした。世間的には無名の存在だったんです。
そんな時に、竹内さんが飛び込んできてくれて、一度だけですが一緒に食事をしたことが、竹内さんの印象に残っていたのは本当に嬉しいですね。
竹内:
もう強烈な印象がありましたね。
- 起業したきっかけ -
竹内:
あの時は起業されて、どれぐらい経っていたのですか。
村中:
7年前(2017年)ということは、ちょうど起業して10年経った頃ですね。事業としては10年を乗り切った時期です。「事業家ってこういうものなのか」と少しずつ理解できるようになってきた、事業家としての感覚が掴めてきたタイミングでした。
竹内:
その時はもう「あすはな先生」を立ち上げられていましたか?
村中:
あの時は7年前なので、ちょうどサポーターズスクールというスクール事業を始めた直後くらいでしたね。スクール事業自体は8年目くらいになると思います。私のタイミングとしては、一つの事業を立ち上げた後で、グループ会社として動いていたため、担当者を若手に任せつつ、私自身は新しい事業を立ち上げて1年目、2年目の頃でした。
事業の立ち上げは、これまでに2回、3回経験していますが、まさにその時が2回目の立ち上げに取り組んでいた時期でした。
竹内:
ちょうど私が起業したのが1年前くらいなので、新規事業を立ち上げたばかりの今の自分と、当時の村中さんの状況が重なる部分があります。
村中:
そうですね。あの時の私と被る部分があるかもしれないですね。
竹内:
あの時は、「なんでも頑張るぞ」という感じでしたか?
村中:
そうですね。当時は今より少し体力がありましたね。(笑)
ただ、何というか、当時から筋は見えていたというか、ストーリーがあったんです。私は臨床心理士として活動をする中で、子どもたちやその家族のニーズに出会い、それをサポートするための社会的資源がとても不足していることに気づき、「自分がやろう」と思いました。そこで最初に学習支援の事業を立ち上げた時に、「こんなにも支援者が足りないのか」と感じました。
でも、考えてみれば当たり前でした。当時、臨床心理士の養成課程では発達障害について学べる機会が非常に限られていたんです。今の若い世代は違うかもしれませんが、私たちの頃はそうでした。新しい法律や制度が急にできたけれど、それに対応する学びの場がほとんどなかったんです。
マーケティング調査をすることで、ニーズが確実に存在することが分かり、そのニーズにどれだけ応えられるかが課題だと考えました。ビジネスの筋としては、比較的、筋道を立てやすかったというのもありますね。
竹内:
僕自身もそうです。現場で、ターゲットとなる子どもや「この方のこういう課題を解決したい」という思いからビジネスを導き出すという部分は、心理を学んでいたからこそできることだと思っています。その人が抱える課題に自然と目が向き、「では、そこにどんなニーズがあるのか」「何が必要なのか」に気づく力があるのだと思います。
村中さんも、心理専門職としての立場だからこそ分かることや、臨床経験が活かされていると感じる部分はありますか?
- 心理専門職だからこそわかること -
村中:
そうですね。例えば学習支援に関して言えば、子どもたちに対してしっかりと見立てを立てるというのは、臨床心理士としてのトレーニングを受けていたので、当然のようにやっていました。今振り返っても、それは非常に重要なことだったと思います。つまり、サービスの内容を考える上で、臨床心理士のトレーニングを受けていて本当に良かったと感じています。
同時に、これは今後の心理専門職を支える若い世代にも伝えたいメッセージですが、私は子どもたちやその家族のニーズを見ると同時に、彼らが置かれている社会的構造にも強く関心を持っていました。
例えば、特別支援教育が2007年に始まった際、「この制度が始まってどうなるのだろう」と考えていました。特別支援学級が導入される一方で、この仕組みから外れてしまう子どもが多いと感じることがありました。今もそうですが、当時は制度が始まったばかりで困難が多く、その影響で転げ落ちる子が多かったです。
学校に通い続けるものの、授業中は「ぽかんとしているだけ」という子どもたちが多く、そういった子どもたちを支えるための社会的な仕組みや対応がないと感じました。
とはいえ、社会構造を大きく変えるだけの力はありませんでしたが、少なくともその社会構造の中で、その子どもたちの立ち位置を支える仕組みを作ろうと考えたのです。
臨床心理学の視点と、社会構造や社会的リソースを組み合わせて見る視点を、私は最初から持っていたので、それが起業しやすく、今の動きにもつながりやすかったのだと思います。
竹内:
そうですよね。心理学を活用して、それをどうビジネスに結びつけるかという時に、心理学的な視点とビジネスの視点、その両方を回せる思考や行動がとても重要になってきますよね。
村中:
そうですね。もう少し具体的に言うと、社会構造にどのような仕組みが必要か、どんな仕組みが求められているのかという発想が非常に重要です。社会の仕組みだけでなく、事業やサービスの仕組みについても、どう作っていくかが鍵になります。
臨床心理学の言葉で言うと、それは「構造」の話になりますが、この「構造」を面接の構造だけでなく、もっと広い視点で「サービスの構造」や「社会構造」として捉えていくことが大切です。これからは、そういった視点がますます重要になってくると思います。そして、その中に臨床心理学的な視点を取り入れることで、両方の要素が活きてくるのではないかと考えています。
-「社会構造」における臨床心理学の活用 -
竹内:
そうですね。まさに村中さんがよくおっしゃっているように、臨床心理士の方々には、もっと活躍できるフィールドがたくさんあると思います。僕もそう感じていて、この「ラポトーク」という事業は、心理専門職の方々の雇用創出を一つのビジョンとして掲げています。そのビジョンを達成するためには、やはり心理専門職の方々にも少しマインドチェンジが必要だと思っています。これまでは教育や医療福祉などの領域で活動されている方が多いですが、産業領域という少し異なる分野に進出する際には、そのマインドチェンジが不可欠であり、そこに一緒に取り組んでいる状況です。
村中:
具体的には、どのようなことが必要だと思いますか?
竹内:
そうですね。まず、共通言語がないことが一つの問題点だと感じています。心理専門職の方々が持っているスキルと、産業領域で認識されていることの間にギャップがあります。産業領域では「心理専門職はメンタルヘルスを担当するものだ」というイメージが強く、「守り」の部分にフォーカスされがちです。もちろん、メンタルヘルスのニーズは非常に大きいですが、それだけでなく、「攻め」の部分、つまり「人材開発」や「組織開発」にも心理専門職が入り込める余地があると考えています。ここには、「ニューロダイバーシティ」という概念も関わってくると思います。
村中:
「攻め」の部分、そうですね。竹内さんがおっしゃるように、共通言語がないというのは私も感じています。具体的に何をするかというソフトの部分と、それを支える構造の部分を考えた時に、社会の構造にアクセスする際にキーワードが非常に重要だと思っています。私が重視しているキーワードは「ニューロダイバーシティ(脳の多様性)」です。この言葉は学術的に定義されたものではなく、ソーシャルアクションの中で生まれてきたものです。学術的な定義は存在しませんが、企業と接続するための言葉として非常に使いやすいです。なぜなら、特定の利害に抵触せず、企業が取り組む理由を持たせることができるからです。
たとえば「組織開発」というテーマは非常に重要ですが、それだけでは企業は動きません。「組織開発のためにこれをする」という形で、何かしらの行動理由が必要になってくるのです。
竹内:
その通りですよね。
村中:
私も「ニューロダイバーシティ」というキーワードを使ってコミュニケーションする際には非常に注意しています。例えば、この推進について「具体的に何をするのか」を企業に説明する時は、「認知的多様性と心理的安全性のバランスを高水準で取ること」が推進の本質だと説明しています。「認知的多様性」とは、物の考え方や感じ方、情報処理の違いのことです。心理専門職が言う「認知」に相当します。この多様性が組織内で高く担保されると、多様な人材が一つのチームとして働けるようになります。
臨床心理学の領域だけではなく、産業やイノベーションの研究においても、「認知的多様性」がイノベーション創出のベースであることが確認されています。「認知的多様性」が高ければ必ずしもイノベーションが生まれるわけではありませんが、低ければイノベーションは生まれないということは確かです。
では、なぜ「認知的多様性」が高い企業でイノベーションが生まれる企業と生まれない企業があるのか。その分かれ目は「心理的安全性」にあります。「認知的多様性」を高めるほど、「心理的安全性」に危機が訪れるのです。これは、発達障害の方々が一番分かりやすく教えてくれることです。発達障害の方が一人いるだけで、その場の認知的多様性が飛躍的に高まります。しかし、それに伴い「心理的安全性」の危機が訪れ、抑圧や排除、攻撃といった問題が発生することもあります。
つまり、「認知的多様性」と「心理的安全性」はトレードオフの関係にあり、どちらかを広げればどちらかに問題が生じます。心理的安全性を簡単に高める方法は、似たような考え方を持つ人たちで仕事をすることですが、そこから新しいアイデアは生まれません。このジレンマに企業は向き合う必要があります。
現在、企業は「人的資本経営」や「イノベーション創出」というキーワードで取り組んでいますが、具体的な施策が少ないのが現状です。そこで「ニューロダイバーシティ」というキーワードを用い、認知的多様性と心理的安全性を高め、全員がそれぞれの強みを活かしながら新しいことに挑戦できる環境を作ることが重要だと考えています。しかし、現状では臨床心理士のスキルや知識がそのまま産業に活かされるのは難しい部分もあると思います。
- イノベーション実現において、心理専門職に必要なソフトスキル -
竹内:
そうですね。おっしゃる通りだと思います。今、企業の中でもイノベーションが一つのテーマになっていますが、それは一人では生まれません。チームとしてどのようにイノベーションを進めていくかというときに、「どう組織を作っていくのか」「どのように人材開発を進めていくのか」が重要です。村中さんの考え方は、この点で非常に大切だと思っています。
私たちも、臨床心理士の方々を企業に派遣するにあたって、必要なソフトを開発することで、企業をサポートしていきたいと考えています。
村中:
今、立ち上げたばかりですが、反響はどうですか?
竹内:
そうですね。特に人事部門の方々からは非常に良い反響をいただいています。今まで「健康経営」や「自己資本経営」に取り組んでいたものの、現場で何をすれば良いのか分からないというニーズが非常に強いです。実際に現場にどう介入するかが求められていると感じますね。
村中:
なるほど。具体的に、どの部分に人事部門の方は興味を持っているのでしょうか?
竹内:
基本的には、管理職をターゲットにした研修を行っているのですが、管理職の方々が「組織のパフォーマンスをどう向上させるか」、つまり「人材開発」という視点で部下の育成にどう取り組むかに非常に関心があります。また、村中さんがおっしゃっていたように、チームを作る際に、多様な人材が互いを認め合い、そのアイデアを共有しながらイノベーションを生むようなチームを作ることが目標です。
そのため、管理職向けの研修の中で「チームビルディング」をメインに据えています。現在、京都文教大学の川畑先生にその設計をお願いさせていただきました。
村中:
私が大学院に在学していた頃のゼミの先生ですね。なるほど、ありがとうございます。
-「レンガモデル」と「Ishigakiモデル」-
村中:
この動画を見ている方の中には、私たちがイノベーションという言葉を当たり前に使っているのを聞いて、少し馴染みがない方や、苦手意識を持っている方もいるかもしれません。そこで少し補足をさせていただきますね。私たちが使っている「イノベーション」という言葉は、例えばアップルがiPhoneを作ったような革新的なプロダクトを生み出すという意味だけではありません。もっと平易に言うと、「新しいことをする」ことがイノベーションです。そして、その新しいことが後々スタンダードになっていく。そうなると、「イノベーションが生まれたね」という話になるのです。要は、今までにやらなかった新しいことをやることがイノベーションの本質です。
これが意外と難しいのです。組織には「経営の依存性」というものがあり、一度うまく回る仕組みができると、その仕組みに依存してそのまま進んでしまうという慣性の法則が働きます。同じことを続ける方が楽で、やりやすいのです。しかし、現代の市場環境は、同じことを続けることを許してくれません。たとえ過去に大成功した企業でも、変化しないと衰退してしまう。だからこそ、常に新しいことを続けなければならないのです。
新しいことを続けるためには、それを可能にする仕組みが必要です。ここで私は「Ishigaki(石垣)モデル」をよく話題にしています。「Ishigakiモデル」に対して「レンガモデル」というのもありますね。実は今年(2024年)の1月の日経新聞に「レンガモデル」と「Ishigakiモデル」についての記事が掲載されました。取材も受けたので、堂々とこの話ができます。
「レンガモデル」は、人間を一つの規格化された形として扱うモデルです。このモデルはスクラップアンドビルドが容易で、部品を入れ替えることが簡単なので、新しいチームを作るのに適しています。だから、採用時には「コミュニケーション能力」を重視するという考えが根付いていたのです。けれども、この「コミュニケーション能力」というのは、「レンガモデル」的な発想のもとで、誰とでもうまくやれる力を意味していたのです。しかし、このモデルの最大の弱点は「変化に弱い」という点です。
日本は地震が多い国なので、レンガ作りが馴染まなかったという説があります。その代わりに作られたのが石垣です。石垣は揺れに強く、豊臣秀吉が作った大阪城の石垣は今でも残っています。それは、石が接着剤で固定されているわけではなく、自然の形をうまく組み合わせて作られているからです。
企業の組織作りにも、石垣作りに似たものがあると思います。人は規格化されたレンガではなく、皆が異なる形をしている。そのため、石垣のように、それぞれの個性を活かしながら組み合わせていくことが求められます。しかし、この方法にはデメリットもあり、チームを組み上げるのが大変です。石垣作りには、マネージャーの意識改革が必要です。レンガモデル時代のマネージャーがしていた仕事とは全く違うものになります。
特に心理学と関連させると、上司が部下一人ひとりの個性や特性を見分ける力が大切です。心理専門職の見分ける力がなければ、石垣作りはうまくいきません。そこで心理専門職の役割が非常に重要だと思っています。
- 課題解決のための「Ishigaki(石垣)モデル」的な仕組み -
竹内:
非常に理解できます。私が「ラポトーク」というサービスを立ち上げようと思ったきっかけがまさにその考え方です。以前、村中さんにご相談していたこともありますが、ネスレで「イノベーション・アワード」を取ろうと挑戦していた際、どうやって取るのかを壁打ちのように相談させていただきました。最終的に取ることができましたが、そのプロジェクトは、2020年のコロナ禍で全員がリモートワークになったときに始まったものです。
リモートワークで孤独感やキャリアへの不安が顕在化し、何とか解決したいと考えました。取締役に直接提案し、プロジェクトを通じて解決しようという話になりました。週に一度、一人ひとりと1on1で話す時間を設け、ルールとして否定も肯定もせずにただ話を聞き合うという形式を取りました。それをリモートで実施し、100人ほどの部署で新入社員から取締役まで全員が参加しました。
結果として、横のつながりができ、過去最高の利益と売り上げを達成しました。このプロジェクトが大きな要因だったと取締役の方も評価してくれました。コミュニケーションの方法を変えただけですが、それだけで大きな成果を生んだことが私にとっての原体験となりました。それが「Ishigakiモデル」と通じるものがあると感じました。
村中:
そうですね。そのお話は以前にも伺ったことがありますが、今のお話につなげると、竹内さんのプロジェクトがうまくいったのは、ソフトとハードの仕組みを絶妙に組み合わせたバランスが大きかったのではないかと思います。先ほどもお話ししましたが、「コロナ禍でコミュニケーションが不足しているので、他のメンバーともっとコミュニケーションを取ろう」と声をかけただけでは、多分うまくいかなかったでしょう。また、「食事会をしてみんなで話し合おう」といった施策も、恐らく同様に成功しなかったと思います。
定期的にスケジュールされ、プロジェクトリーダーがそれを管理する仕組みが導入されていたからこそ、うまくいったのです。ソフトや仕組みの設計が非常に重要で、すごく良い仕組みを作っていたと改めて感じました。
竹内:
ありがとうございます。
- 産業領域における心理専門職の働き方の多様性 -
竹内:
この動画を心理専門職の方々もご覧になっているので、彼らにとっては、個人にフォーカスした心理支援から、組織や仕組み作りに介入していくにはマインドチェンジが必要だと思います。もちろんスキルも必要です。そのあたり、どう考えればいいのでしょうか?
村中:
仕組みや構造の話は、例えば起業されている方や面接室を運営する責任者であれば意識していると思います。面接の構造や時間配分、ルールなどですね。そういった発想を持っている方は、その対象を拡大するだけで良いと思います。そうでない方は、一度プチ起業をして、週末にカウンセリングルームを開くだけでも良いでしょうし、大学であれば相談室の責任者をやってみるのも良い経験になります。
枠組みをコントロールする立場になることで、「枠組みを変えるとこんなに影響があるのか」と実感できると思います。それは臨床のトレーニングでも言われていることで、構造がどれだけ影響を与えるかを実感できる心理専門職は多いと思います。「これなら自分に向いている」と感じた方は、ぜひ産業領域に進出してほしいです。活躍の場はたくさんあります。
竹内:
私が「ラポトーク」を立ち上げた理由の一つは、心理専門職の方々がこれからどんどん個人事業主化していくのではないかと思っているからです。自分自身の市場価値を高めることが重要で、自分が提供できる価値を認識し、自分で仕事を取っていくスタンスが求められると思います。産業領域との接点に私たちのサービスがなれればと考えています。
村中さんは臨床心理士として活動された後に起業されていますが、そのあたりはどのように取り組んでこられたのでしょうか?
村中:
そうですね。私は比較的早い段階で、「自分でやっていかないといけないな」と感じていました。以前のインタビューでもお話ししましたが、スクールカウンセラーをしていた時、給料がどんどん減っていく経験をしました。それだけではなく、既存の枠組みの中では本当に必要なことや自分のやりたいことが制限されるという実感もありました。
その枠組みの中でできることを一生懸命やるのも大事ですが、それを越えてやりたいことがあるなら、自分で作るしかないと思いました。当時は、法人を立ち上げて自分たちでやる以外の選択肢が浮かばなかったので、そうしました。
ただ、必ずしも法人を立ち上げなくてもいいと思います。非常勤で働きながら別の仕事をする併用型の働き方や、既存のプロジェクトに参画して学ぶ方法もあります。個人事業主になるのはもちろんですが、「働き方の多様性」が重要だと思います。常勤か非常勤か、非常勤なら病院か学校かだけではなく、自分の選択肢を広げて、「選択肢がこんなにあるんだ」と気づいてもらえると良いですね。
竹内:
そうですね。本当にいろいろな選択肢があると思います。自分のライフプランやキャリアに合わせて選び、進んでいくことが良いと思いますし、私たちのサービスとも協業できるかもしれません。
ソーシャル・イノベーションという観点から、臨床心理士の方々がソーシャル・イノベーション実現を目指す際に、産業領域と心理学の両方を知っている私たちが迎え入れる心理専門職の方々には、どのようなマインドや準備をして産業領域に入ってきてほしいと考えていますか?
村中:
それを言語化するのは非常に難しいですね。どうでしょうかね。
竹内:
私も今リクルーティングをしている中で、非常に悩んでいる部分でもあります。
村中:
私たちが起業してもうすぐ20年になりますが、実感として、最近はその人が何を言っているかよりも、実際に何をやってきたかを重視するようになりました。「やるやる」と言って何もやらない人も多い中で、竹内さんのように一度会っただけで、その後実際に事業を立ち上げ、ローンチしている方もいます。結局、やる人はやるし、やらない人はやらない、という感じですね。
竹内:
どの業界でもそうですよね。
村中:
だから、今はその人の行動の軌跡を重視しています。何を言っているかよりも、何を実際にやってきたかの方が重要です。ただ、これは少し諸刃の剣でもあります。実績のある人でなければ組めなくなってしまうので、若い方々と組むのが難しくなるんですよね。それでも、学生時代からいろいろな活動をしていた人は、やる気があることが最初から分かります。「私はこれを感じて、こう考えたからこう行動した」ということを自分の言葉で語れる人と一緒に仕事をしたいですね。
竹内:
本当にそう思います。その人がどういう経験をしてきたかが、その人を物語るものです。それを経て、私たちと一緒に働いていける人なら良いなと思います。その意味でも「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」に興味を持って参加する方は、私たちにとっても嬉しいことですし、共通点になるポイントだと思います。
村中:
そうですね。そのようなプログラムに参加している人は、すでにそういった意識を持っているということが分かります。実績の指標としても分かりやすいですよね。
竹内:
はい、ありがとうございます。
こうして憧れの先輩とお話しできて、とても嬉しいです。ありがとうございました。
村中:
楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございました。
「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」公式ホームページ
https://www.kbu.ac.jp/kbu/siprg/index.html
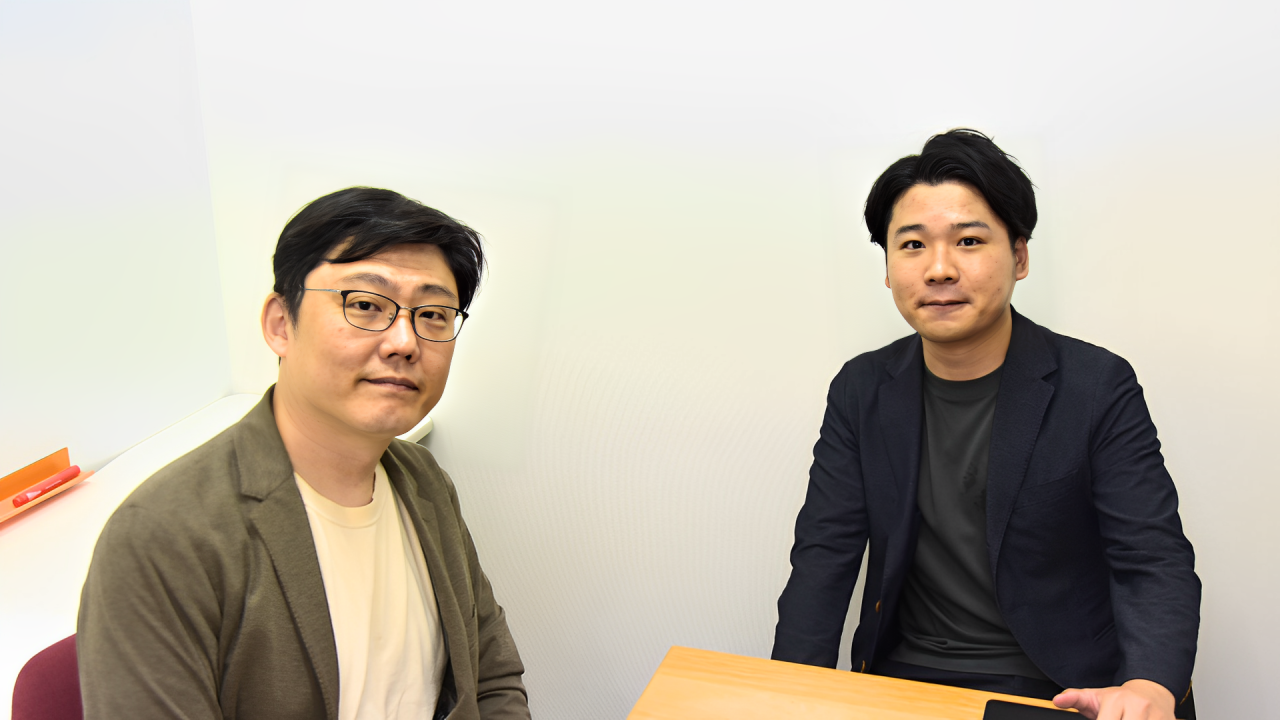
お問い合わせ窓口
京都文教大学大学院臨床心理学研究科(大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム担当)
〒611-0041 京都府宇治市槇島町千足80
お問い合せフォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXy4M4_xmAHPJu0lFeUyrG-comYT_mSQrCZosOwUWS1By73Q/viewform