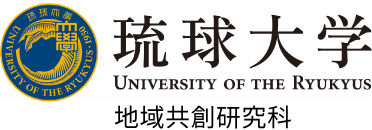Topics 2024 2024年度ニュース・プレスリリース一覧
2024.08.26
【ダイジェスト記事版】京都文教大学OB起業家・竹内良地氏が語る「心理専門職の雇用を創出するソーシャルイノベーション」
はじめに
今回は、京都文教大学のOBでありActors合同会社のCOO(最高執行責任者)を務める竹内良地氏に、現在同大学院に在籍し将来は産業領域で活躍する臨床心理士を目指す吉岡優那さんがインタビューをした様子をお届けします。
テーマは『ソーシャルイノベーションと産業臨床心理学』です。
本インタビューでは、竹内氏が産業臨床心理学の知見をどのように事業に応用し社会に貢献しているのかを深掘りし、今後の展望をお伺いしました。
出演者紹介
スペシャルゲスト:竹内良地氏(Ryoji Takeuchi)
2017年京都文教大学臨床心理学部を卒業後、ネスレ日本株式会社へ新卒入社。セールス及び企画業務を担当。2022年には人材・組織開発プロジェクトをオーナーとして率いて社内コンテスト「イノベーションアワード」を受賞。その後、ユニファ株式会社での勤務を経て、2023年よりActors合同会社の立ち上げに参画し最高執行責任者(COO)を務める。2024年にはラポトーク事業を立ち上げ、事業責任者に就任。その他、京都文教大学での「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」コーディネーターや、NPO法人カタリバでの不登校支援事業スタッフを務める。
ラポトーク公式HP:https://rapotalk.studio.site/
インタビュアー:吉岡優那(Yuna Yoshioka)
2024年 京都文教大学大学院 臨床心理学研究科 博士前期課程2年に在籍。修了後は産業領域で活躍する臨床心理士を目指している。
インタビュー全編は、ぜひYouTube動画をご覧ください。
https://youtu.be/Ze0QqX62qOo
インタビュー内容ダイジェスト
インタビュー実施日:2024年7月3日(水)
-ライフビジョンや現在の仕事-
吉岡:竹内さん、本日はどうぞよろしくお願いします。まず、竹内さんの現在のお仕事内容やビジョンについて教えていただけますか。
竹内:よろしくお願いします。私のライフビジョンは「子どもたちが将来にワクワクできる環境をつくる」ことです。そのビジョンを達成するために、まずはビジネスパーソンがワクワク働ける環境を作りたいと思い、「ラポトーク」という事業を始めました。そこで事業責任者を務めています。ラポトークは、臨床心理士や公認心理師などの心理専門職の雇用創出を目指しており、ビジネスパーソンにカウンセリングやコーチングを提供するサービスです。
ラポトーク公式HP:https://rapotalk.studio.site/
-キャリアの歩み-
吉岡:なぜそのようなキャリアを歩もうと思ったのか教えてください。
竹内:3つの経験が影響しています。1つ目は高校時代の不登校経験です。小学生からサッカーを始め、自分の自己表現の場だったサッカーを辞めたことが大きなショックでメンタル不調になりました。その際、スクールカウンセラーさんに助けていただいたことが一つ目の原体験です。2つ目は、中学生時代に父親が起業して失敗した経験です。父親のチャレンジ精神を尊敬し、彼が40歳で起業したことを知って、私も40歳までに起業したいと思うようになりました。3つ目は、養子として迎えた家族との関係があります。その子が来た背景などに関心を持つようになり、家族とは何かということに興味を持つようになりました。これらの経験があり、私自身が将来にワクワクできる環境ではなかったことから、次の世代の子どもたちには将来にワクワクしてほしいと思い、まずはビジネスパーソンがワクワク働けるような環境を作る現在の事業を行っています。

-学生時代に臨床心理学から学んだこと-
吉岡:学生時代に臨床心理学で学んだことについて教えてください。
竹内:臨床心理学部でカウンセリングを通じたコミュニケーションスキルを学び、それが社会に出てからも非常に役立っています。営業の仕事でも商談の中でラポール(信頼関係)を築くことが重要で、カウンセリングのスキルを応用できました。
また、課外活動としていくつかの活動をしました。不登校の子どもたちを支援するボランティアでは、自分の不登校経験をもとに、不登校の子どもたちに貢献したいと思って始めたボランティアでしたが、関わる子ども達からたくさんのことを学びました。児童養護施設でもアルバイトをしていました。まさに自身の家族が来たバックグラウンドに興味を持ち始めたのがきっかけです。多様なバックグラウンドを持った子ども達や、迎え入れる施設スタッフの方々との交流を通じて、実体験として多くのことを学びました。東日本大震災の復興支援のボランティアとして、岩手県大船渡市で住み込みのバイトをしました。そこではバス停等で無料でお話をお伺いする「聴き屋」というボランティアを行いました。ある日、50代くらいの女性の方が「お兄ちゃん、何してるの?」と声をかけてくださり、そこから15分ほどその方の色んなお話をお伺いしました。最初は、少し顔が曇っていた様子でしたが、バスが来て、その方が乗り込む際に「お兄ちゃん、ありがとう!」といってくださったときの笑顔が印象的で、「聴くことにはすごい力があるんだ」と強く感じました。私はお話を聴いただけでしたが、そのタイミングだけでもその方をポジティブに変えることができたことが、大きな経験となりました。
吉岡:これまで子ども福祉のお話が多くありましたが、なぜ大学卒業後は、子ども福祉ではなく産業領域に進まれたのですか?
竹内:就職活動時には、新卒で子ども福祉の分野に進むつもりでしたが、アルバイトをしていた児童養護施設の施設長から「新卒で児童養護施設に入職してくれるのも嬉しいが、ビジネスに行ってから戻ってきてもらった方が、子ども達に多様なキャリアを知ってもらえるし、施設としても運営に携わってもらえるため、よりありがたい存在になる」という言葉をいただき、ビジネスの方へ進む決断をしました。
-子どもと関わる上で難しかったことや苦労-
吉岡:これらのご経験を通じて様々な人と関わる中で、難しかったことや苦労したことはありますか?
竹内:児童養護施設で働いていた時は、色んな特性を持ったお子さんがおられました。子ども同士の喧嘩の仲裁に入る際も、それぞれの子ども達の特性を踏まえた対応をしました。例えば、覚えている範囲で出来事を時系列に書き留めて、子ども達同士が客観的に把握できるようにしました。そこは、臨床心理学を学んで知識があったからこそ、そういった仲裁の仕方ができたのかなと思います。
-大学卒業後のキャリア形成-
吉岡:大学卒業後は、どのようなキャリアを形成されてきましたか?
竹内:京都文教大学臨床心理学部を卒業してからは、ネスレ日本株式会社に入社し、営業と営業企画の仕事をしました。その後、スタートアップ企業への転職を経て、昨年独立し、ネスレ時代の同期と共にActors合同会社を立ち上げました。
吉岡:私は将来は臨床心理学を活用して産業領域で働こうと思っていますが、竹内さんが起業しようと思ったキッカケは何ですか?
竹内:起業を志したのは父親の存在が大きいと思います。父親が起業をしていたので、40歳までには自身も起業をしたいと思っていた事が、起業の動機としては大きいと思います。私自身が新卒で就職をする際に、正直臨床心理学がどう活きるのかイメージしづらかったです。ただ、試行錯誤する中で、あるプロジェクトが上手く行ったという経験がありました。そのプロジェクトは、コロナ禍で顕在化した社員の孤独やキャリアの不安を、社員同士で聴き合う機会を提供することで解決するプロジェクトでした。事業としてもその年がコロナ禍でありながら過去最高の売上と利益を達成し、役員からもその要因の1つがこのプロジェクトだったと成功事例として言及をいただきました。社員同士がお互いの話を聴き合うということをしただけで、これだけの成果がありました。それはまさに、臨床心理学の傾聴というコミュニケーションスキルがビジネスで応用できたという事例でした。
吉岡:それを聴いていると、「話す」「聴く」というのがいかに大事かがわかりますね。
-臨床心理学の事業への応用-
吉岡:臨床心理学の知見をどのように事業に応用していますか。
竹内:今行っているラポトークという事業において、臨床心理学の知見をビジネスに応用しています。ビジネス現場では聴き合う文化があまりないため、信頼関係が構築されていない中で業務の話ばかりしてしまい、結果としてディスコミュニケーションが起こることがあります。そこを解決するために、ラポール(信頼関係)を形成するスキルが応用できると思っています。私たちのサービスでは、ラポールを構築するためのトークという意味で「ラポトーク」というサービス名にしました。京都文教大学の先生方にもご協力をいただき、事業を設計しています。
-ソーシャルイノベーション実践における成功事例や課題-
吉岡:ソーシャルイノベーションの実践における成功事例や直面した課題について教えてください。
竹内:ラポトークというサービス自体がソーシャルイノベーションに繋がると思っており、これから事業を伸ばしていきたいと考えています。
課題としては、これまで心理の領域と産業の領域が交わってこなかったため、双方に共通理解がないという点があります。この課題に対して、臨床心理学を学び、ビジネスを経験してきた私自身がパイプ役となることで解決していきたいと思っています。
-産業領域から見た心理専門職に知って欲しいこと-
吉岡:私は心理専門職の側から産業領域を見ていますが、逆に産業領域から見て心理専門職に知って欲しいことはありますか?
竹内:心理専門職が企業で採用される際、募集要項で人事経験が問われるケースが多いのは、産業現場のリアルな課題感を理解してほしいという企業からのメッセージだと思います。日々のカウンセリング等の臨床現場で、産業現場で働く方々の課題感をしっかりとキャッチアップすることが大事です。これは実際に産業領域で活躍されている心理専門職の共通点でもあると思います。
吉岡:心理専門職として企業に入る立場でありながら、組織の一員になるということですね。
竹内:まさにそうです。
-今後の展望やビジョン-
吉岡:今後の展望やビジョンについて教えてください。
竹内:ラポトークをしっかりと伸ばしていきたいと思っています。この事業が成長することで、心理専門職の雇用を創出できます。ラポトークを通じて、産業領域で活躍できる心理専門職を増やし、産業領域の様々な課題を解決したいと思っています。現代の産業領域では人的資本経営や健康経営が注目されており、社員一人一人を大切にすることが各社の重点課題となっています。そういった領域に心理専門職のスキルを応用し、貢献したいと考えています。
-視聴者の皆様へのメッセージ-
吉岡:最後に視聴者の皆様にメッセージをお願いします。
竹内:私は臨床心理学部を卒業して、すぐに産業領域に進みました。当初は臨床心理学のスキルがどのように役立つかイメージしづらかったですが、現代の産業領域では傾聴スキルやメンタルケアのスキルが非常に求められています。心理専門職を目指す皆様は産業領域で求められている存在です。ぜひ、そういった視点を持って心理専門職の勉強を続けていただければと思います。
-最後に-
吉岡:ソーシャルイノベーション人材養成プログラムの詳細については、公式ホームページからご覧いただけます。ぜひご参加ください。本日はご視聴いただき、ありがとうございました。
「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」公式ホームページ
https://www.kbu.ac.jp/kbu/siprg/index.html
お問い合わせ窓口
京都文教大学大学院臨床心理学研究科(大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム担当)
〒611-0041 京都府宇治市槇島町千足80
お問い合せフォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXy4M4_xmAHPJu0lFeUyrG-comYT_mSQrCZosOwUWS1By73Q/viewform